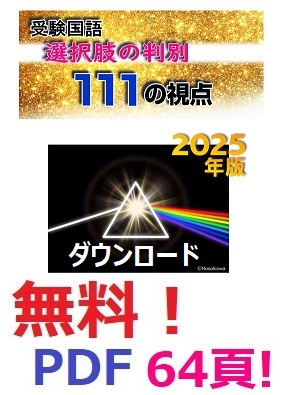中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■記事
・正味64ページ(両面17枚)
・本編約103,000字
■PDFデータ量
・7.51MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
・枚数:全17枚(表紙1枚含む)
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
万葉集(通釈)
論理パズル
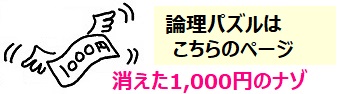
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
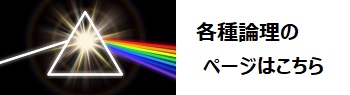
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
万葉ゆにばーす
■初期万葉、万葉隆盛期、万葉最盛期、万葉衰退期、東歌、防人歌……古典三大歌集の一つ『万葉集』に収録された代表的な作品を通釈しました。私たちの祖先が暮らしていた古代日本の情趣を味わいながら時の流れを超えた宇宙の旅を楽しみましょう!
■以下の文献を参考にしました。
・古典解釈シリーズ 文法全解 「万葉集」(大久保廣行著)旺文社
・「通解 名歌辞典」(武田祐吉・土田知雄共著)創拓社
目 次
■第一期 作歌群(初期万葉 近江期以前 629年~672年)
1:結婚しようよ(雄略天皇)
2:期待はずれ(舒明天皇)
3:ビューティフル・ヤマト(舒明天皇)
4:はかない望み(有間皇子)
5:金弭の音(中皇命)
6:三角関係(天智天皇)
7:雄大壮麗(天智天皇)
8:秋山の勝ち(額田王)
9:秋の風(額田王)
10:困った人ね、あなたったら(額田王)
11:恋せずにはいられないんだもの(大海人皇子)
■第二期 作歌群(万葉隆盛期 飛鳥・藤原期 672年~710年)
1:風薫る(持統天皇)
2:春になったよ(志貴皇子)
3:いわゆるグレートなランドスケープ(柿本人麻呂)
4:麻呂はちょっぴりセンチメンタル(柿本人麻呂)
5:追憶の日々(柿本人麻呂)
6:戯れ(天武天皇)
7:応酬(藤原夫人)
8:不穏(大伯皇女)
9:祈り(大伯皇女)
10:従容(大津皇子)
11:悲痛(大伯皇女)
12:あなたのために(作者未詳/柿本人麻呂歌集より)
13:姿(作者未詳/柿本人麻呂歌集より)
14:鶴鳴き渡る(高市黒人)
■第三期 作歌群(万葉最盛期 奈良時代前期 710年~733年)
1:濁り酒(大伴旅人)
2:酒壷になりたい(大伴旅人)
3:よっぱらいの一言(大伴旅人)
4:酔臥(大伴旅人)
5:面影(大伴旅人)
6:酔眼(大伴旅人)
7:唐より愛をこめて(山上憶良)
8:子どもたちよ(山上憶良)
9:生まれてきてくれて、ありがとう(山上憶良)
10:嘆息(山上憶良)
11:悟り(山上憶良)
12:薫ふがごとく(小野老)
13:微笑(大伴坂上郎女作)
14:そこはかとなく(大伴坂上郎女作)
15:メッセンジャー(大伴坂上郎女作)
16:麗容(山部赤人)
17:若の浦(山部赤人)
18:夕景(山部赤人)
19:静寂(山部赤人)
20:野辺にて眠る(山部赤人)
21:春雪(山部赤人)
22:真間の手児奈よ(高橋虫麻呂)
23:真間の井(高橋虫麻呂)
24:浦島太郎(高橋虫麻呂)
25:夕月夜(湯原王)
■第四期 作歌群(万葉衰退期 奈良時代中期 734年~759年)
1:嘆きの歌(元興寺の僧)
2:うなぎの人・パートⅠ(大伴家持)
3:うなぎの人・パートⅡ(大伴家持)
4:紅にほふ(大伴家持)
5:純白(大伴家持)
6:可憐(大伴家持)
7:憂愁(大伴家持)
8:幽玄(大伴家持)
9:哀傷(大伴家持)
10:ハッピー・ニュー・イヤー(大伴家持)
11:片想い・パートⅠ(笠郎女)
12:片想い・パートⅡ(笠郎女)
13:母の純愛(作者未詳
■東歌
1:旅の宿り
■防人歌
1:出立の朝
2:思慕
第一期 作歌群(初期万葉・近江期以前・629年~672年)
結婚しようよ(雄略天皇/ゆうりゃくてんのう)
籠(こ)もよ み籠(こ)持ち
ふくしもよ みぶくし持ち
この岡に 菜(な)摘(つ)ます子
家聞かな 告(の)らさね
そらみつ 大和の国は
おしなべて われこそ居(お)れ
しきなべて われこそ座(ま)せ
われにこそは 告(の)らめ
家をも名をも
・第二十一代、雄略天皇
・万葉集、巻一、万葉集開巻第一の歌
よいかごを手に持ち
よいへらも手に持って
この岡で
菜を摘んでおられる
娘さん
あなたのお家が聞きたい
あなたの名をおっしゃいな
この大和の国は
すべて
この私が従え
治めているのです
その私にこそは
教えてくれるでしょう
あなたの家も名をも
・名前には神秘な霊魂が宿る。名前を相手に告げることは、わが身の霊魂を相手に捧げ、相手に心身を委ねること、つまり求婚への承諾となる。
期待はずれ(舒明天皇/じょめいてんのう)
夕されば
小倉の山に鳴く鹿は
今夜(こよい)は鳴かず
い寝にけらしも
・第三十四代、舒明天皇
・万葉集、巻八
夕方になると
いつも決まって鳴く小倉の山の鹿は
今夜に限って鳴かない
さては
妻を得て
安らかに寝てしまったらしい
・鹿は妻を恋い慕って鳴く。
ビューティフル・ヤマト(舒明天皇/じょめいてんのう)
大和には
群山(むらやま)あれど
とりよろふ
天の香具山
登り立ち
国見をすれば
国原(くにはら)は
煙(けぶり)立ち立つ
海原(うなはら)は
鴎(かまめ)立ち立つ
うまし国ぞ
蜻蛉島(あきづしま)
大和の国は
・第三十四代、舒明天皇
・万葉集、巻一
この大和の国には
多くの山々があるけれど
中でも美しく整った
天(あめ)の香具山(かぐやま)よ
この山に登り立ち
国内を見渡すと
広々とした国土に
炊煙(すいえん)があちらにも
こちらにも立ち昇(のぼ)っている
埴安(はにやす)の池の広い水面には
一面に水鳥たちが
あちらに飛び立ち
こちらに飛び立ちしている
すばらしい国よ
この大和の国は
はかない望み(有間皇子/ありまのみこ)
磐代(いわしろ)の
浜松が枝(え)を引き結び
ま幸(さき)くあらば
また還(かえ)り見む
・有馬皇子:孝徳天皇の皇子
・万葉集、巻二
和歌山は
磐代(いわしろ)の浜辺に生えている
松の枝と枝とを引き結び
無事であったならば
再びここへ帰って
これを見よう
無事であったならば
・大化の改新後、謀反の疑いで護送される途中紀伊の磐代で詠んだ歌で、この歌を詠んだ磐代までは戻れたが、直後藤白にて絞首に処せられた。時に十九歳。
・長寿の象徴である松の枝と枝とを引き結んで自分の魂を結び留めておくと、無事に再びそこへ帰って来ることができる。
金弭の音(中皇命/なかつすめらみこと)
やすみしし
わご大君(おおきみ)の
朝(あした)には
とり撫(な)でたまひ
夕(ゆうべ)には
い倚(よ)り立たしし
御執(みと)らしの
梓(あづさ)の弓の
金弭(かなはず)の音すなり
朝猟(あさかり)に今立たすらし
暮猟(ゆうかり)に
今立たすらし
御執(みと)らしの
梓の弓の
金弭(かなはず)の音すなり
・中皇命:天智天皇の妹
・万葉集、巻一
わが大君(おおきみ)が
朝は手に取り
夕べには
その傍(そば)に寄り立って
お慈(いつく)しみになる
ご愛用の梓(あずさ)の弓の
金弭(かなはず)の鳴る音がする
朝の狩(かり)に
今お出かけになるらしい
夕べの狩に
今お出かけになるらしい
ご愛用の梓の弓の
金弭(かなはず)の鳴る音が聞こえる
・金弭:弓の両端の弦をかける部分(弭)が金属製になっている。
三角関係(天智天皇/てんじてんのう)
香具山は
畝火を愛(お)しと
耳梨と相争(あいあらそ)ひき
神代(かみよ)よりかくなるらし
いにしへも
然(しか)なれこそ
うつせみも
嬬(つま)を争ふらしき
・第三十八代、天智天皇
・万葉集、巻一
香具山(かぐやま=男山)は
畝火山(うねびやま=女山)を
いとおしみ
耳梨山(みみなしやま=男山)と争った
神代(かみよ)からこのように
男は妻を争って
戦うものであったという
古代もそのようであったから
今の世の人も
妻をわがものとしようとして
争うものであるらしい
・はじめ中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と呼ぶ。天智天皇は弟の大海人皇子(おおあまのみこ=後の天武天皇)と額田王(ぬかたのおおきみ)をめぐって争ったことがある。
雄大壮麗(天智天皇/てんじてんのう)
わたつみの
豊旗雲(とよはたぐも)に
入日(いりひ)さし
今夜(こよい)の月夜(つくよ)
まさやかにこそ
・第三十八代、天智天皇
・万葉集、巻一
海上に
おおらかになびいた雲には
夕日が
美しく
美しく
差している
今夜の月も
さやかに照ってほしい
秋山の勝ち(額田王/ぬかたのおおきみ)
冬ごもり
春さり来れば
鳴かざりし鳥も
来鳴きぬ
咲かざりし花も
咲けれど
山を
茂み入りても取らず
草深み
取りても見ず
秋山の
木(こ)の葉を見ては
黄葉(もみ)つば取りてぞしのふ
青きをば
置きてぞ嘆(なげ)く
そこし恨(うら)めし
秋山
われは
・額田王
・万葉集、巻一
春がやって来ると
冬の間鳴かなかった鳥たちも
やって来て鳴く
咲かなかった花々も
咲いている
けれど
木々が茂っているので
山に入って
花を摘むことはしない
草が深く茂っているので
手折って愛(め)でることもしない
秋山の木々の葉を見ると
紅葉(もみじ)したのは
手に取って愛で
青いのはそのままにおいて
嘆(なげ)くしかない
そこが本当に恨(うら)めしい
それでも
やっぱり秋山だなあ
わたしが好きなのは
秋の風(額田王/ぬかたのおおきみ)
君待つと
わが恋ひ居(お)れば
わが屋戸(やど)の
すだれ動かし
秋の風吹く
・額田王
・万葉集、巻四
わが君(天智天皇)の
お出でをお待ちして
ひたすらに
恋い慕(した)っていると
家の戸口のすだれを
ふいに揺(ゆ)らすもの
秋の風が
吹いてくる
困った人ね、あなたったら(額田王/ぬかたのおおきみ)
あかねさす
紫野行き
標野(しめの)行き
野守(のもり)は見ずや
君が袖振る
・額田王
・万葉集、巻一
美しい紫草の
植えてある
この御料地(ごりょうち)を
あなた(大海人皇子)は
巡り歩いては
そんなに袖を振って
私に向かって
合図をなさる
困るではありませんか
野の番人に見られては
・今自分は天智天皇の后(きさき)であり、人目もはばからず求愛の情を示す大海人皇子(おおあまのみこ=天智天皇の弟)に対して、口ではそれをたしなめながらも心では密かに皇子を慕っている複雑な心境が詠われている。
恋せずにはいられないんだもの(大海人皇子/おおあまのみこ) ※返歌
紫の
にほへる妹を
憎くあらば
人妻ゆゑ(え)に
われ恋ひめやも
・大海人皇子:天智天皇の弟で、後の天武天皇
・万葉集、巻一
あでやかで美しいあなたよ
あなたを
いとおしく思えばこそ
人妻であっても
恋せずにはいられない
第二期 作歌群(万葉隆盛期 飛鳥・藤原期 672年~710年)
風薫る(持統天皇/じとうてんのう)
春過ぎて
夏きたるらし
白たへの
衣乾(ほ)したり
天(あめ)の香具山(かぐやま)
・第四十一代、持統天皇
・万葉集、巻一
春は過ぎ
いよいよ夏が
来たらしい
真っ白な衣が
干してあるのが
見えている
ああ
青葉の茂った
あの
天の香具山(かぐやま)のふもとに
・天智天皇の第二皇女。天武天皇の皇后となり、その崩御後、即位した。
春になったよ(志貴皇子/しきのみこ)
石(いわ)ばしる
垂水(たるみ)の上の
さ蕨(わらび)の
萌(も)え出(い)づる春に
なりにけるかも
・志貴皇子
・万葉集、巻八
雪解けのために
かさを増し
激しい勢いで
石の上を流れる水
滝のほとりのわらびが
芽を出した
待ち焦がれて
いよいよ
春になったよ
・天智天皇の第七皇子。
いわゆるグレイトなランドスケープ(柿本人麻呂/かきのもとのひとまろ)
東(ひむがし)の野に
かぎろひの
立つ見えて
かへり見すれば
月傾(かたぶき)ぬ
・柿本人麻呂
・万葉集、巻一
大和(やまと)の
阿騎(あき)の野に宿り
目が覚め
東の空を見やると
すでに
茜色(あかねいろ)の光が差し染めている
さて
西の方を振り返って見ると
今や
野末(のずえ)に残月(ざんげつ)が
没(ぼっ)しようとしているところだった
・三十六歌仙の一人
麻呂はちょっぴりセンチメンタル(柿本人麻呂/かきのもとのひとまろ)
淡海(おうみ)の海
夕浪千鳥
汝(な)が鳴けば
情(こころ)もしのに
古(いにしえ)思ほゆ
・柿本人麻呂
・万葉集、巻八
ほろび果てた
大津の都の跡に立ち
天智天皇の代(よ)を偲(しの)び
悲しみにたえないのに
夕暮れの波に
群がり飛ぶ千鳥よ
お前たちの鳴き騒ぐ声を聞くと
心も打ちしおれて
いっそう古(いにしえ)のことが
偲(しの)ばれてならない
・淡海の海:琵琶湖
追憶の日々(柿本人麻呂/かきのもとのひとまろ)
黄葉(もみぢば)の
散りゆくなべに
玉梓(たまづさ)の
使ひを見れば
逢ひし日思ほゆ
・柿本人麻呂
・万葉集、巻二
黄葉(こうよう)の散る時節
妻の死を知らせる
使いの者がやって来た
わたしの妻だった人よ
しみじみと
切なく
思い出されるのは
あなたに出会った
その日のことです
・死者の魂は、花の咲き乱れる美しい山やもみじの美しい山にひかれ入ってゆく。
戯 れ(天武天皇/てんむてんのう)
わが里に
大雪降れり
大原の
古(ふ)りにし里に
降らまくは後(のち)
・第四十代 天武天皇
・万葉集、巻二
私の里(飛鳥の都)には
どうだ
もう大雪が
降ったぞ
そなたの里
古びた大原に
雪が降るのは
もっと後のことだろう
・大原:飛鳥の都の東南1キロの地
応 酬(藤原夫人/ふじわらのぶにん) ※返歌
わが岡の
おかみに言ひて
降らしめし
雪のくだけし
そこに
散りけむ
・藤原夫人
・万葉集、巻二
わたしの住む
大原の里の
竜神様に
言いつけて
降らせた
雪のくだけたのが
そちらに
降ったのでございましょう
それを得意に
なっておっしゃって
・藤原鎌足の娘で、天武天皇に仕えた女性。
不 穏(大伯皇女/おおくのひめみこ)
わが背子(せこ)を
大和(やまと)へ遣(や)ると
さ夜(よ)ふけて
暁(あかとき)露(つゆ)に
わが立ち濡(ぬ)れし
・大伯皇女
・万葉集、巻二
私の愛する弟(大津皇子)を
都へ帰しやるというので
別れを惜(お)しみ
いつまでも見送っていると
いつしか夜も更(ふ)け
明け方の冷ややかな露に
しっとりと濡(ぬ)れ
私は佇(たたず)んでいました
・天武天皇の皇女。
・弟である大津皇子(おおつのみこ)が、父である天武天皇の崩御後、皇太子である草壁皇子(くさかべのみこ)に謀反(むほん)を企てたとして処刑される直前に、伊勢斎宮であった姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)を訪ね、その別れに際して弟の身を案じて詠んだ歌。
祈 り(大伯皇女/おおくのひめみこ)
ふたり行けど
行き過ぎがたき
秋山を
いかにか
君がひとり
越ゆらむ
・大伯皇女
・万葉集、巻二
二人で行ってさえ
越えがたい
ものさびしい秋の山々を
弟(大津皇子)は
今ごろは
どのようにして一人で
越えているのでしょうか
従 容(大津皇子/おおつのみこ)
百伝(ももづた)ふ
磐余(いわれ)の池に
鳴く鴨(かも)を
今日のみ見てや
雲隠(くもがく)りなむ
・大津皇子
・万葉集、巻三
この磐余(いわれ)の池に
鳴く鴨(かも)を
今日限りに見て
私は
死んでしまうのであろうか
・天武天皇の第三皇子。
・草壁皇子(くさかべのみこ)に対する謀反(むほん)の疑いをかけられ、天武天皇の崩御(ほうぎょ)後二十余日にして処刑された。時に二十四歳。
悲 痛(大伯皇女/おおくのひめみこ)
うつそみの
人にあるわれや
明日(あす)よりは
二上(ふたかみ)山を
いろせと
わが見む
・大伯皇女
・万葉集、巻二
この世に遺(のこ)された
私は
明日からは
弟を葬(ほうむ)った
この二上(ふたかみ)山を
愛する弟と思って
眺(なが)めようか
あなたのために(詠み人知らず) ※柿本人麻呂歌集より
君がため
手力(たぢから)疲れ
織(お)りたる衣(きぬ)ぞ
春さらば
いかなる色に
摺(す)りてば好(よ)けむ
・万葉集、巻七
あなたのために
腕も疲れて織(お)った
着物です
春になったら
どんな色に
染めつけたら
よいでしょうね
姿(詠み人知らず) ※柿本人麻呂歌集より
水門(みなと)の葦(あし)の
末葉(うらば)を誰(たれ)か
手折(たお)りし
わが背子(せこ)が
振る手を見むと
われぞ
手折りし
・万葉集、巻七
水門の
葦(あし)の葉を
誰が
手折(たお)ったの
船出する
愛しいあなたが
振る手を見ようと
私が
手折ったの
・水門は河口・海峡・湾頭などの舟の出入口のこと。
末葉は草木の先端の葉のこと。
鶴鳴き渡る(高市黒人/たけちのくろひと) ※柿本人麻呂歌集より
桜田へ
鶴(たづ)鳴き渡る
年魚市潟(あゆちがた)
潮(しお)干(ひ)にけらし
鶴(たづ)鳴き渡る
・高市黒人
・万葉集、巻三
桜田の方へ
鶴が鳴きながら
群れ飛んで行く
年魚市潟(あゆちがた)の
潮が引いたらしい
鶴が鳴きながら
群れ飛んで行く
・桜田は今の名古屋市南区にある旧地名。
年魚市潟も名古屋市南区のかつて入海となっていた低地帯。
第三期 作歌群(万葉最盛期・奈良時代前期・710年~733年)
濁り酒(大伴旅人/おおとものたびと) ※『酒を讃(ほ)むる歌』より
験(しるし)なき
物を思はずは
一杯(ひとつき)の
濁れる酒を
飲むべくあるらし
・大伴旅人
・万葉集、巻三
妻を失い
悲嘆(ひたん)にくれ
もの思いなどしていても
甲斐(かい)がない
一杯の濁(にご)り酒でも
飲んでいたほうが
よさそうだ
酒壷になりたい(大伴旅人/おおとものたびと) ※『酒を讃(ほ)むる歌』より
なかなかに
人とあらずは
酒壷(さかつぼ)に
なりにてしかも
酒に染みなむ
・大伴旅人
・万葉集、巻三
なまじ
人などでいずに
いっそ
酒壷(さかつぼ)に
なってしまいたい
酒に存分に
浸(ひた)っていられるし
浮世(うきよ)の辛(つら)さだって
絶つこともできる
よっぱらいの一言(大伴旅人/おおとものたびと) ※『酒を讃(ほ)むる歌』より
あな醜(みにく)
賢(さか)しらをすと
酒飲まぬ人を
よく見れば
猿にかも似る
・大伴旅人
・万葉集、巻三
ありゃ
醜(みにく)いものだねぇ
賢人(けんじん)ぶって
酒を飲まない人を
よく見ると
お猿さんに
まあ
よく似ているんだもの
酔 臥(大伴旅人/おおとものたびと)
この世にしく
楽しくあらば
来(こ)む世には
虫に鳥にも
われはなりなむ
・大伴旅人
・万葉集、巻三
この世が
楽しくありさえすれば
来世(らいせ)には
虫にでも
鳥にでも
なってやるさ
楽しくありさえすれば
面 影(大伴旅人/おおとものたびと)
吾(わが)妹子(もこ)が
植ゑ(え)し梅の樹
見るごとに
こころ咽(む)せつつ
涙し流る
・大伴旅人
・万葉集、巻三
今は亡き
妻の植えたこの梅の木は
これを
目にするたびに
お前の面影(おもかげ)が心に浮かぶ
涙が
とめどなく流れ落ちる
酔 眼(大伴旅人/おおとものたびと)
わが園に
梅の花散る
ひさかたの
天(あめ)より雪の
流れ来るかも
・大伴旅人
・万葉集、巻五
我が家の庭園に
梅の花が散っている
いや
あれは
空から流れ落ちる
雪じゃないかしら
唐より愛をこめて(山上憶良/やまのうえのおくらら)
わが園に
梅の花散る
ひさかたの
天(あめ)より雪の
流れ来るかも
・大伴旅人
・万葉集、巻五
我が家の庭園に
梅の花が散っている
いや
あれは
空から流れ落ちる
雪じゃないかしら
わが子よ(山上憶良/やまのうえのおくらら)
瓜(うり)食(は)めば
子ども思ほゆ
栗食めば
まして
偲(しぬ)はゆ
何処(いずく)より
来(きた)りしものぞ
眼交(まながひ)に
もとな懸(かか)りて
安眠(やすい)し
寝(な)さぬ
・山上憶良
・万葉集、巻五
まくわ瓜(うり)を食べていると
わが子が
喜んでこれを食べている姿が
目に浮かぶ
栗を食べていれば
なおいっそうわが子が
いとおしく思われてならない
どのような過去の因縁(いんねん)で
子どもというのは
自分の子として
生まれてきたものなのだろうか
こうして離れていても
子の面影が
目の前にしきりにちらついて
安らかに眠ることができない
嘆 息(山上憶良/やまのうえのおくらら)
富人(とみひと)の
家の児(こ)どもの
着る身無み
腐(くた)し棄(す)つらむ
絹綿(きぬわた)らはも
・山上憶良
・万葉集、巻五
富裕(ふゆう)な家の子どもが
多くの衣服を持ち倦(あぐ)んで
捨ててしまうという
絹や綿といったら
まあ
あきれるばかりだ
そんな衣服であっても
着せて喜ぶ子どもは
世間にどれだけいることだろう
悟 り(山上憶良/やまのうえのおくらら)
世間(よのなか)を
憂(う)しと痩(や)さしと
思へども
飛び立ちかねつ
鳥にし
あらねば
・山上憶良
・万葉集、巻五
世の中を
辛(つら)いと
身も細るような心地(ここち)も
するけれど
それでも
どこかへ飛び去ってしまう
ことなどできはしない
鳥ではないのだから
生まれてきてくれて、ありがとう(山上憶良/やまのうえのおくらら)
銀(しろがね)も
金(くがね)も
玉(たま)も
何せむに
勝(まさ)れる宝
子に及(し)かめやも
・山上憶良
・万葉集、巻五
銀も
金も
宝石も
何になろうか
子どもに勝(まさ)る宝など
ありはしない
薫ふがごとく(小野老/おののおゆ)
あをによし
寧楽(なら)の京師(みやこ)は
咲く花の
薫(にほ)ふがごとく
今
盛りなり
・小野老
・万葉集、巻三
奈良の都
平城京は咲く花が
色美しく
照り映(は)えるように
今や
まことに
繁栄の極(きわ)みである
微 笑(大伴坂上郎女/おおとものさかのうえのいらつめ)
青山を
横切る雲の
いちしろく
われと
咲(え)まして
人に知らゆな
・大伴坂上郎女:大伴安麻呂の娘
・万葉集、巻四
青い山を
横切って流れてゆく
白雲のように
際(きわ)やかな
笑みを私と
お交わしになって
人にそれと
知られなさいますな
そこはかとなく(大伴坂上郎女/おおとものさかのうえのいらつめ)
ぬばたまの
夜霧(よぎり)の立ちて
おほほしく
照れる月夜(つくよ)の
見れば
悲しさ
・大伴坂上郎女
・万葉集、巻六
夜霧が立ちこめ
あわくかすんだ
月の姿
そこはかとなく
悲しく
メッセンジャー(大伴坂上郎女/おおとものさかのうえのいらつめ)
暇(いとま)無み
来(こ)ざりし君に
霍公鳥(ほととぎす)
われかく恋(こ)ふと
行きて告げこそ
・大伴坂上郎女
・万葉集、巻八
暇(ひま)をもてず
たずねてくださることの
なかった
あの方に
ほととぎすよ
恋い慕(した)う
私の
この思いを
飛んで行って
告げてきておくれ
麗 容(山部赤人/やまべのあかひと)
田児(たご)の浦ゆ
うち出(い)でて見れば
真白にぞ
不尽(ふじ)の高嶺(たかね)に
雪は降りける
・山部赤人
・万葉集、巻三
田児(たご)の浦を
海上に
こぎ出して
ふと見上げると
富士の高い峰には
真白に
まあ
見事に
雪が
降り積もっているよ
・三十六歌仙の一人
若の浦よ(山部赤人/やまべのあかひと)
若の浦に
潮(しお)満ち来れば
潟(かた)を無(な)み
葦辺(あしべ)をさして
鶴(たづ)鳴き渡る
・山部赤人
・万葉集、巻六
若の浦に
潮が満ち
干潟(ひがた)が消えて
葦(あし)の生える
岸辺を目指し
鶴(つる)の群れが
鳴きながら飛んで行く
夕 景(山部赤人/やまべのあかひと)
み吉野の
象山(きさやま)の際(ま)の
木末(こぬれ)には
ここだもさわく
鳥の声かも
・山部赤人
・万葉集、巻六
吉野の
象山(きさやま)の
山間(やまあい)の
梢(こずえ)には
これほどまでに
数多く
鳴き騒ぐ
鳥たちの声
静 寂(山部赤人/やまべのあかひと)
ぬばたまの
夜の更けゆけば
久木(ひさき)生(お)ふる
清き川原に
千鳥しば鳴く
・山部赤人
・万葉集、巻六
夜は
更けゆき
久木(ひさき)の生える
清らかな吉野川の
川原のかすかな
せせらぎ
千鳥の
しきりに
鳴く声がする
野辺にて眠る(山部赤人/やまべのあかひと)
春の野に
すみれ採(つ)みにと
来(こ)しわれぞ
野をなつかしみ
一夜(ひとよ)寝にける
・山部赤人
・万葉集、巻八
春の野に
すみれの花を
摘みに来た
野辺を慕い
野辺をなつかしみ
一夜
野に
宿ることにした
春 雪(山部赤人/やまべのあかひと)
明日よりは
春菜(わかな)採(つ)まむと
標(し)めし野に
昨日も今日も
雪は降りつつ
・山部赤人
・万葉集、巻八
明日からは
若菜を摘(つ)もうと
標縄(しめなわ)を
張っておいた
野には
昨日も
今日も
雪が降り
雪が降り
真間の手児奈よ(高橋虫麻呂/たかはしのむしまろ)
鶏(とり)が鳴く吾妻(あずま)の国に
ありける事と今までに
絶えず言ひ来る勝鹿(かづしか)の
真間(まま)の手児奈(てこな)が
麻衣(あさぎぬ)に
青衿(あおくび)着け
直(ひた)さ麻(お)を裳(も)には織り着て
髪だにも掻(か)きは梳(けず)らず
靴(くつ)をだに穿(は)かず行けども
錦綾(にしきあや)の中に
つつめる斎児(いつきご)も
妹(いも)に如(し)かめや
望月(もちづき)の
満(た)れる面輪(おもわ)に
花の如(ごと)笑(え)みて立てれば
夏虫の火に入るが如(ごと)
水門(みなと)入りに
船漕(こ)ぐ如(ごと)く
行きかぐれ人のいふ時
いくばくも生けらじものを
何すとか
身をたな知りて
波の音(と)の騒ぐ
湊(みなと)の奥津城(おくつき)に
妹(いも)が臥(が)せる
遠き世にありける事を
昨日(きのう)しも
見けむが如(ごと)も
思ほゆるかも
高橋虫麻呂
万葉集、巻九
東(あずま)の国
下総(しもふさ)の
真間(まま)の手児奈(てこな)という
古来伝えられる美少女は
青いえりのついた麻の衣を着て
麻糸で織った裳(も)を腰にまとい
髪さえ
櫛(くし)でとかさぬままに
歩くときも
履(は)き物すらはかずにいた
そんな素朴な身なりの
手児奈であっても
その美しさは
錦(にしき)や綾(あや)の衣を
身にまとった
都の豪家(ごうか)の娘でさえ
到底(とうてい)及びはしない
満月のように
美しくふくよかに
清らかに整った
その顔立ちで
花のように微笑みたたずんでいれば
夏虫が
灯(あか)りを慕(した)って
火に飛び込んでゆくように
先を争って
湊(みなと)に舟が漕(こ)ぎ入ってゆくように
恋焦(こ)がれる
多くの男たちに求愛され
どれほどの余生で
あったかも知れないのに
何としたことか
思案に余り
わが身さえなければと
海に身を投げ
波音の騒ぐ湊を
自らの墓としてしまった
はるか遠い
古(いにしえ)の
この出来事は
昨日にでも
目にしたことのように
鮮やかに
目に浮かぶ
・手児奈の霊は、千葉県市川市にある真間の手児奈堂に祭られている。
真間の井(高橋虫麻呂/たかはしのむしまろ)
勝鹿(かづしか)の
真間の井を見れば
立ち平(なら)し
水汲(く)ましけむ
手児奈(てこな)思ほゆ
・高橋虫麻呂
・万葉集、巻九
葛飾(かつしか)の
真間の井を
見ていると
ここを
行き来しては
水を汲(く)んでいたであろう
手児奈(てこな)の姿が
目に浮かぶ
・真間の井は手児奈堂の境内にある。
浦島太郎(高橋虫麻呂/たかはしのむしまろ)
春の日の霞(かす)める時に
墨吉(すみのえ)の岸
に出(い)でゐ(い)て
釣舟(つりふね)のとをらふ見れば
古(いにしえ)の事ぞ
思ほゆる
水江(みずのえ)の浦島の子が
堅魚(かつお)釣り鯛(たい)釣り
七日(なぬか)まで家にも来(こ)ずて
海界(うなさか)を過ぎて
漕(こ)ぎ行くに
海若(わたつみ)の岬の女(おとめ)に
たまさかにい漕(こ)ぎ向(むか)ひ
相(あい)誂(あとら)ひこと成りしかば
かき結び
常世(とこよ)に至り
海若(わたつみ)の神の宮の内の重(え)の
妙(みょう)なる殿(との)に
携(たづさ)はり
二人入り居(い)て
老いてもせず
死にもせずして
永(なが)き世にありけるものを
世の中の愚人(おろかひと)の
吾(わが)妹子(もこ)に
告げて語らく
須叟(しましく)は家に帰りて
父母(ちちはは)に
事も告(かた)らひ
明日(あす)のごとわれは来(き)なむと
言ひければ
妹(いも)がいへらく
常世辺(とこよへ)に
また帰り来て
今のごと逢(あ)はむとならば
この篋(くしげ)開くな
ゆめとそこらくに
堅(かた)めし言(こと)を
墨吉(すみのえ)に還(かえ)り来たりて
家見れど家も見かねて
里見れど里も見かねて
恠(あや)しとそこに思はく
家ゆ出(い)でて
三歳(みとせ)の間(ほど)に
垣(かき)も無く
家滅(う)せめやと
この箱(はこ)を開きて見てば
もとの如(ごと)家はあらむと
玉篋(くしげ)少し開くに
白雲(しらくも)の箱より出(い)でて
常世辺(とこよへ)に
棚引(たなび)きぬれば
立ち走り叫(さけ)び
袖(そで)振(ふ)り
反側(こいまろ)び
足ずりしつつ
たちまちに
情(こころ)消失(けう)せぬ
若かりし膚(はた)も
皺(しわ)みぬ
黒かりし髪(かみ)も
白けぬ
ゆなゆなは
気さへ絶えて後(のち)
つひに命死にける
水江(みづのえ)の
浦島の子が
家地(いえどころ)見ゆ
・高橋虫麻呂
・万葉集、巻九
ある春の
霞(かすみ)のかかった日に
墨吉(すみよし)の岸まで来て
釣り舟が揺れているのを見ると
昔あった出来事が思われる
水江(みずのえ)の浦島の子が
鰹(かつお)を釣り
鯛(たい)を釣っては
得意になって
一週間も家に戻らない
海の果てまで漕(こ)ぎ行くと
海神(かいじん)の姫(ひめ)に出会い
夫婦(めおと)になる
相談がまとまり
堅(かた)く約束し合った
老不死(ふろうふし)の
仙境(せんきょう)の
立派な宮に二人着き
互いに手を取り入って行った
宮の中では
年を取ることなく
死ぬこともなく
長い間暮らしていたというが
世にも愚(おろ)かな
浦島の子が
愛人に告げて言うには
しばしの間家に帰って
父母(ちちはは)に事の次第(しだい)を
物語り
明日にでも宮に戻って来ようと
言ったところ
愛人が言うには
この宮にまた帰り来て
今のように再び二人が会おうと思うなら
この箱を
決して開けてはならぬと
くれぐれも堅(かた)く
禁じたにもかかわらず
墨吉(すみよし)に帰り着けば
自分の家が探しても見つからず
住んでいた里が探しても見つからず
不思議に思い
家を出て三年間に
垣根も家も露と消え去ることが
あるはずないと
あるいは
この箱を開いて見たならば
元のように家は現れるだろうと
美しい箱を
わずかに開けてみたところ
たちまち白雲(しらくも)が箱から出て
仙境(せんきょう)の彼方へとたなびいた
浦島は驚いて
立ち走り
叫んでは袖を振り
ころげ回って
足ずりをしながら
たちまちに気を失ってしまった
若々しかった肌は
たちまちに皺(しわ)が寄り
黒かった髪は白く変わり
後(のち)には息までも絶え
ついには命を
落としてしまったという
浦島の子の家のあったあたりが
見えている
わが子よ(山上憶良/やまのうえのおくらら)
勝鹿(かづしか)の
真間の井を見れば
立ち平(なら)し
水汲(く)ましけむ
手児奈(てこな)思ほゆ
・高橋虫麻呂
・万葉集、巻九
葛飾(かつしか)の
真間の井を
見ていると
ここを
行き来しては
水を汲(く)んでいたであろう
手児奈(てこな)の姿が
目に浮かぶ
・真間の井は手児奈堂の境内にある
夕月夜(湯原王/ゆはらのおおきみ)
夕月夜(ゆふづくよ)
心もしのに
白露(しらつゆ)の
置くこの庭に
蟠蟀(こおろぎ)鳴くも
・湯原王
・万葉集、巻八
夕月の
淡(あわ)い光の下
しっとりと
白露(しらつゆ)のおく
この庭で
しみじみと
心にしみる
秋の虫の声
・天智天皇の孫、志貴皇子の子
第四期 作歌群(万葉衰退期・奈良時代中期・734年~759年)
嘆きの歌元興寺(がんごうじ)の僧(ほうし)
白珠(しらたま)は
人に知らえず
知らえずともよし
知らずとも
われし知られば
知らずともよし
・元興寺の僧
・万葉集、巻六
真珠は
その真価を
人に知られることはない
知られなくてもかまわない
自分の真価は
自分一人が知っていさえすれば
たとえ
世人(よひと)が知らなくても
かまわない
うなぎの人・パートⅠ(大伴家持/おおとものやかもち)
石麻呂(いはまろ)に
われもの申す
夏痩(なつやせ)に
よしといふものぞ
鰻(むなぎ)漁(と)り食(め)せ
・大伴家持
・万葉集、巻十六
ひどく痩(や)せて
うなぎのような
石麻呂(いわまろ)様に
申し上げます
夏痩(なつやせ)に
よく効くということですよ
うなぎを漁(と)って
召し上がりなさいよ
・大伴旅人(おおとものたびと)の長男
うなぎの人・パートⅡ(大伴家持/おおとものやかもち)
痩(や)す痩すも
生けらばあらむを
はたやはた
鰻(むなぎ)を漁(と)ると
河に流るな
・大伴家持
・万葉集、巻十六
石麻呂(いわまろ)さん
痩(や)せていながらも
生きていればそれでよいのに
ひょっとして
あなた
うなぎを漁(と)ろうとして
川に流されなどして
死んでしまってはいけませんよ
紅にほふ(大伴家持/おおとものやかもち)
春の苑(その)
紅(くれない)にほふ
桃の花
下(した)照る道に
出(い)で立つ少女(おとめ)
・大伴家持
・万葉集、巻十九
春の庭園に
紅(くれない) 色に映(は)えて咲く
桃の花よ
花の光
照り輝く
樹下(じゅか)の道に
立つ少女よ
純 白(大伴家持/おおとものやかもち)
わが園(その)の
李(すもも)の花か
庭に落(ふ)る
はだれの
未(いま)だ
残りたるかも
・大伴家持
・万葉集、巻十九
一面に白いのは
私の庭園の
すももの花が
散ったものか
はらはらと
庭に降った
薄雪(うすゆき)が
消え残っているのか
可 憐(大伴家持/おおとものやかもち)
もののふの
八十少女(やそおとめ)らが
汲(く)みまがふ
寺井(てらい)の上の
堅香子(かたかご)の花
・大伴家持
・万葉集、巻十九
おおぜいの
少女たちが
入り乱れて水を汲(く)んでいる
寺の井のほとりに咲く
堅香子(かたかご)の花の
可憐(かれん)さよ
憂 愁(大伴家持/おおとものやかもち)
春の野に
霞(かすみ)たなびき
うら悲し
この夕かげに
うぐひす鳴くも
・大伴家持
・万葉集、巻十九
春の野に
霞(かすみ)がたなびき
もの悲しく
この夕方の
淡(あわ)い日差しの中
うぐいすが
鳴いている
幽 玄(大伴家持/おおとものやかもち)
わが宿の
いささ群竹(むらたけ)
吹く風の
音のかそけき
この夕(ゆうべ)かも
・大伴家持
・万葉集、巻十九
私の家の
少しばかり
群がり生えている
竹の
その茂みに
吹く風の音も
かすかな
この夕暮れ
哀 傷(大伴家持/おおとものやかもち)
うらうらに
照れる春日(はるひ)に
雲雀(ひばり)あがり
情(こころ)悲しも
独(ひと)りし
おもへば
・大伴家持
・万葉集、巻十九
うららかに
照っている
春の日に
雲雀(ひばり)が
舞い上がり
心が痛まれる
独(ひと)りで
もの思いに
沈んでいると
ハッピー・ニュー・イヤー(大伴家持/おおとものやかもち)
新しき
年の始めの
初春(はつはる)の
今日降る雪の
いや重(し)け
吉事(よごと)
・大伴家持
・万葉集、巻二十
新しい
年の初めの
初春(はつはる)の今日
降る雪が
積もるように
いよいよ
積もり重なれよ
めでたいことが
・万葉集二十巻はこの歌で終わっている
片想い・パートⅠ(笠郎女/かさのいらつめ)
君に恋(こ)ひ
甚(いた)も術(すべ)なみ
平山(ならやま)の
小松が下に
立ち嘆(なげ)くかも
・笠郎女
・万葉集、巻四
あなたが
恋い慕(した)われて
まるでどうしようもない
奈良山の小松の下に
立って嘆(なげ)くの
・大伴家持の若い頃の愛人の一人
片想い・パートⅡ(笠郎女/かさのいらつめ)
わが屋戸(やど)の
夕影草(ゆうかげくさ)の
白露(しらつゆ)の
消(け)ぬがに
もとな
思ほゆるかも
・笠郎女
・万葉集、巻四
私の家の
庭の
夕暮れの
薄(うす)明かりの中
草に置く
白露(しらつゆ)が
やがて
消えてしまうように
身も心も
消えてしまいそうに
無性(むしょう)に
あなたのことが
思われます
母の純愛(作者未詳)
旅人の
宿りせむ野に
霜(しも)降(ふ)らば
わが子
羽(は)ぐくめ
天(あめ)の鶴群(たずむら)
・万葉集、巻九
・旅人:遣唐使の一行
旅人が
宿りをする野に
霜(しも)が降りたなら
私の子を
羽で包んでやっておくれ
大空を飛ぶ
鶴(つる)の群れよ
東 歌
旅の宿り
夏麻(なつそ)引く
海上潟(うなかみがた)の
沖(おき)つ渚(す)に
船はとどめむ
さ夜(よ)
更(ふ)けにけり
・万葉集、巻十四
海上潟(うなかみがた)の
沖の州(す)に
今夜は
船を泊(と)めよう
夜はすっかり
更(ふ)けて
しまった
・海上潟は千葉県の市原にあった海上村付近の海
防人歌
出立の朝
防人(さきもり)に
立ちし朝明(あさけ)の
金門出(かなとで)に
手放(たばな)れ惜(お)しみ
泣きし児(こ)らはも
・万葉集、巻十四
防人(さきもり)として
出立(しゅったつ)した
その明け方の
門出(かどで)に
別れを惜(お)しんで
涙した
あの娘(こ)だったよ
思 慕
葦(あし)の葉に
夕霧(ゆうぎり)立ちて
鴨(かも)が音(ね)の
寒き夕(ゆうべ)し
汝(な)をば
偲(しの)はむ
・万葉集、巻十四
葦(あし)の葉に
夕霧(ゆうぎり)が立ち
鴨(かも)の鳴き声が
寒く
身にしみて
聞こえてくる
夕べには
お前のことを
きっと
思い慕(した)うことだろう
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。