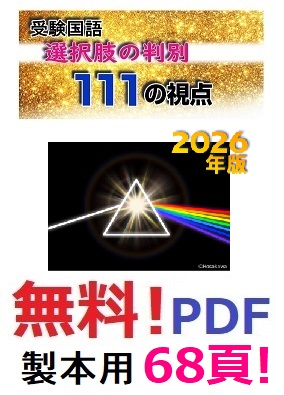中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
■接続語一覧表
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。

■『接続語 一覧表』:PDFのダウンロード(B4・1枚)
論理パズル
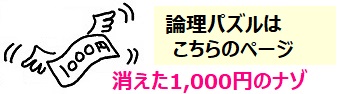
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
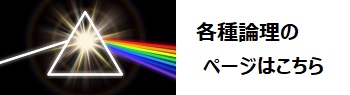
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
・接続語とは、①語と語、②文と文、③段落と段落等をつなぎ、前後がどんな関係であるかを表す言葉です。
・単純に空欄の「直前と直後」だけを読めば解ける問題ばかりではないので、接続語の問題を解くときには、「前後のどの語とどの語とが接続しているのか」、「前後のどの文とどの文とが接続しているのか」、あるいは「前後段落のどの内容とどの内容とが接続しているのか」といった視点をもったうえで、「どのような文脈が成立するか」を考えながら解くようにしよう。
・「段落と段落」との接続関係をとらえる場合、「空欄の前後段落のみ」にとらわれず、「本文全体の構成や展開」も踏まえながら総合的に判断する視点を持つことも重要。一部分にばかりとらわれ、そのために正しく文脈を把握できなくなってしまう恐れもあるので、複眼的視点も備えていこう。
※「説明」の項に含めた「たとえば・言わば・つまり・要するに」は、品詞としては「副詞」である。接続機能をもつ一部の「副詞」は、「接続語」として扱われる。(品詞としての『接続詞』になるわけではない)
※尚、 「接続語」として扱われる語には他に「接続助詞」や「接続機能を持つ連語」などもあるが、小学生には混乱を招く恐れがあるため、本項では主に自立語の接続詞を中心に挙げた。
①順 接
■前の内容が原因・理由となり、後にその順当な結果や結論がくる。
・だから、すると、それで、そこで、したがって、それゆえ、ゆえに、よって
〈例文①〉
・強い風が吹いてきた。
【だから】、
・木々の枝が大きく揺れた。
※例文①の「だから」を同じ順接の接続語である「すると」に置き換えると、「当然の結果」ではなく、逆に「意外な出来事が起こる」文脈となる。次の例文②でも同様に、今度は「だから」に置き換えて文意の違いを確かめてみよう。
〈例文②〉
・玉手箱のふたをそっと開けてみました。
【すると】、
・白い煙がモクモクと出てきました。
②逆接
■前のことがらと対立するようなことがらが後にくる。
・しかし、ところが、でも、けれど、だが、だけれど、だけれども、だけど、けれども、けど、それでも、が、それなのに、しかしながら、ですが、だのに
〈例文〉
・全力で走った。
【しかし】、
・ゴールの手前で転んでしまった。
※前後の内容が対立的となっている。(あるいは、対比的・不調和(不釣り合い)・反対・逆である)
※上の例文で「しかし」以外に「ところが」や「にもかかわらず」に置き換えてみるとわかるとおり、同じ逆接の接続語でも「不釣り合いの度合い」や「主観の度合い」等が異なる。中学入試では小学生の語感を試すような問題も珍しくなく、さらに、記述での表現力向上につなげていくためにも、文脈や場面、状況に応じた言葉の選択、使い分けができるよう、普段から語感を磨き、表現力の訓練にも注力しておきたい。
③並列
■二つ以上のことがらを対等に並べる。「並立」ともいう。
・また、そして、それから、および、ならびに
〈例文〉
・笑っている人もあれば、
【また】、
・考え込む人もある。
※「並列」の場合、「前後の内容が対等な関係」にあるため、以下のように前後を置き換えても元の文の意味が壊れない。ただし、使われ方によっては「並列」と「添加」のどちらかが決定できないことがある。
・考え込む人もあれば、
【また】、
・笑っている人もある。
※小学生には複雑な内容になってしまうが、副詞の「また」との区別も必要。
〈例文〉テストでまたミスをしてしまった。
「再び~する」という意味で動詞にかかっているので、この「また」は副詞である。「副詞」は修飾語として働くが、「接続詞」は修飾語にはならない。
④添加
■前のことがらに新しい事柄や重要な事柄をつけ加える。
・そして、また、それから、そのうえ、それに、しかも、さらに、なお、おまけに、かつ
〈例文〉
・私は七時に起きた。
【そして】、
・顔を洗いに行った。
※「添加」の場合、前後の内容を置き換えると意味的に不自然となる。ただし、使われ方によっては「並列」と「添加」のどちらかが決定できないことがある。③の『並列』の例文と同様に前後の文を置き換えてみると、時系列的に文脈が成立しない。
・顔を洗いに行った。
【そして】、
・私は七時に起きた。
⑤選 択
■前のことがらと後のことがらのどちらかを選ぶ。
・それとも、あるいは、または、もしくは、ないしは
〈例文〉
・コーヒーにしますか。
【それとも】、
・ジュースにしますか。
※上の例では前後の文が対等な関係で並列され、前後を置き換えることもできるが、「どちらかを選択する」という文脈で用いられることから「選択的並列」という捉え方をするとよい。
⑥説明
■理由、換言、例示、補足などを示す。
(1)なぜなら、だって(理由・根拠)
(2)つまり、すなわち、要するに(換言…言いかえること)
(3)たとえば 、言わば(例示・比喩)
(4)ただし、もっとも、なお(補足)
(1)理由・根拠
〈例文〉
・私はA君が嫌いだ。
【なぜなら】、
・彼はいい加減だからだ。
※「順接」の場合と反対に「理由・原因」が後にくる。
(2)換言
〈例文〉
・文法とは、
【つまり】、
・言葉の決まりのことだ。
※「換言」とは、言い換えること。
(3)例示・比喩
〈例文〉
・僕の趣味は読書です。
【たとえば】、
・冒険ものや探偵ものをよく読んでいます。
(4)補足
〈例文〉
・さあ、遊んでおいで。
【ただし】、
・5時になったら帰って来なさい。
※「添加」の接続語は「後に新しい事柄や重要な事柄を付け加える」場合が多いが、「補足」の接続語は「もともと不足している点を後から補う」場合に用いられる。
⑦転換
■話題を変える。(話題転換)
・さて、ところで、では、それでは、そもそも、ときに
〈例文〉
・激しい雨だ。
【さて】、
・明日の試合はどうかな。
※天候の話題から運動会の話題へと転換している。
■注意点
※「そして(添加・並列)」を「だから」と同じ「順接の接続語」と捉え違えている小学生が非常に多い。「そして」には前後の因果関係を積極的に示す働きはない。
例:①私は六時に起きた。だから、顔を洗いに行った。
(前後内容についての因果関係を積極的に示す文脈)
②私は六時に起きた。そして、顔を洗いに行った。
(因果関係ではなく、前の事柄に別の新たな事柄が添加されることを示す文脈)
※「そして」等、添加の接続語の後には「新しい事柄や重要な事柄」を置く場合が多い。空欄補充問題においては、「添加(そして)」と「順接(だから)」のいずれがふさわしいかをその時々の文脈によって判断できるようにしよう。
※接続語の補充問題において、感覚に頼って解答を決めている小学生が非常に多い。
※本文通読中、接続語の分類や働きを理解せぬまま接続語を囲むなど作業のみに注力している小学生が非常に多い。作業自体を主目的とした本末転倒に陥らぬよう、接続語の働きと併せて文脈や展開、構成を捉えるという本来の訓練に注力しよう。
※国語が得意な生徒は接続語の補充問題において判断ミスをほとんどしない。まずは接続語における七種の分類をしっかりと基本として身につけ、前後それぞれの「主語・述語」を押さえて「要約」し、「文脈をたどる」訓練をすると判定の精度が向上する。
※接続語は、日常においては話者や書き手の感情の表出、また、主観性や客観性のニュアンスなど、その時々に応じてさまざまに使い分けられている。中学入試では小学生の語感を試すような問題も珍しくないので、文脈や場面、状況に応じた言葉の選択、使い分けができるよう、普段から語感を磨き、表現力を高める訓練にも注力しておきたい。
※文章を書く際には接続語の後に「読点(、)」を打つことが原則となっている。
■接続語と接続詞の違い
・現在サイトの全面リニュアル作業を行っているため、旧サイト(2024年3月閉鎖)にて掲載していた「『接続語』と『接続詞』の違い」についての記事(約14,000字)は、後日、本項に掲載する予定です。大変ご迷惑をお掛けいたします。
・ただ、ごく簡単に説明すると、『接続語』の中には、品詞としての『接続詞』や『助詞(接続助詞)』が含まれるだけでなく、【つまり】のような『連結機能をもつ一部の副詞』や、【なぜかというと】のような『接続機能をもつ連語』も含まれる。つまり、『接続詞』は『接続語』の中に含まれる一要素であって、厳密には同義ではない。
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。