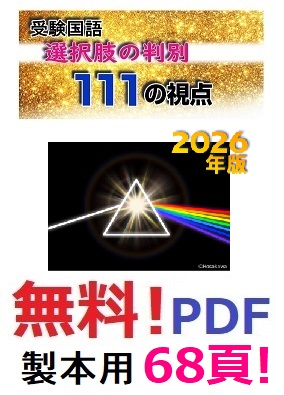中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
■オーラル・リコンストラクション(口頭での再構築的論証訓練)■高速トレース(全脳型分析的高速処理)■フラッシュリーディング(全脳型分析的速読法)■時間短縮訓練
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。
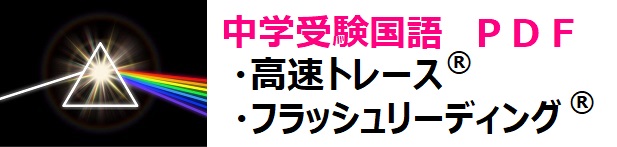
■時間短縮訓練・高速トレース・再現学習・フラッシュリーディング:PDFのダウンロード(B4・3枚)
論理パズル
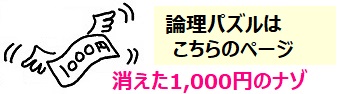
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
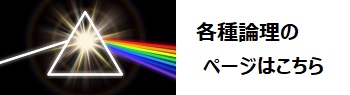
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
■オーラル・リコンストラクション(口頭での再構築的論証訓練)※登録商標
■口頭での再現学習/論理的再構築訓練/説得的論証(Oral Reconstruction Training)
・確実に『トレース』ができたかどうか、学習による理解、獲得(かくとく)が十分であったかどうかは、トレース作業後に、学習内容や解法、記述内容等を子どもに『口頭で再現(アウトプット)』させてみれば確かめることができます。
・『高速トレース』に続き、『再現学習』においては、本文を参照しながら、①「設問の要求に沿(そ)って」、②「トレース作業において確認、獲得された情報を一気に整理、総合し」、③「その内容を言語化によって」、④「論理的に再構築」し、⑤「『伝わりやすさ』を意識しながら」、⑥「的確な表現で」、また、⑦「『自分の言葉』として」、⑧『口述(アウトプット)』します。そして、⑨「その説明は「聞き手がよく理解でき」、また、⑩「話者と聞き手の双方(そうほう)が納得のいくもの」であることが重要な条件です。この時、『高い再現性・再構築性』が認められない場合には子どもの理解度やトレースの質が十分でないと判断できますから、指導者側や保護者側が、子どもの理解度や表現力をより高めるための工夫や取り組みにあらためて注力することができます。
・指導する側は「教えたつもり」になって自己満足に陥(おちい)ることのないよう常に自戒(じかい)しなければなりませんが、子どもにとっては「わかったつもり・学んだつもり」で済(す)ませてしまわぬよう、「本来的な復習」の一環として、ご家庭における『トレース学習』と『口頭での再現学習』の導入をお勧(すす)めします。
※尚(なお)、慣(な)れないうちは手順を変え、口述する内容について整理する時間を事前に与えたうえで、先に『口述(こうじゅつ)による再現学習(アウトプット)』を行い、解法や学習内容等の理解、獲得がしっかりと為(な)されていることを確認し、その後『高速トレース訓練』に入ると効果的です。
■高速トレース(全脳型分析的高速処理)※登録商標
■Flash Trace/High Speed Trace
※「トレース学習」は、個別指導等により、読解内容、設問における要求の把握、解法、記述構成や表現、その他知識事項に至るまで、子どもが当該範囲の学習内容を十分に理解、獲得しえた状況を前提として行います。そのため、子どもが 「なんとなくわかったつもり」の状況だけではそもそも「トレース学習」は成立しませんのでご注意ください。
※また、「対話型」ではなく、講師がまくし立てながら一方的に進めるスタイルの授業を受けている場合には(※当方自身も1987年~92年の間、集団指導において同様のマシンガントークスタイルで授業をしていました)、子どもにはその解説内容が頭に入っていないことが多く、その場合にも『トレース学習』は不可能です。学習内容が本当に理解されているかどうかは、子ども自身に『解説を受けたその内容を口頭で再現』させてみることで確かめることができます。
■左脳は言語や論理、分析、判断等の機能を受け持ち、右脳はイメージや感覚、全体的な情報処理、全体把握等の機能を受け持っています。国語の読解学習(分析的学習)においては、左脳の機能だけで問題を処理できるわけではなく、右脳をも同時に駆動させて問題解決に当たる必要があります。
・読解や解法等の論理的・分析的学習への没入により「頭脳の回転力」が低下する恐れがあるため、当該範囲の学習後に「高速トレース」を行うことで「頭脳の回転力」を回復させ、また、継続的な訓練により「思考の高速化」を図ります。さらに、実戦における脳の機能的シミュレーション(模擬練習)を兼ね、即時の問題解決力の発揮へと繋げていきます。
■「高速トレース」の方法
①高速での追跡確認
・学んだ内容や解法などを高速で確認する。
②時間を計る
・ストップウォッチやタイマー等でトレース時間を計測する。自分をよい意味で心理的に追い込み、普段眠らせている潜在力を発動させる。
③可能な限り高速で、あるいは瞬時に行う
・頭脳の回転力を回復させる。また、思考の高速化訓練、思考の切り替え訓練ともなる。
④声に出さない
・頭の中でだけで思考作業を行う。
⑤言語化は最小限にとどめる
・頭の中でしゃべると(言語化=音声化すると)、実際に声に出して説明するのと同じ時間を要してしまい、思考が高速化されない。
⑥右脳と左脳のいずれをもフルに駆動させる
・逐次に、そして瞬時に、分析的に情報を整理、把握し、判断する。
⑦正確、確実に
・トレース内容の正確性は、口頭での再現時における正確性にそのまま直結する。
⑧「獲得する」意識をもつ
・学んだことを流してしまわず、「自分のもの」にし、「自分の力に変換」する。
⑨「高い再現性・再構築性」
・トレースを終えた後に、各問題の考え方や解法を口頭で確実に説明できること。
⑩聞き手に対し、説得力をもってしっかりと「伝える」
・トレースを終えた後の「口頭での再現学習」において、聞き手に説明内容がしっかりと納得されることを念頭に置く。「伝える力」の訓練の一環でもあり、記述力や表現力にも反映する。
■ある程度訓練を積むと、「文章題1題分を30秒以内にトレースできる」ようになりますから、指導や学習に導入される方はこれを一つの基準としてください。トレース作業の高速化と実質化に慣れると、塾での授業中のほんのちょっとした時間(一問あたり数秒)を使ってトレースを行い、学習内容によっては現場でその都度「復習」、および「獲得作業」を済ませてしまうことも可能です。
■指導する側においても、子どもの口頭での再現状況を確かめることで理解度の確認ができ、適宜補完指導を行うことができます。また、当該箇所における指導の不備を認識できた場合には、指導法を改善・改良してゆくための手がかりともなります。
※「高速トレース(Flash Trace/High Speed Trace)」という名に、「高速での追跡・処理・獲得」といった意味と、「全脳型思考機能の向上と高速化」、「潜在力の発動」、「獲得力・再構築力・再現力・表現力の向上」といった狙いを込めました。尚、「高速トレース」は一つのモデル手法として、適宜工夫を加えてみてください。
■フラッシュリーディング(全脳型分析的速読法)※登録商標
■Flash Reading/Trace Reading
・科学的には、「右脳によって超高速で文章を読む、いわゆる『速読術(速読テクニック)』は『高度な読書力』の向上には繋がらない」という研究結果が既に出されています(キース・レイナー教授/カリフォルニア大学/2016年)。「大意を何となくつかむ練習」にはなりますが、本来的な読書力や文章読解力の向上には何の効果もありません。
・そもそも「本来的な速読力」とは、大量の書物を読破した経験を持つような人が備えた特殊、かつ高度な機能的能力であって、形だけを真似た訓練をいくら積んでも同質の能力を備えることは原理的に不可能なのです。文章の内容を速く正確に理解するには、まずは平常における「適切な速度での通読訓練」と、「右脳と左脳のフル駆動による高度な分析的学習(=読解学習)」の継続が最低要件となります。
・左脳をフルに駆動させる「読解学習=分析的学習」を済ませた後、続けて「高速トレース」と「口頭での再現学習」によって当該教材の内容把握を確実なものとし、そのうえで、学習の最終的な仕上げとしての、また、「より実戦的な速読力のための訓練」としての『フラッシュリーディング(右脳と左脳とを同時に駆動させながら分析的に速読する訓練)』の導入をお勧めします。
・脳内で一字一字を音声化して読む「黙読」をすると「音読」と同じほどの時間を要してしまうため、『フラッシュリーディング』では「視読=脳内で文字を音声化せずに読むこと」を行います。「文における意味上のまとまり(パート)ごとに、写真を撮るようにしてまるごと右脳に投射(文字情報を視覚によって瞬時に脳に取り込むこと)しながら、次々と高速で視点移動をして本文を辿ってゆきます。ただし、それと同時に、左脳をもフルに駆動させ、逐次、および瞬時に内容整理をしながら、『分析的』に本文を読み進めます。文章の内容把握(分析的学習)は事前に済んでいるので、この頭脳作業は『全脳型の分析的速読を主眼とした訓練』となります。
※フラッシュリーディング(Flash Reading):2018年(平成30年)、当方の指導していた、当時インターナショナルスクールに通学していた生徒(小6女子)が名付けてくれました。(旧称は「トレースリーディング」)
【フラッシュリーディングの方法】
①『フラッシュリーディング』においては、「一文字一文字を丁寧(ていねい)に追う読み方」をするのではなく、文章における「一文」を構成する「いくつかの意味内容のまとまり」を意識しながら、そのパート内の数文字分をまるごと『写真を撮るようにして瞬時に脳に投射』しながら、後に続くパートへと順次滑らかに視点移動してゆく読み方をします。
※例えば、本項①の文の場合、「符号を除いた文字数」は約130字、「意味上のまとまり」は10前後です。
②はじめに、これから脳に「投射」する一段落分程度の範囲を、ほんの一瞬(一秒程度)、さっと目に映し取ります。少しでも滑らかに視読できるよう、断片的情報と、およその道筋とを予め脳に無意識的に認知させるだけなので、文を読む必要はありません。(※この手順は状況により省略可)
③続けて、「一文一文の投射」に入ります。「読点(、)と句点(。)の位置」を意識しながら、「文」や「文脈(語や文どうしの論理的なつながり)」に意味的な断絶が起きてしまわぬよう『投射読み(フラッシュリーディング)』を進めていきます。慣れないうちは、一定のリズムをつけて、各パートをゆっくり視点移動させるとよいでしょう。視点移動のしかたやスピードは柔軟に変えて構いません。
④気張って機械的な目の動かし方をするとすぐに目が疲れますから、背筋を張り、気持ちを落ち着け、ある程度文章から目を離して『物理的・認知的視野』を広く保ちながら『投射読み(フラッシュリーディング)』を進めてください。
⑤ストップウォッチやタイマー等で時間を計測してください。同じ文章で「フラッシュリーディング」を数度繰り返すと、その都度投射スピードが高速化されます。慣れるにしたがい、「いくつかのパートを同時に『投射』」したり、「パートにこだわらずに滑らかに視点移動」したり、「一文」や「数行」をまるごと同時に脳に投射」してみましょう。脳の回転力に勢いがついてくると、速く視点移動するほうが却って読みやすくなります。
⑥読解学習で使われた様々な「分析アンテナ」をフルに稼働させ、右脳と左脳を同時に働かせながら、高速、かつ正確に文意、文脈を辿りつつ、逐次、および瞬時に「情報どうしの関連付けや内容整理」を行い、「文章全体の多角的・総合的な把握」を目指します。いわゆる「速読術(速読テクニック)」とは異なる「本来的な速読訓練」を積むと、数行(数文)をまとめて読み進めながら正確に内容把握ができるようになります。 ※ただし、これについては相当な訓練が必要です。
⑦以後も授業等で扱われた教材ごとに同様の訓練を継続することで、全体視野の向上、情報の取り込み方や分析・整理のしかた、処理力や処理スピード等の向上に徐々に反映してゆきます。一本一本の教材を大切に扱い、そして最大限に活用しましょう。
⑧「速読・速解の訓練」、あるいは、「テストや入試本番に向けてのシミュレーション(模擬(もぎ)練習)」として、「速読(フラッシュリーディング)」をしながら、同時に「線引き」や「情報どうしの関連付け」等のチェックをする訓練も導入してみましょう。複眼的・全体的視野で要所を押さえながら読解する訓練となるため、形式的・近視眼的な線引きや見当外れのチェック等の無駄な作業が格段に減り、「読解に有効な本来的な『分析的チェック作業』」が身に付きます。また、「線引きやチェック作業自体が主目的となって本文の内容把握がぞんざいになる本末転倒」に陥ってしまっている受験生にとっても、その改善に有効です。
※尚、「高速トレース」や「口頭での再現学習」、「フラッシュリーディング(速読)」、「分析的チェック作業」の訓練用に、別途何も書き込みされていない状態の当該教材を予めコピーしておくとよいでしょう。
■時間短縮訓練
※「時間短縮訓練」は、個別指導等により平常より「精度重視型」の取り組みが『日々継続的に行われている』ことを前提としています。この取り組みが実現していない状況下では、以下の「時間短縮訓練」は十分な効果を見込めない可能性がありますのでご注意ください。
■「解答スピードだけは速いが、読解や解答の精度が低く、答案全体の仕上がりが雑」という特徴が、上位生を含め、特に国語を得意としない受験生に共通して見受けられます。「スピード」を優先するあまり、「読解と解答の精度」を犠牲にしてきた結果です。「精度より、解答欄を全て埋めきることにこそ重点を置く」というのは、学習全般においても本末転倒です。そればかりか、「本文を通読せずに解けばよい」という非本質的な手法や、普遍性の無い安直な小手先テクニックに幻想を抱き、それを「よすが」として、ますますこの「底なしの悪循環」から逃れられなくなっていきます。
・「精度を犠牲にせず制限時間内に全問解決する」には、学習におけるそれまでの取り組み方を「精度重視型」に完全転換し、併せて「時間短縮訓練」を導入し、日々着実に継続する必要があります。平常における訓練の継続無しに、テストや入試本番の時だけ時間短縮を実現することなど不可能です。
【自宅での演習時における時間短縮訓練】
①時間配分を行う。
②ストップウォッチやタイマー等で時間を計測する。
③本文を通読する。
④読解と解答の精度を上げることに重点を置く。
⑤入試本番を意識し、良い意味で自分を心理的に追い込み、全力で問題解決に当たる。
⑥問題処理中は常に時間を意識しつつ、頭脳の回転力を高速で維持する。
⑦頭脳の回転力をさらに高めるため、解ける問題の処理をどんどん進める。
⑧訓練開始当初、時間内に解き切れない場合は延長時間をとり、自分の頭を使って最後まで徹底的に考え抜く。
⑨得点は精度の結果なので当初は気にしすぎず、1か月後、2か月後……の自身の進歩・向上を明確に見据(す)えて、それを当面の目標とする。
⑩訓練を重ねるごとに、『今回は延長しても何分以内で』というように、徐々に延長時間を「短く設定」してゆく。
・「精度重視型」の取り組みに転換した当初、個々の状況によっては、暫くの期間、目標の時間内に全ての問題処理が終わり切らないことがあります。その場合においても、躊躇せずに延長時間を設けてください。大人の力を借りる前に、「まずは限界に挑む気持ちで、自分の頭を使って最後まで徹底的に『考え抜く力』の育成」を最優先してください。
・そして、時間短縮のための訓練を重ねるごとに、延長する時間を毎度徐々に短く設定します。元来人間には、訓練によってその能力や技術を確実に向上させる力が備わっています。また、一定期間内での訓練機会を多く設けるほど、時間短縮の能力向上が確実に早まります(指導経験上、断言します)。訓練を開始する時期や受験生個々の状況により違いはありますが、一つの目安として、通常三か月ほどで、精度を上げつつ時間内に解答欄全てを埋め切ることができるようになります。
・尚、国語の偏差値が50前後以下の受験生の場合、学習の取り組み方をそれまでの「スピード優先・精度犠牲型」から「精度重視型」へと完全転換して1か月ほどの間、テスト本番で制限時間内に「文章題二題のうち一題がまるごと解答できない」といった現象が見られる場合があります。しかし、それを恐れて再び「スピード優先・精度犠牲型」の取り組み方に戻してしまうと、「底なしの悪循環」に舞い戻り、そのままそこから脱することなく入試本番を迎えることになるでしょう。
■当方自身の経験として、集団指導時代(~2002年)には、「自宅での演習においても常にテスト形式で臨み、制限時間が来たら、解けていても、解けていなくても、そこで一切手をつけてはならない」といった方法で生徒たちの解答スピードの向上を図っていました。しかし、この方法だと、大方の子どもたちにとっては、いつまで経っても精度向上が望めないばかりか、自分が処理できなかった問題について「自分の頭を使って最後まで徹底的に考え抜く」習慣がつかず、しかも、「問題の解決を大人に丸投げ」したり、解説を聞いたり読んだりして、それで全て分かったつもりになって事を済ませてしまう、といった弊害を感じるようになったという経緯があります。
■読書・音読・読み聞かせ・線引き・根拠記述ノートについて
【読書について】
■左脳は言語や論理、分析、判断等の機能を受け持ち、右脳はイメージや感覚、
全体的な情報処理、全体把握等の機能を受け持っています。
・「うちの子は読書が好きで、一冊の本を20分ほどで読んでしまうのに、国語が全然できない」といったご相談をよく受けます。物語や小説などを「右脳によって作品を楽しんで読む」ことそれ自体は感性や情緒、想像力等を育むうえでの効果も高く、大いに推奨されるのですが、思考力や分析力、論理性や客観性が要求される国語の読解問題に専ら右脳によってセンス的に対処するのにはどうしても限界があります。「左脳をよく働かせ、主体的に自分の頭を使って考えながら読み、解き、書き、獲得(かくとく)し、また、口述によって論理的に説明する」取り組みにも注力しましょう。また、一編の文章題を徹底的に読解、分析する取り組みは、不十分な理解のままに何冊も本を読むより、読解力の向上においてはよほど効果的であると言えます。
【音読について】
・「『音読が効果的だ』と聞いてずっと続けてきたのに、うちの子は国語が全然できない」といったご相談をよく受けます。文章の内容把握が十分に為されていない状況でいくら音読に時間を割いても、「滑らかに字面を追いながら発声する練習」にはなっても、それが読解力の向上に直結しているとは限りません。文章の内容把握には心理や主張の理解、文脈や展開の把握など、多角的視点や分析力、論理的思考力等による総合的な読解力が求められ、相当な集中力や根気も必要です。もし国語学習に音読を導入される場合には、右脳と左脳をフルに駆動させた『読解学習=分析的学習』を十分に済ませた後に行うほうが、獲得したことを昇華させ、「自分の力」へと変換させるうえでの効果が高く、合理的です。
※昇華:物事が、ある状態からさらに高度な状態へと飛躍(ひやく)すること。
【読み聞かせについて】
・「子どもが幼い頃には『読み聞かせ』もしたし、音読もさんざんさせてきたのに、うちの子は国語が全然できない」といったご相談をよく受けます。子どもが「自らの頭をよく使いながら主体的に人の話を聞く姿勢を育てる」視点が無いままに一生懸命読み聞かせを続けていても、逆に子どもに「人の話を受け身の姿勢で聞き、ものごとを受け流す習慣が身に付いてしまう」といった弊害も一つの側面として考えられます。子どもが他者の話を主体的に聞き、受け止め、考え、獲得する姿勢が育つよう、もっと左脳を働かせる工夫をしながら読み聞かせをしてあげてください。
【文章への線引きについて】
・言うまでもなく、『文章への線引きやチェック作業』そのものが主目的となって却って読解が疎かになるようでは本末転倒です。本来こうした作業は、読解力や分析力が備わることで自然に、あるいは必然的に備わる技術、あるいはツールの一つだったはずです。『視野を常に広く保ち』、『思考力と感性を最大限に働かせ』、『細部や文脈』、『要点』、『折々の感情や状況』、『変化や展開・構成』、『主題や要旨』等の種々の情報を的確に、かつ、総合的に捉える訓練の継続と蓄積によってこそ、チェック作業は本来の『分析的ツール』として機能するものです。『線引きテクニック』としてただ機械的に作業をするのではなく、まずは『文章の内容を正確に、かつ総合的に把握する』という本義を根底に据え、これと並行して右脳と左脳をフルに駆動させる『本来的な分析的チェック作業』ができるよう訓練を重ねてゆく必要があります。
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。