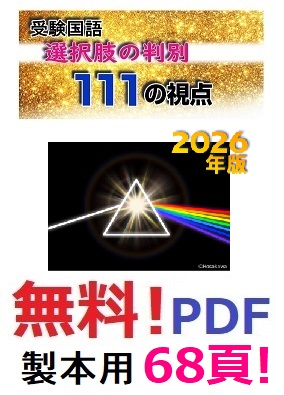中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
■記述力の練成技術
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。
論理パズル
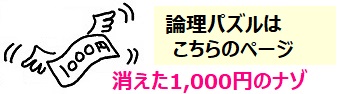
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
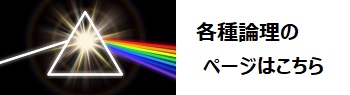
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
■表現の本質
・開成中学で開示された模範(もはん)解答に、記述答案の採点基準として、かつて次のように記(しる)されていたことがありました。
・「言葉の係り受けが正確であること、文章のつながりが適切であること、読みやすく誤字のない表記であることなども、重要な要素です(平成14年度/2002年度入試)」
・「本文中の言葉や自分なりの言葉を使って、説得力のある文章を作りあげる力が大切です(平成15年度/2003年度入試)」
・「解答にあたって求められているのは、…(中略)…正確な、伝わりやすい表現が工夫されていることです(平成16年度/2004年度入試)」
・これを読んでわかることは、表面的には「単に機械的に切り貼(は)りをしただけのような記述答案や、趣意(しゅい)のはっきりしない記述答案には十分な評価を与えられない」といった技術的な側面での評価基準です。しかし、一歩踏(ふ)み込んでみると、そこにあるのは、「自分の考えをしっかりと持ち、それを論理的、かつ正確に、他者に対してしっかりと伝える力」を素養として備えた者に入学してきてもらいたいという、人間同士の生身(なまみ)のコミュニケーションを前提とした、開成中学の発するメッセージの深遠な本質です。
・普段、机に向かうばかりが勉強ではありません。時に外界に目を広げ、五感を働かせながら、一つひとつの事象や問題について、触れ、感じ、考えてみる。一つひとつの問題について、それを「自分の中でしっかりと受け止める」こと。そして、「自分が考えたことや感じたこと」を「他者に対し本気で伝えたいと欲(ほっ)する」こと。さらに、それを「工夫しながら表現し、正確に伝えんとする」こと。
・開成中学は、受験生に対して、実は何も特別高度なことを要求しているわけではありません。書くうえでも、話すうえでも、「伝えることは表現の本質」であり、社会を生きてゆく中で、人と人との関わりやコミュニケーションを根本に据(す)えて、「伝える力の大切さ」や、「自分の言葉を持つことの大切さ」、「言葉の力への信頼」といった、ごく基本的で当たり前のことを認識し、そのうえで、将来をきちんと見据(す)え、着実な歩みとともにしっかりと学業に取り組んでもらいたいという、そんな意味のこめられたメッセージと受け取ることができます。
・「伝え合うこと」の意味をよく考え、それを自ら深く受け止め、言葉に関わる姿勢や取り組みを今一度見直し、普段の言語生活をより豊かに変えてゆくこと、自分自身を磨(みが)き、自分自身の生き方を見定めながら、未来に向けて意志的に歩みを進めてゆく、そんな自分自身に育ててゆくことが、学ぶ者の姿勢としてとても大切です。
■《開成基準》で記述訓練に取り組む
・「正確な、伝わりやすい表現を工夫する」、「説得力のある文章を作りあげる力」。開成中学は特別に高度な記述力を要求しているわけではありません。求められているのは、「自分の考えをまずしっかりと持ちなさい」、「それを他者に対して正しく、確かに伝えられる自分でありなさい」、「基本を疎(おろそ)かにしてはいけない」、というだけの至極(しごく)当たり前のことに過ぎません。難関校に限らず、いずれの中学校を受験するにしても、これを《開成基準》としてよく心に刻(きざ)み、常に念頭に置いて記述学習に取り組むことで、君の記述答案の水準は今後、劇的に変化してゆくことでしょう。
・ちなみに開成中学では、「漢字の書き取り」については、「解答にあたって求められているのは、正確に書かれた読みやすい漢字であることです(平成16年度/2004年度入試)」としています。自分が書く文字についても、「伝える手段」の一つとしてあらためて捉(とら)え直し、いずれの中学校を受験するにしても、また、普段の生活においても、読み手のことを念頭に置いてきちんと書いて伝えられるようにしましょう。
・尚(なお)、現在、配点上、もしくは内容面を評価する都合、入試において「漢字の書き取り問題ではトメ・ハネ・ハライは見ない」、「記述答案での『ら抜き言葉』や『違(ちが)くて』、『今いち』等の『俗語(ぞくご)』の使用は問わない」、「句読点についても見ない」と公言する中学校が増えていますが、君たち受験生は、学ぶ者の姿勢として、あくまで自分に厳(きび)しく、基本を疎かにしない《開成基準》を常からよく守り、学び、取り組んでゆくようにしましょう。
※ら抜き言葉:見れる、着れる、出れる、来れる、起きれる、食べれる、考えれる、決めれる等の俗語。
■記述指導
・集団指導や個別指導でいくら「詳細(しようさい)な解説」を受けたとしても、あるいは、先生から答案に「丁寧(ていねい)な添削(てんさく)」を受け、コメントを細々(こまごま)と熱心に書き込んでもらっても、その後の「仕上げ作業」が伴(ともな)っていないのであれば、いつまで経っても精度の高い記述答案を書き上げられるようにはなりません。返却された添削答案をさらりと眺(なが)めて、「ふうん……」で済ませてしまってはいませんか。
・塾の先生に、質問という形で、少しであっても時間を割(さ)いてもらい、大人の視点による指摘(してき)を受けながら、先生と生徒との生きた言葉での直接のやりとりを通して、両者が納得のいく水準、精度にまで記述答案を練(ね)り上げていくような取り組みを継続しないと、結局は「添削答案を眺(なが)めただけ」の「書きっぱなし、やりっぱなし」に終始し、本来的な記述力の向上を図ることは不可能です。継続的な訓練により、子どもたちの記述力、表現力がその最高水準に達するのは、まさに受験直前期の1月(あるいは、入試本番)です。塾の先生は、自分の担当する生徒たちが質問に来てくれるのを待ってくれています。遠慮(えんりょ)をしてはいけません。自身の記述力を磨(みが)き、最高水準にまで高めるために、受験直前に至るまで、塾の先生の指導を徹底的に活用させてもらいましょう。
・ただし、突然の訪問は避(さ)け、先生の都合に配慮(はいりょ)し、依頼(いらい)の気持ちを自分の言葉で誠実に伝えてください。そして、先生に解決を丸投げするのではなく、疑問について「何をどう改めるべきか」を自ら熟考(じゅっこう)し、「自分なりの準備」を十分に済ませたうえで質問に向かってください。そのうえで、「自分の考え」を、自信を持って先生にぶつけてみてください。
大原則
■大原則
①設問の要求を正確に把握する
・設問がまず「何を要求しているのか」を正確に捉(とら)え、正しい方向に沿(そ)って思考すること。また、「その要求を、自分に与えられた解決すべき問題としてしっかりと受け止める」ことで、見当違いの思考やミスが必然的に無くなっていく。
②趣旨(しゅし)を固定する
・「自分が伝えたい内容を明確に固定する」。正確な読解に基づき、伝えんとする趣旨(しゆし)を明確に固定すれば、解答要素は自動的に集まってきてくれる。ただし、「あらすじを書いただけ(あらすじ解答)」、「機械的に切り貼(は)りをしただけ、本文の内容を書き写しただけ(コピペ答案)」とならぬよう、趣意に沿って、正確に文脈構成しよう。
③正確で、伝わりやすい表現を工夫する
・「正確で、伝わりやすい表現を工夫すること」は、「表現の本質」だと言える。最難関校を目指しながら、単に「切り貼り」をしただけのような、機械的で稚拙(ちせつ)な、読み手に「うまく伝わってこない」記述答案しか書けない受験生が驚くほど多い。入試答案を採点する先生のうんざりした表情が目に浮かぶようだ。自分の将来のためにも、「自分の考えが読み手や聞き手によく理解されるような表現力や説明力、説得力」を磨(みが)いておこう。
※「中学受験は算数さえ強化すれば何とかなる」といった昔ながらの観点で、「極端に算数に偏重(へんちょう)した指導」に徹(てっ)する受験指導者がまだまだ多く見受けられるが、現在は「国語はできて当たり前」にしておかなければならないだけでなく、「四教科や分野間の学習バランスや実力バランス」、また、「総合的学力」をも勘案(かんあん)し、適宜(てきぎ)学習時間や学習メニューを「調整」しながら強化、補完等を図ってゆく必要がある。
■基本
①主語・述語
・一文一文、文意が正しく伝わるよう、主語・述語の整った文章を心掛けよう。
②係り受け
・趣旨や文脈が乱れないよう、係り受けを意識して正しく表現する。
③誤字・脱字
・誤字・脱字の無いよう、「書きながら確認」する注意力が必要。
④句読点・符号は一字扱い
・一般に「句読点、符号等は一字扱い」が原則となっている。原稿用紙の書き方の決まりと、模試や入試での書き方の決まりとは異なるため、句点や読点を次行の冒頭に打たねばならない場合がある。
⑤口語体(会話表現)や俗語を使用しない
・「~けど」、「~じゃなく」、「あったかい」、「おんなじ」等の口語体は使用しない。また、「違(ちが)くて」、「ばれる」等の俗語(ぞくご)も使用せず、「違い」、「知られる・知れる・露見する」などと言い換える。「むかつく」は俗語ではないが粗暴な印象を与えるので「腹が立つ」、「腹を立てる」などと言い換える。
※ばれる:2025年現在、岩波、旺文社、学研、角川、三省堂、集英社、小学館等の国語辞典では「俗(ぞく)語」と明記。
⑥文体統一
・文体は常体(「~だ、~である言葉」)で統一する。
※「です・ます言葉」は「敬体」という。
⑦文中語句・自分の言葉
・「本文中の語句を使用して」とある場合には、本文中で使用されている語句をなるべく多く使用する。
・「自分の言葉で」とある場合には、説明に必要な語句を除き、本文中の語句はなるべく使用せず、自分の語彙(ごい)力を駆使(くし)して説明する。
⑧不明確な比喩(ひゆ)表現の使用は避(さ)ける
・例えば、「海のような心の持ち主」という表現は、たとえている内容が「広い、大きい、静かだ、穏(おだ)やかだ、包(つつ)み込むような深さ、荒々しい……」というように受け取り方がさまざまに異なり、客観的な説明が成立しない。
⑨自分の使える漢字は使う
・普段の言語生活がそのまま一枚の答案に反映する。言葉に関わる姿勢を保って学習をしよう。
⑩無駄なく、正確な内容で表現する
・一文50~60字で無駄なく正確な内容と文脈で表現する力を身に付ければ、あとは「趣旨に沿(そ)った文どうしのふさわしい連結」によって、「一文100字」であっても流れのよい趣意の正確な叙述(じょじゅつ)ができるようになる。「連結」の際に、「~で」、「~して」、「~ので」、「~が」を多用しないよう意識しよう。
■暗黙(あんもく)の前提(ぜんてい)(暗黙の了解(りょうかい))
・「わざわざ言明せずともわかりきった前提」を「暗黙の前提」という。記述上の高度な技術の一つとして、「暗黙の前提」の利用がある。簡単な例では、「建物の中から外へ飛び出す(12字)」という表現の場合、「建物の中から飛び出す(10字)」、あるいは、「建物から外へ飛び出す(10字)」、「建物から飛び出す(8字)」としても、意味的にほとんど違いは無い。文脈上、「飛び出す」行為に「中から外へ」の意味が暗黙のうえに了解されるためだ。「暗黙の前提」を記述説明に利用する場合には、文章全体の流れや、文意、文脈を踏(ふ)まえ、文字数も勘案(かんあん)しながら適宜(てきぎ)表現の調整を行うとよい。
技術的基本①
①文末処理
・設問の要求に沿って、文末を正確に対応させる。
・なぜ? どうして? 理由は? ・・・・・・ ~から。~ため。(~ので。)
・何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~こと。~体言。(~もの。)
・どういうこと? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)こと。
・どのようなもの? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)もの。(~体言。)
・どのような意味? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)こと。
・どのような内容? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)こと。
・どのような気持ち? ・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)気持ち。
・どのような様子? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)様子。
・どのような点? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~(という)点。
・どうしていますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・ ~している。
・どうしましたか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~した。
・どうしていましたか? ・・・・・・・・・・・・・・ ~していた。
※文末を「~ので。」と結ぶのは文法的にも解法的にも誤りではないが、模範解答等ではごく稀(まれ)に 見かける程度である。
例:声の教育社版、『麻布中学(平成3年度・昭和63年度)』、『桜蔭中学 (平成12年度・8年度)』、『雙葉中学(平成20年度・15年度・10年度)』等。
②前提(ぜんてい)事項(じこう)の重複(ちょうふく)記入に注意
・「設問文中の前提事項」を重複記入しない。
※例えば、設問で「太郎の気持ちを説明せよ」と求められているのなら、太郎を「暗黙(あんもく)の前提」として説明すればよいのだから、文脈上必要な場合を除き、「太郎は…、太郎は…」のように何度も書き重ねる必要はない。
※「前提事項の重複記入」に意識が向かず、制限字数を圧迫(あっぱく)して解答要素をはじき出してしまっている受験生が、上位生を含めて非常に多く見受けられる。
※「抜き出し問題」においてもまた、設問の条件における「前提事項」に注意が向かないと、『ここから、ここまで』という、要求に対応した正確な範囲(はんい)特定を誤(あやま)る恐れがある。
③長い主語の構成
・短い主語での書き出しは、「~で、~で、だらだら」と稚拙(ちせつ)で冗長(じょうちょう)な文章になりがち。
※例えば、「 花が →庭に美しく咲いており、……」を「庭に美しく咲いている 花が 、~」のように、関連語句をまとめて「中心主語」の上に載(の)せ、「長い主語」を構成して書き出すことで、それに続く文脈もすっきりとし、わかりやすくなる。
※「主語」以外についても意味的にまとめる工夫をしてみよう。
④表現の重複を避(さ)ける
・文脈上必要な場合を除き、記述説明に「同語・同義語」を重複使用しない。制限字数を圧迫(あっぱく)する原因となるだけでなく、解答要素をはじき出してしまう原因ともなる。
⑤「が」と「は」の使い分け
・「太郎が」と「太郎は」とでは意味、用法が異なる。文意、文脈に沿(そ)ったふさわしい表現を選択する。
⑥語句の短縮
・動詞や語句を適宜短縮する。(例:食物にふくまれている脂肪(しぼう)=食物にふくまれる/ふくまれた脂肪)
⑦倒置・再構成
・「語句の倒置」や「パーツ全体の再構成」を適宜(てきぎ)行い、無駄(むだ)の無い、内容の整理されたわかりやすい文脈を構成する。
《例》
・『牛乳にはわずかな塩分がふくまれているが、海水に比べるとその濃度(のうど)ははるかに低い。(39字)』を再構成すると、『牛乳にふくまれる塩分の濃度は、海水に比べてはるかに低い。(28字)』となる。
⑧具体性を高める
・言葉を整理して、具体的でわかりやすい文章を心掛けよう。
⑨趣旨(しゅし)を文、または文章の後尾に固定する
・「仲直りして、握手(あくしゅ)した(事柄(ことがら)の前後関係を示す)」と、「握手して、仲直りした(並行(へいこう)的状況を示す)」とでは文意が異(こと)なる。趣旨(伝えたい内容の中心)は文章全体を支配する。「解答の核(かく)」となる趣旨を文(文章)後尾に固定したうえで文脈を構成しよう。たとえ解答要素が揃(そろ)っていても、趣旨が異なることで文章全体を殺(ころ)してしまう危険もある。問題の水準にもよるが、作問者はそこまで予見して作問をしている。
⑩句読点
・一文において、読み誤(あやま)りや読みにくさを避(さ)けるため、「意味の流れが途切(とぎ)れる所」や必要な場所を適宜判断し、「読点(、)」を打つ。「一つ言いたいことを述べたらテン(読点)を打つ」ことを意識し、各要素どうしを適切に連結していくとよい。そして、叙述(じょじゅつ)が完結したら、文末に「句点(。)」を打つ。
技術的基本②
①適切な動詞の選択:「ある・いる・やる・する」で済まさず、その都度(つど)適切な動詞を探(さが)して用いる。
②本文表現の尊重:筆者や作者の意図(いと)により選択された表現を尊重する。
③文末の心情表現:「安心する気持ち。(体言処理)」、「安心している。(動詞処理)」のいずれも可。
④意志・推量表現:助動詞の「う・よう・まい」を適宜(てきぎ)使用し、正確な表現とニュアンスを工夫する。(例:去ろうとした。逃げようとした。嘘(うそ)はつくまい。)
⑤希望表現:助動詞の「たい・たがる」を適宜使用し、正確な表現を工夫する。(例:帰りたがった)
⑥「~ている・~てある」は「~た」に置き換えが可能。(例:『壁(かべ)に掛(か)かっている時計=壁に掛かった時計』・『紙に書いてある文字=紙に書いた文字』)
⑦ニュアンスの調整:自分の語彙(ごい)力を駆使(くし)し、「説明にふさわしいニュアンス」で表現する。
⑧語句の補完:説明に必要な語句を判断し、適宜自分の「言葉の引き出し」から取り出して補(おぎな)う。
⑨自由スペースでの字数の推定:「自由スペース:マス目の無い解答欄(らん)」では、抜き出し問題等のマス目のある解答欄等を利用し、要求されている字数を推定する。
※一般に「縦一行25字」が平均であるが、模試や各学校の解答スペースに合わせて適宜推定する。
⑩指定字数の順守:「~字以内」とある場合は八割以上書き、「~字程度」とある時は、極力その指定字数に近づける。
⑪文脈構成:主語と述語の「ねじれ」や「係(かか)り受け」に注意し、正確でわかりやすい文脈を構成する。
⑫指示語:指示語を使用する際には、文脈上正しい用い方をすること。ただし、指示語を使うと無駄(むだ)に字数を消費する場合が多いので、なるべく指示語を使わない文脈構成を訓練しておくとよい。
技術的基本③
①強調表現:文章に説得力を与えたり、ニュアンスを与えたりするための工夫の一つ。
②説得力を与える:読み手を説得する内容や表現の工夫をし、また、文章に「流れ」を作る。
③抽象表現化:説明に必要な語句を適宜(てきぎ)抽象化し、無駄(むだ)の無い、要を得た文章を作る。「抽象化」が過度だと『まとめすぎ』となって「具体性」が低下し、逆に「具体的すぎる」と「解答要素をはじき出す」恐れがあるため、制限字数に応じて抽象度と具体性を適宜調整する訓練が必要。平常より「記述や口頭でのアウトプット」を通して、説明の具体化や、概念語などの抽象表現に変換する訓練を積んでおこう。
※概念語(がいねんご):物事の本質や性質について、その内容を抽象化して表す語。友情・信頼・疑問・対立・理解・喜び・不安・文化・社会・自然・価値・情報・合理的・因果関係、などの語。
④文章構成・展開:文章全体の構成や展開を工夫し、無駄(むだ)のない、まとまりのある文章を心掛(こころが)けよう。
⑤書き出しの変更:当初の書き出し方で文脈構成に行き詰(づ)まったら、即座に「別の語による書き出し」に切り替える。普段から「文の書き出しを瞬時に切り替えて文脈構成する」訓練を積んでおこう。
⑥要約・凝縮(ぎょうしゅく):各部を適宜凝縮する。無駄のない表現で的確に内容を伝える工夫をする。
⑦表現の変換:状況に応じ、適切な表現に言い換える。
⑧反照代名詞の利用
・「自分」という語を適宜利用し、誰(だれ)の視点からの説明かを明確にする。「彼は自分の思いを伝えた」
⑨「~など(等)」は安易に用いず、必要な場合に適切な用法を考えて使用する。
⑩「の」の連続使用:「私の本の表紙の絵の色の~」のような、『の』の不適切な連続使用を避(さ)ける。
⑪「Aしたり、Bしたり」:「飛んだり、跳(は)ねたり」、「降ったり、やんだり」のような「動作や作用の並列」においては、並列した回数分の「たり」を使用する。
⑫連結表現の工夫:文中における「連結部の表現」を工夫する。「~ので/~から(理由・原因)」、 「~のに/~が(逆接)」、「~で/~して/~し(並列・添加)」等を多用すると、「~で、~で、だらだら」型の稚拙
(ちせつ)で冗長(じょうちょう)な文章となりがちなので注意。(※下表参照)
■連結表現
・~について(論点/関連) ・~ために(目的/原因・理由) ・~ことで/によって/に基(もと)づく/をもとに(土台) ・~に対し/ことに/への(対象)
・~せずに/ことなく(否定) ・~において/における(時間/場所/状況) ・~だけでなく/とともに/うえに/のみならず/に加え/ばかりか/ばかりでなく(添加・並列)
・約束したにもかかわらず/自由でありながら(も)/信じたものの/疑いつつも(逆接)
・達成するうえで/協力のもと(条件・前提) ・許すとしても/難しいにせよ(にしろ)/友人であれば/認めるなら(ば)(仮定条件)
・社会人として(の)(資格) ・姉である花子(同格) ・増えるにつれて/発展にともない(変化)
・早いのに対し(て)/意に反し(て)/強い反面/増えた一方で(対比) ・咲くと同時に/日没とともに(同時)
■連用中止法
・「よく学び、よく遊べ」、「頼もしく、快活な人物」、「静かに、ゆっくりと歩く」などのように、動詞や形容詞、形容動詞などの語を連用形で一旦(いったん)中止して、その後に文を続ける方法。直後に読点を打つ。
読点の打ち方
・読点が多いと文章が緩慢になりがちなので、記述答案を作成する訓練において、無駄に解答スペースを消費してしまわないよう、普段から読点が本当に必要な位置をしっかりと意識しながら取り組むようにしよう。
①主語のあと
(1)「叙述の主題となる主語」のあとに打つ。
・ゾウは、鼻が長い。
(2)助詞が省略された主語のあと
・ぼく、もう宿題は済んだよ。
※「ぼくは」の「は」が省略されている。
②並列関係にある語句の間
(1)重文(主語・述語を備えた文の対等な連結)
・おじいさんは山へシバ刈りに、おばあさんは川へせんたくに行きました。
(2)述語が二つ以上あるとき
・犬が立ち上がり、ほえだした。
(3)語句が二つ以上並ぶとき
・静かな、明るい朝のひとときです。
(4)同格(イコール関係)の語の間
・それは1945年、昭和20年のことであった。
③条件や限定などを表す文のあと
(1)条件や限定を表す文のあと
・犬が追いかけてきたので、走って逃げた。
(2)時・場合などを表す語句のあと
・その時、戸があいた。
(3)接続語のあと
・しかし、誰一人彼を理解しようとはしなかった。
(4)文頭に用いる副詞のあと
・もしも、雨がふったら…。
(5)感動詞のあと
・「おお、寒い。」(感動)
・「おはよう、花子さん。」(あいさつ)
・「もしもし、 山田さんのお宅ですか。」(呼びかけ)
・「はい、そのとおりです。」(応 答)
・「さあ、始めよう。」(かけ声)等
※感動詞:感動、あいさつ、呼びかけ、応答、かけ声などを表す言葉。
④倒置文の場合
(1)主語の前
・やぶの中から、ウサギが出てきた。
(2)述語が文の中間に置かれた場合、そのあとに打つ
・ぼくは知らないよ、そんなこと。
⑤カギの前
※会話・引用文の場合
(1) 力ギの前
・次郎が、「あれは何だろう」と言った。
(2) 会話や引用文でを力ギで囲まない場合、その前後
・次郎が、あれは何だろう、と言った。
⑥読み誤りや、読みにくさをさける
(1)読み誤りを避ける場合
・「大急ぎで、逃げる男のあとを追いかけた。」
・「大急ぎで逃げる男のあとを、追いかけた。」
(2)読みにくさを避ける場合
・裏の山の、松の木の上の鳥の巣が、風でこわれてしまった。
※「の」の連続使用や、「の」による単純連結にも注意しよう。
⑦読みの間(ま)
・チリン、チリリンと、風鈴が鳴る。
※「チリン、チリリン」とするか、「チリンチリリン」とするか、読点を打つ場所や有無によって、風鈴の鳴り方の違いを表すことができる。
⑧!(感嘆符)と?(疑問符)について
・もともと外国語に用いられる符号であり、和文に用いる場合は意図や効果を考えて使うようにしよう。
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。