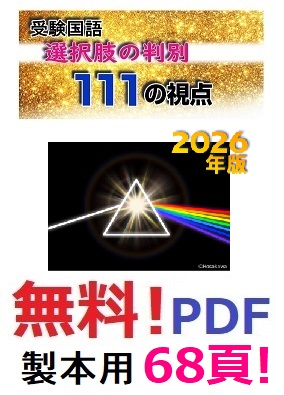中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
- ■方丈記(通釈)
- ■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
- 論理パズル
- 各種論理
- ・序 その一
- ・序 その二
- ・安元の大火(あんげんのたいか)
- ・治承の辻風(じしょうのつじかぜ)
- ・福原遷都(ふくはらせんと) その一
- ・福原遷都(ふくはらせんと) その二
- ・養和の飢饉(ようわのききん) その一
- ・養和の飢饉(ようわのききん) その二
- ・養和の飢饉(ようわのききん) その三
- ・元暦の大地震(げんりゃくのおおなゐ)
- ・煩悩の浮世(ぼんのうのうきよ)
- ・出家遁世(しゅっけとんせい)
- ・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その一
- ・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その二
- ・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その三
- ・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その四
- ・閑居の気味(かんきょのきび) その一
- ・閑居の気味(かんきょのきび) その二
- ・閑居の気味(かんきょのきび) その三
- ・早暁の思策(そうぎょうのしさく)
- ■剽窃について
■方丈記(通釈)
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。
論理パズル
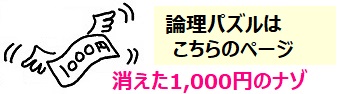
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
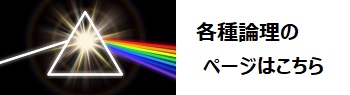
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
方丈らいふ
・見聞した天災の様相、この世の無常、閑居生活の情趣を述べた古典三大随筆のひとつ、蓮胤(れんいん:鴨長明(かものながあきら))の著した「方丈記」を通釈しました。仏道を歩むために遁世し、閑居の暮らしへの愛着を抱いたものの、皮肉にも執着心から逃れられないでいる自分に気づき自己糾明を行わざるをえなかった蓮胤(れんいん)の心境に触れてみましょう!
■以下の文献を参考にしました。
・古典解釈シリーズ 文法全解 「方丈記・無名抄」(島田良夫著)旺文社
・「方丈記」(川瀬一馬校中・現代語訳)講談社文庫
・少年少女古典文学館 「徒然草(嵐山光三郎)・方丈記(三木卓)」講談社
「行く河の……」の「河」はどこにある?
■「行く河の……」、実はこの有名な書き出しは論語の『子罕篇(しかんへん)』の中にある『川上の嘆(せんじょうのたん)』として知られた一章が元となっていると言われています。
・「先生が、川のほとりで流れゆく水を前にして、こう言われた。過ぎ去ってゆくものは皆、の川の流れのようなものだ。昼も夜も一時も休まないで、流れ去ってゆくことよ」
(子(し)、川の上(ほとり)にありて曰(いわ)く、逝(ゆ)く者は斬(か)くの如(ごと)きか、昼夜を舎(お)かず)
■また、『文選(もんぜん)』という中国南北朝時代の詩集がありますが、これに収められた陸士衡(りくしこう)の『歎逝賦(たんせいふ)一首』が出展であるという説もあります。
・「水は滔々(とうとう)と日々絶え間なく流れている。人もまた日々絶えることなく行き暮らしている。いかなる世にあっても、人は一新されることはなく、また、この世に生きる人であっても、昔のままではありえない」
(水は滔々(とうとう)として日々に度(わた)る。人は冉々(ぜんぜん)として行き暮らしぬ。何(いずれ)の世(よ)としてか弗(ざら)ん。絶えて新(あらた)なら、世(よ)何(いずれ)の人としてか、能(よ)く故(ふる)からん)
・語源的に「河」は「大きな川」の意味です。『川上の嘆』では『川』となっていますから、孔子が見つめた川は黄河などの大河ではなかったことになります。
■「無常」とは?
・「無常」ですぐに思い起こすのは、『平家物語』冒頭『祇園精舎の段』の一節や『いろは歌』です。
「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鳴り渡る鐘の音には、万物の絶えざる生滅(しょうめつ)を告げ知らせる響きがある。釈迦(しゃか)の入滅(にゅうめつ)とともにあせたという沙羅双樹(しゃらそうじゅ)の花の色も、栄華(えいが)を誇(ほこ)る者とて、いずれ必ず衰滅(すいめつ)するというこの世の道理を表している」
(祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響きあり。沙羅双樹(しゃらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(じょうしゃひっすい)のことわりをあらわす)
※釈迦…釈迦牟尼(しゃかむに)。ゴータマ・シッダールタ。紀元前5世紀頃の人。インド・ネパール国境付近の城主の子に生まれる。29歳で出家、35歳で悟り(さとり:心の迷いが解け、真理を会得〔えとく〕すること)を開き、仏陀(ぶっだ:悟りを得た人)となる。80歳で入滅(にゅうめつ:高僧が死ぬこと)。
※祇園精舎…釈迦に深く帰依(きえ:神仏を信仰して、その力にすがること)していた須達多(シュダッタ)という長者が釈迦のために建立(こんりゅう)した僧坊(そうぼう)で、その中の病僧を収容する無常堂の四隅(よすみ)に掛けられていた鐘が、病僧の臨終に際し自然に鳴って「諸行無常…」と説いたと伝えられる。
※諸行…万物。因果関係によって作られた、世界にあるすべての物事や現象のこと。
※無常…この世のすべてのものは生滅、変化して、少しもとどまることがないこと。人の世のはかないこと。
※沙羅双樹…サラノキ。高さ30m以上になるインドに産する落葉高木。釈迦が入滅した時、その四方に二本ずつあったというが、入滅とともにたちまち枯れて白くなったと伝えられる。
※盛者必衰のことわり…勢い盛んなものも必ず衰えるものだという道理。
※生滅…生ずることと滅びること。生と死。
■いろは歌(伊呂波歌)
・「花は色艶(あで)やかに咲くけれども、間もなく散り果ててしまう。人間の命もこの花と同じであって、永久に生き続けることはできない。それだから、空しい夢を見たり、人情におぼれたりする浮世(うきよ)の煩悩(ぼんのう)の境地(きょうち)から逃れて、ひたすら仏様にすがって往生(おうじょう)を祈ろう」
(色は匂(にほ)へど〈イロワニオエド〉、散りぬるを〈チリヌルヲ〉、我(わ)が世誰(たれ)ぞ〈ワガヨタレゾ〉、常(つね)ならむ〈ツネナラン〉。有為(うゐ)の奥山(おくやま)〈ウイノオクヤマ〉、今日(けふ)越(こ)えて〈キョウコエテ〉、浅き夢見じ〈アサキユメミジ〉、酔(ゑ)ひもせず〈エイモセズ〉
※浮世…辛(つら)くはかないこの世。
※煩悩…悟(さと)りを妨(さまた)げる人間のさまざまな心の働き。
※悟り…真理を会得(えとく)すること。
※往生…極楽浄土に生まれ変わること。
※極楽浄土…苦しみのない安楽の世界。
・『伊呂波歌』は 仏教の根本思想である、「万物は絶えず移り変わり生滅(しょうめつ)するもので、不変なものではない」という意味の、諸行無常(しょぎょうむじょう)の精神を訳したものです。
「無常」とはつまり、一切万物が絶えず移り変わり、生滅変化して、同じ状態にとどまっていないあり方をいい、仏教では教理の根本にこの思想を据(す)えているというわけです。古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの説いた「パンタ・レイ=万物は流転(るてん)す」という思想とも共通するものがあります。
■庵の「トイレ」は?
・とある研究者に伺ったところ、蓮胤(鴨長明)の住んだ庵の外に水洗トイレが設けられていたのではと推測しています。ただし、庵の南側には懸樋(かけひ)や水を溜めた岩などが配置されていましたから、当然下流側になるとのことです。具体的な位置、形状など詳細は不明です。今後の研究が待たれます。
・序 その一
行く河の流れは絶えずして
しかももとの水にあらず
よどみに浮かぶうたかたは
かつ消え かつ結びて
久しくとどまりたるためしなし
世の中にある人とすみかと
またかくのごとし
絶えることなく流れ続ける川は常に同じ姿を保ち、しかも、流れは決してもとの水ではありえない。淀(よど)みに浮かぶ泡(あわ)つぶは、そこではじけて消えたかと思えば、また新たに現れ、はかなく生滅(しょうめつ)を繰り返す。この世に生きる人も、世のありさまも、また、これと同じである。
・序 その二
玉敷(たましき)の都のうちに棟(むね)を並べ
甍(いらか)を争へる高き 卑(いや)しき人のすまひは
世々(よよ)を経(へ)て尽(つ)きせぬものなれど
これをまことかと尋(たず)ぬれば
昔ありし家はまれなり
あるいは 去年(こぞ)焼けて今年作れり
あるいは 大家(おおいえ)滅(ほろ)びて小家(こいえ)となる
住む人もこれに同じ
所も変はらず 人も多かれど
いにしへ見し人は 二、三十人が中に
わづかにひとり ふたりなり
朝(あした)に死に 夕べに生まるるならひ
ただ水のあわにぞ似たりける
知らず
生まれ死ぬる人 いづかたより来たりて いづかたへか去る
また知らず
仮の宿り たがためにか心を悩(なや)まし
何によりてか目を喜ばしむる
そのあるじとすみかと 無常を争ふさま
いはば朝顔の露(つゆ)に異ならず
あるいは露落ちて花残れり
残るといへども朝(あした)に枯れぬ
あるいは
花しぼみて露なほ消えず
消えずといへども夕べを待つことなし
はなやかで美しい京の町に、甍(いらか)を競(きそ)い合い 、建ち並んでいるさまざまな身分の人たちの住まいは、幾代(いくだい)にもわたりそこにそうしてあるものだ。しかし、それが真実かと確かめてみれば、昔からあった家は 実はかえって珍しい。去年焼失して今年建てなおした家もあれば、大きな家が没落(ぼつらく)し、小さな家に建て変わったものもある。
住んでいる人もまた、これと同じことだ。家の場所も以前と変わらず、人の数もまたかつてと同様に数多(あまた)いるというのに、昔会った人は 二、三十人の中で、わずかに一人二人である。朝どこかでだれかが死に、夕べにはまたどこかでだれかが生まれる世のならいは、まったく水の泡(あわ)のさまにそっくりではないか。
わからぬ。生まれ、死にゆく人は、どこからこの世に訪(おとず)れ、そして、どこへ去ってゆくのか。
わからぬ。
この世の仮の住まいのために心労(しんろう)し、それを飽(あ)かず眺(なが)めては楽しみ、それが一体何になるというのか。
家も住む人もが、ともに無常を競(きそ)い合うさまは、まさに朝顔の花と、その花びらに宿(やど)る朝露(あさつゆ)との関係と変わらない。あるときは露が落ちて花だけが残り、が、朝日を浴(あ)びれば、花はじきに萎(しお)れる。
またあるときは、花が先に萎(しぼ)み 露は消え残る。消え残るとはいえ、暮(く)れ方(がた)まで残り続けることはない。
・安元の大火(あんげんのたいか)
われ
ものの心を知れりしより
四十(よそじ)あまりの春秋(はるあき)を送れるあひ(い)だに
世の不思議を見ること ややたびたびになりぬ
去(い)んし安元(あんげん)三年四月(うづき)二十八日かとよ
風はげしく吹きて 静かならざりし夜
戌(いぬ)の時ばかり
都の東南(たつみ)より火出(い)で来て
西北(いぬい)に至る
はてには朱雀門(すざくもん) 大極殿(だいこくでん) 大学寮(だいがくりょう) 民部省(みんぶしょう)などまで移りて
一夜のうちに塵灰(ちりはい)となりにき
火(ほ)もとは樋口富(ひぐちとみ)の小路(こうじ)とかや
舞人(まいびと)を宿せる仮屋(かりや)より
出(い)で来たりけるとなん
吹き迷(まよ)ふ風に
とかく移りゆくほどに
扇(おうぎ)をひろげたるがごとく 末広(すえひろ)になりぬ
遠き家は煙(けぶり)にむせび
近きあたりはひたすら ほのほ(お)を地に吹きつけたり
空には灰(はい)を吹き立てたれば
火の光に映(えい)じて あまねく紅(くれない)なる中に
風に堪(た)えず吹き切られたるほのほ(お)
飛ぶがごとくして 一ニ町を越えつつ移りゆく
その中の人 現(うつ)し心あらむや
或(ある)は煙(けぶり)にむせびて 倒(たお)れ伏(ふ)し
或(ある)はほのほ(お)にまぐれて たちまちに死ぬ
或(ある)は身ひとつから(ろ)うじてのがるるも
資財(しざい)を取り出(い)づるに及(およ)ばず
七珍万宝(しっちんまんぽう) さながら灰燼(かいじん)となりにき
その費(つい)え いくそばくぞ
そのたび 公卿(くぎょう)の家十六焼けたり
ましてその外(ほか)数へ知るに及ばず
すべて都のうち 三分(さんぶ)が一に及(およ)べりとぞ
男女(なんにょ)死ぬるもの数十人
馬、牛のたぐひ 辺際(へんさい)を知らず
人の営(いとな)み
皆(みな)愚(おろか)なるなかに
さしも危(あや)ふき京中(きょうじゅう)の家をつくるとて
宝を費(ついや)し 心を悩(なやま)すことは
すぐれてあぢきなくぞはべる
私が、ものごころがついてから、四十年余(あま)りの年月を過ごしてきた間には、世の中の思いがけない出来事を目にする機会もたびたびあったものだ。
去る安元(あんげん)三年、四月二十八日のことであったか、風が激(はげ)しく吹(ふ)き 少しも収(おさ)まらぬまま、夜八時ごろ、都の東南(たつみ)方より火がおこり、西北(いぬい)方へと燃え広がり、ついには朱雀門(すざくもん) 大極殿(だいこくでん)、大学寮(だいがくりょう)、民部省(みんぶしょう)にまで焼け移り、一夜のうちにそれらは 灰燼(かいじん)に帰(き)してしまった。
火元(ひもと)は樋口富(ひぐちとみ)の小路(こうじ)とかで、舞人(まいびと)を泊(と)めていた仮屋(かりや)から出火したということだ。
狂(くる)いすさぶ風に、あちこち燃え広がっていくうちに、扇(おうぎ)を広げたように末広(すえひろ)がりとなって燃え移っていった。火災より遠くにある家々は 、煙のためにむせび、近く燃えさかる辺りは、ただ、もう火炎(かえん)を地に勢いよく吹きつけるばかりだった。
空には高々と灰煙(はいえん)を吹き上げていたので、それが火の光に照らし出され、あたり一面真っ赤になっている中に、風の激しさに堪(た)えきれず、吹きちぎられた火炎が飛ぶようにして、一、ニ町も飛び越え、燃え広がっていく
そんなありさまの只中(ただなか)にいた人たちは、それは生きた心地(ここち)が しなかったことだろう。ある者は煙にむせんで倒れ伏(ふ)し、ある者は火炎(かえん)にまかれ、たちまちにして死んでいった。ある者は、身(み)一つでかろうじて逃(のが)れはしても、家財(かざい)を持ち出すまでは叶(かな)わず、貴重な財宝もそっくり灰と化した。その損害(そんがい)たるや、いかほどのものだったろう。
この大火(たいか)で、公卿(くぎょう)の屋敷(やしき)が十六件も焼けたほどだ。まして、その他の家の焼失(しょうしつ)数たるや、到底(とうてい)計(はか)り知れない。まさに、都(みやこ)の三分の一の域(いき)に及(およ)ぶ大火であったという。男女併(あわ)せて、焼死(しょうし)した者数十人。馬や牛の家畜類(かちくるい)に至(いた)っては、焼け死んだその数は把握(はあく)も出来ぬ。
人の営(いとな)みの愚(おろ)かさの中でも、わざわざこれほど危険な京の町なかに家を建てんがために、資財(しざい)を投(とう)じ、あれやこれやと心労(しんろう)することほど、とりわけ馬鹿(ばか)げた無駄(むだ)なことはございません。
・治承の辻風(じしょうのつじかぜ)
また
治承四年四月(うづき)のころ
中御門(なかみかど) 京極(きょうごく)のほどより
大きなる辻風(つじかぜ)おこりて
六条わたりまで吹けることはべりき
三四町を吹きまくる間に
こもれる家ども
大きなるも小さきも
一つとして破れざるはなし
さながらひらに倒れたるもあり
桁(けた)柱(はしら)ばかり残れるもあり
門(かど)を吹きはらひて 隣(となり)と一つになせり
いはむや
家のうちの資財(しざい)
数を尽(つ)くして空(そら)にあり
檜皮(ひはだ)葺板(ふきいた)のたぐひ
冬の木の葉の風に乱るるがごとし
塵(ちり)を煙のごとく吹き立てたれば
すべて目も見えず
おびただしく鳴りよどむほどに
もの言ふ声も聞こえず
かの地獄の業(ごう)の風なりとも
かばかりにこそはとぞおぼゆる
家の損亡(そんもう)せるのみにあらず
これを取り繕(つくろ)ふ間に 身をそこなひ
かたはづける人 数も知らず
この風
未(ひつじ)の方(かた)に移りゆきて
多くの人の歎(なげ)きなせり
辻風は常に吹くものなれど
かかることやある
ただごとにあらず
さるべきもののさとしかなどぞ
疑ひはべりし
また
治承(じしょう)四年四月のころ、中御門(なかみかど)京極(きょうごく)の辺(あた)りより大きなつむじ風が巻(ま)き起こり、六条界隈(かいわい)まで吹きぬけるという出来事がございました。
三四町を猛烈(もうれつ)な勢いで吹きぬける間に、そのつむじ風に巻き込まれた家は、大きな家も 、小さな家も、一つとして壊(こわ)れないものはなかった。
そっくりそのまま ぺしゃんこにひしげた家もあれば、無残に桁(けた)や柱だけが残された家もあった。門を吹き飛ばして、四五町も離(はな)れたところに放り置かれ、また、垣根(かきね)を吹き払(はら)って隣家(りんか)との境(さかい)が失われてしまったところもあった。
そんなありさまだから、ましてや、家の中の財宝などは一切(いっさい)が大空に舞(ま)い上がり、屋根に葺(ふ)いてあった檜皮(ひはだ)や葺板(ふきいた)などが吹き飛ぶさまは、まるで冬の木の葉が風のため大空に乱(みだ)れ狂(くる)うようであった。
ほこりを煙のように吹き立てたので、まったく何も見えず、渦巻(うずま)く風がごうごうと鳴り響(ひび)くので、もの言う声も聞こえない。あの地獄(じごく)に吹きまくる悪業(あくごう)の風にしても、これほどのものであろうかと思われるのだった。
家屋が損壊(そんかい)しただけではなく、壊(こわ)されまいとその家を必死に防(ふせ)いでいた間にも、身体に怪我(けが)を負い、不自由になった者が数知れない。
このつむじ風は、その後南南西の方に移り行き、また多くの人々の悲嘆(ひたん)を生んだ。つむじ風が吹くことは、さしてめずらしいことではないにしろ、これほどまでにひどく吹くつむじ風はまずないだろう。
これはただごとではあるまいと、何か神や仏のお諭(さと)しではあるまいかなどと、人々は疑い恐(おそ)れたことでした。
・福原遷都(ふくはらせんと) その一
また
治承(じしょう)四年水無月(みなづき)のころ
にはかに都 遷(うつ)りはべりき
いと思ひの外(ほか)なりしことなり
おほかた
この京(きょう)のはじめを聞けることは
嵯峨(さが)の天皇の御時(おんとき)
都と定まりにけるより後
すでに四百余歳(しひゃくよさい)を経(へ)たり
ことなるゆゑ(え)なくて
たやすく改まるべくもあらねば
これを世(よ)の人
安からず憂(うれ)へあへる
げにことわりにも過ぎたり
されど
とかくいふかひなくて
帝(みかど)より始め奉(たてまつ)りて
大臣(だいじん)公卿(くぎょう)
みなことごとく移ろひたまひぬ
世に仕(つか)ふるほどの人
たれか一人ふるさとに残りをらむ
官(つかさ)位(くらひ)に思ひをかけ
主君(しゅくん)のかげを頼(たの)むほどの人は
一日なりともとく移ろはむとはげみ
時を失ひ
世に余(あま)されて
期(き)する所なきものは
愁(うれ)へながらとまりをり
軒(のき)を争ひし人のすまひ
日を経(へ)つつ荒れゆく
家はこぼたれて
淀河(よどがわ)に浮かび
地は目のまへに畠(はたけ)となる
人の心みな改まりて
ただ馬 鞍(くら)をのみ重くす
牛 車を用(よう)する人なし
西南海(さいなんかい)の領所(りょうしょ)を願ひて
東北の荘園(しょうえん)を好まず
また、治承(じしょう)四年六月のころ、突如(とつじょ)として遷都(せんと)が行われました。それはまったく思いがけないことだった。
そもそも、この平安京の起こりについて、聞くところでは、嵯峨(さが)天皇の御代(みよ)に都と定められてのち、すでに四百年余(あま)り、格別(かくべつ)の訳(わけ)なく、そう易(やす)く都を移(うつ)してよいはずもない。世人(せじん)の不安、憂(うれ)い合うのも無理からぬことだった。
しかしながら、とかく案じたかいもなく、天皇より始め申し上げ、大臣(だいじん) 公卿(くぎょう)方も、その後、みな残らずお移りになった。
それゆえ、朝廷(ちょうてい)にお仕(つか)えする身分の人たちは、誰(だれ)一人京に留(とど)まろうという者はない。
官位(かんい)を望み、主君(しゅくん)のお蔭(かげ)を頼(たよ)りとするほどの人たちは、一日なりとも早く都移(うつ)りをしようと努め、時機を失(しっ)し、立つ瀬(せ)を失った者は、憂(うれ)いに沈(しず)んで、京に留(とど)まった。
軒(のき)を競(きそ)い合った人々の住まいは、日を経(へ)るにしたがい、荒(あ)れ果(は)てていった。家は解(と)き壊(こわ)され、筏(いかだ)に組まれて淀川(よどがわ)を運ばれ、更(さら)になった土地は、たちまちにして畠(はたけ)と化(か)した。
人心(じんしん)もすっかり変わり、武家(ぶけ)のように馬や鞍(くら)ばかりを重んじ、牛や牛車(ぎっしゃ)を用立てる者はなくなった。九州、四国、中国、富(と)んだ平家(へいけ)の土地を領地(りょうち)に望んでも、誰(だれ)も遠地(えんち)東国、北陸、源氏(げんじ)の土地を自(みずか)ら望もうとはしなかった。
・福原遷都(ふくはらせんと) その二
その時
おのづからことの便りありて
津の国の
今の京に至れり
所のありさまを見るに
その地 程(ほど)せばくて
条理(じょうり)を割るに足らず
北は山に添(そ)ひて高く
南は海近くて下れり
波の音
常にかまびすしく
塩風ことにはげし
内裏(だいり)は山の中なれば
かの木の丸殿(まろどの)もかくやと
なかなか様(よう)変はりて
優(ゆう)なるかたもはべり
日々にこぼち
川も狭(せ)に
運びくだす家
いづくに作れるにかあるらむ
なほ空(むな)しき地は多く
作れる家(や)は少なし
古京(こきょう)はすでに荒れて
新都(しんと)はいまだ成らず
ありとしある人は
皆
浮雲(うきぐも)の思ひをなせり
もとよりこの所にをるものは
地を失ひて愁(うれ)ふ
今移れる人は
土木のわづらひあることを嘆(なげ)く
道のほとりを見れば
車に乗るべきは馬に乗り
衣冠(いかん) 布衣(ほひ)なるべきは
多く直垂(ひたたれ)を着たり
都の手振(てぶ)り たちまちに改まりて
ただひなびたる
武士(もののふ)に異ならず
世の乱るる瑞相(ずいそう)とか
聞けるもしるく
日を経つつ
世の中浮き立ちて 人の心もをさまらず
民の愁(うれ)へ
つひに空しからざりければ
同じき年の冬
なほこの京に帰りたまひにき
されど
こぼちわたせりし家どもは
いかになりにけるにか
ことごとくもとのやうにしも作らず
伝へ聞く
古(いにしへ)の賢(かしこ)き御世(みよ)には
憐(あはれ)みを以(も)って
国を治めたまふ
すなはち
殿(との)に茅(かや)ふきて
その軒(のき)をだにととのへず
煙の乏しきを見たまふ時は
限りある貢物(みつぎもの)をさへゆるされき
これ
民を恵(めぐ)み
世を助けたまふによりてなり
今の世のありさま
昔になぞらへて知りぬべし
そのころ、用事のついでがあって、摂津(せっつ)の国の、福原の都に赴(おもむ)いた。
都の様子を見ると、土地が狭(せま)く、町割(わ)りをするには余裕(よゆう)がない。北は山の傾斜(けいしゃ)に添(そ)って高くなり、南は近く海へと下(くだ)っている。波の音が絶(た)えず騒(さわ)がしく、潮風がことのほか激(はげ)しく吹(ふ)く。
それでも、内裏(だいり)は山の中に建てられたので、昔のあの木の丸殿(まろどの)の姿(すがた)もこのようであったろうかと、かえって新奇(しんき)に感じられ、感興(かんきょう)を催(もよお)したものだ。
さて、日ごと解体(かいたい)し、川も狭(せま)しといかだに組んで運び下した家は、一体(いったい)どこに建て改(あらた)められたであろうか。見渡(わた)したところ、いまだ空(あ)いたままの土地は多く、建てられた家は少ない。
京都はすでに荒(あ)れ果(は)てたのに、福原京はいまだ完成しない。ありとあらゆる人々が、空を流れる雲のように、不安な思いの中に漂(ただよ)っていた。
もともと福原に住み暮(く)らしていた者たちは、土地を召(め)し上げられ、嘆(なげ)き、新たに移(うつ)り住んで来た者は、土木(どぼく)建築(けんちく)の煩(わずら)いを嘆く。
道行く人を見ると、牛車(ぎっしゃ)に乗るべき者が馬に乗り、衣冠(いかん)や布衣(ほい)を着るべき者が、多く直垂(ひたたれ)を着ている都の風俗(ふうぞく)が、見る間に改(あらた)まり、田舎(いなか)びた武家風(ぶけふう)と変わらないありさまだ。
このようなことは、世の中が乱(みだ)れる兆(きざ)しであると、ものの本に記(しる)されているが、まさにその通りで、日が経(た)つにつれ、世間はざわつき、人心も不穏(ふおん)で、人々の愁訴(しゅうそ)の願いは、まさにその通りになり、同じ年の冬、天子(てんし)様は、元(もと)どおり京都にお帰りになることになった。
しかしながら、取り壊(こわ)して運んだ家などは
どうなったことやら、みながみな、元のようには戻(もど)らずにしまった。
伝え聞くところによれば、昔の名君(めいくん)の御代(みよ)には、民(たみ)への慈(いつく)しみをもって、国を治(おさ)められたという。そのため、御住(おすま)いに茅(かや)を葺(ふ)いても、その軒先(のきさき)を切りそろえず、また、民(たみ)のかまどの煙(けむり)が乏(とぼ)しいありさまをご覧(らん)になると、決まっている年貢(ねんぐ)さえも免除(めんじょ)なされたという。
これは、民(たみ)を憐(あわ)れみ、世を救(すく)おうという、ご配慮(はいりょ)あってのことである。今の世のありさま、昔と比べていかなるものかが、よくわかるというものだ。
・養和の飢饉(ようわのききん) その一
また
養和(ようわ)のころとか
久しくなりて覚えず
二年(ふたとせ)があひだ
世の中飢渇(けかつ)して
あさましきことはべりき
或(ある)は春
夏 ひでり
或は秋
大風 洪水など
よからぬことどもうち続きて
五穀(ごこく)ことごとくならず
むなしく春かへし
夏植うるいとなみありて
秋刈(か)り
冬収(おさ)むる
ぞめきはなし
これによりて
国々の民(たみ)
或(ある)は地を棄(す)てて
境(さかい)を出(い)で
或は家を忘れて山に住む
さまざまの御祈(おんいの)りはじまりて
なべてならぬ法ども行(おこな)はるれど
さらにそのしるしなし
京のならひ
何わざにつけても
みなもとは田舎(いなか)をこそ頼めるに
絶えて上るものなければ
さのみやは操(みさお)もつくりあへん
念じわびつつ
さまざまの財物(たからもの)
かたはしより捨つるがごとくすれども
さらに
目見立つる人なし
たまたま換(か)ふるものは
金(こがね)を軽くし
粟(ぞく)を重くす
乞食(こつじき)路(みち)のほとりに多く
愁(うれ)へ悲しむ声
耳に満(み)てり
また、養和(ようわ)のころであったか、随分(ずいぶん)以前のことではっきり覚えてはいないが、二年もの間、飢饉(ききん)が訪(おとず)れて、人々が飢(う)えるさまは、何とも言いようのない酷(ひど)い事態が起こりました。
春や夏に日照り続きの年があれば、秋に台風や洪水(こうずい)に襲(おそ)われ通しの年もあり、良からぬことばかりがうち続いて、作物はとんと実らない。
春には耕作(こうさく)し、夏に苗(なえ)を植える営(いとな)みがあっても、秋に収穫(しゅうかく)し、冬には収納するという、恒例(こうれい)のにぎわいは、皆目(かいもく)見ることができなかった。
このために諸国(しょこく)の人々は、ある者は土地を捨(す)てて、故郷(こきょう)を出、ある者は家を捨てて、山中に移(うつ)り住んだりもした。
さまざまな祈祷(きとう)が始まり、格別(かくべつ)念入りな加持祈祷(かじきとう)も行われたが、一向(いっこう)に効(き)き目は現れなかった。
都の暮らしは、何事につけても、田舎(いなか)を頼(たよ)りとして成り立っているものだが、物資(ぶっし)がさっぱり届(とど)いてこないので、そうそういつものように平静(へいせい)を保っていられるはずもない。
我慢(がまん)しようにも耐(た)えられなくなり、さまざまな財宝(ざいほう)、調度品(ちょうどひん)を手当たり次第に処分(しょぶん)するが、それに目をくれる者もいない。
まれに食糧と交換(こうかん)するときは、財宝の値打ちなどずっと低く、穀物(こくもつ)の値打ちのほうがずっと重かった。
物乞(ものご)いが路傍(ろぼう)にあふれ、愁(うれ)い悲しむ声がいたるところで耳についたものだった。
・養和の飢饉(ようわのききん) その二
前の年
かくのごとくからうじて暮れぬ
明くる年は立ち直るべきかと思ふほどに
あまりさへ疫癘(えきれい)うちそひて
まさまさに
あとかたなし
世の人みなけいしぬれば
日を経(へ)つつ
きはまりゆくさま
少水(しょうすい)の魚(いお)のたとへに
かなへり
はてには
笠(かさ)うち着
足引き包み
よろしき姿したるもの
ひたすらに家ごとに乞(こ)ひありく
かくわびしれたるものどもの
ありくかと見れば
すなはち倒れ伏(ふ)しぬ
築地(ついひじ)のつら
道のほとりに
飢(う)え死ぬるもののたぐひ
数も知らず
取り捨つるわざも知らねば
くさき香(か)世界に満ち満ちて
変はりゆくかたちありさま
目も当てられぬこと多かり
いはむや
河原(かわら)などには
馬
車の行きかふ道だになし
あやしき賤(しず)
山がつも力尽きて
薪(たきぎ)さへ乏(とぼ)しくなりゆけば
頼むかたなき人は
みづからが家をこぼちて
市(いち)に出でて売る
一人が持ちて
出でたる価(あたい)
一日(ひとひ)が命にだに
及(およ)ばずとぞ
あやしきことは
薪の中に
赤き丹(に)着き
箔(はく)など所々に見ゆる木
あひまじはりけるを尋(たず)ぬれば
すべきかたなきもの
古寺(ふるでら)に至(いた)りて
仏を盗(ぬす)み
堂(どう)の物の具(ぐ)を破り取りて
割り砕(くだ)けるなりけり
濁悪(じょくあく)の世にしも
生まれ合ひてかかる心憂(う)きわざをなん
見はべりし
前の年は、こうして、どうにかやっと終わった。
翌年は何とか復興(ふっこう)するかと思っていると、悪い流行病(はやりやまい)が加わって、ますますひどいありさまだった。
世の人々は皆飢(う)えてしまったので、日が経(た)つにつれ、窮乏(きゅうぼう)してゆくさまは、わずかなたまり水にあえぐ、魚のたとえに異(こと)ならない。
ついには笠(かさ)をかぶり、足を脚半(きゃはん)で巻(ま)き包(つつ)み、結構(けっこう)な身なりをした者でさえが一心(いっしん)になり、家ごとに物乞(ものご)いをして歩く。
かようにまで困窮(こんきゅう)した人たちは、今歩いているかと思いきや、次にはたちまち倒れ伏(ふ)している。
土塀(どべい)の傍(かたわ)ら、道の端(はた)で
飢(う)え死んだ人たちの数は、計(はか)り知れない。
遺骸(いがい)の処理の術(すべ)もわからず、異様な悪臭(あくしゅう)が辺りに充(み)ち充ち、遺骸の変貌(へんぼう)してゆく目も当てられないさまに遭遇(そうぐう)することが度々(たびたび)あった。
まして、賀茂(かも)の河原(かわら)などには遺骸がおびただしく横たわり、馬や車の行き交(か)う道さえなかった。
卑(いや)しい木こりも力尽(つ)き、都には薪(たきぎ)までが不足したので、暮らしのあての立たない者は、自分の家を壊(こわ)して、市(いち)に運び出しては売りさばく。
一人が運び出して得た薪(たきぎ)の価(あたい)は、一日の命をつなぐにさえ足りないくらいだったという。
怪(あや)しいことには、この薪(たきぎ)の中には、赤く塗られたもの、所々に金箔(きんぱく)の付いた木片(もくへん)があり、そのわけを探(さぐ)ってみると、
暮らしの術(すべ)に困り果てた者が、古寺(こじ)に忍(しの)び入って、仏像を盗(ぬす)んだり、お堂の器物(きぶつ)や調度品(ちょうどひん)を取り壊(こわ)し、打ち砕(くだ)いて薪に売ったものだった。
濁悪(じょくあく)の末世(まっせ)に生まれ合わせ、このような人間の情けない所業(しょぎょう)を、私は
目にしなければならなかったのです。
・養和の飢饉(ようわのききん) その三
また
いとあはれなることもはべりき
さりがたき妻(め)
を(お)とこ持ちたるものは
その思いまさりて深きもの
必ず先立ちて死ぬ
その故(ゆえ)は
わが身は次にして
人をいたはしく思ふあひだに
まれまれ得たる食ひ物をも
かれに譲(ゆず)るによりてなり
されば
親子あるものは
定まれることにて
親ぞ先立ちける
また
母の命尽(つ)きたるを知らずして
いとけなき子の
なほ乳を吸ひつつ
臥(ふ)せるなどもありけり
仁和寺(にんなじ)に
隆暁法印(りゅうぎょうほういん)といふ人
かくしつつ
数も知らず死ぬることを悲しみて
その首(こうべ)の見るごとに
額(ひたい)に阿字(あじ)を書きて
縁(えん)を結ばしむるわざをなん
せられける
人数(ひとかず)を知らむとて
四五両月を
数へたりければ
京のうち一条よりは南
九条(くじょう)より北
京極(きょうごく)よりは西
朱雀(すざく)よりは東の
路(みち)のほとりなる頭(かしら)
すべて四万二千三百余りなんありける
いはむや
その前後に死ぬるもの多く
また河原
白川
西の京
もろもろの辺地(へんち)などを
加へていはば
際限(さいげん)もあるべからず
いかにいはむや
七道(しちどう)諸国をや
崇徳院(すとくいん)の御位(みくらい)の時
長承(ちょうじょう)のころとか
かかる例(ためし)ありけりと聞けど
その世のありさまは
知らず
まのあたり
めづらかなりしことなり
また、たいそう心動かされることもあった。
互いに離(はな)れがたく愛し合う夫婦は、恩愛(おんあい)の情の、より勝(まさ)る側が、必ず先に死んでいった。
そのわけは、わが身のことは差し置いて、相手をいたわしく思うがため、たまさか手に入れた食べ物さえも、相手に譲(ゆず)ってしまうためである。
それゆえ、親子で暮らしているものは、決まって親が先立っていった。
また、母の命の尽(つ)きたのを知らず、子(おさなご)が、横になりつつ、なお乳(ちち)を吸っている姿もあった。
仁和寺(にんなじ)におられた隆暁法印(りゅうぎょうほういん)という方は、こうして数え切れぬほどの人々が死ぬのを悲しんで、遺骸(いがい)に出会うたびに、額(ひたい)に「阿」の字を書いて、仏縁(ぶつえん)を結ばせる善行(ぜんこう)をなさった。
死んだ人の数を知ろうと、四月五月の両月、数えてみたら
京都、すなわち一条より南、九条(くじょう)より北、京極(きょうごく)より西、朱雀(すざく)より東の域内(いきない)、路傍(ろぼう)の遺骸(いがい)は、四万二千三百余りにも及(およ)んだ。
まして、この両月の前後二月(ふたつき)に死んだ者も多く、また、賀茂(かも)河原、白河、西の京ほか、郊外(こうがい)、辺地(へんち)などを勘定(かんじょう)に入れれば、限(さいげん)もなかっただろう。
ましてや、全国においてのその惨状(さんじょう)たるや、言語に絶(ぜっ)しよう。
崇徳院(すとくいん)がご在位(ざいい)の時代、長承(ちょうじょう)のころ、このような悲惨(ひさん)な飢饉(ききん)があったというが、当時の惨状(さんじょう)はわからない。
しかし、この度(たび)の飢饉の惨状(さんじょう)は、
私自身が目(ま)の当たりにした現実であり、めったに経験することのない出来事だったのだ。
・元暦の大地震(げんりゃくのおおなゐ)
また
同じころかとよ
おびただしく
大地震(おおない)ふることはべりき
そのさま
よのつねならず
を山はくづれて河(かわ)を埋(うず)み
海は傾(かたぶ)きて
陸地(くがち)をひたせり
土裂(さ)けて水湧(わ)き出(い)で
巌(いわお)割れて谷に
まろび入る
なぎさ漕(こ)ぐ船は波にただよひ
道行く馬はあしの立ちどをまどはす
都のほとりには
在々所々(ざいざいしょしょ)
堂舎(どうしゃ)塔廟(とうびょう)
一つとして全(まった)からず
或(ある)はくづれ
或はたふれぬ
塵(ちり)灰(はい)たちのぼりて
盛りなる煙のごとし
地の動き
家のやぶるる音
雷(いかずち)にことならず
家の内にを(お)れば
たちまちにひしげなんとす
走り出(い)づれば
地割れ裂(さ)く
羽なければ
空をも飛ぶべからず
龍(りゅう)ならばや
雲にも乗らむ
恐れのなかに恐るべかりけるは
ただ
地震(ない)なりけりとこそ
覚えはべりしか
かく
おびただしくふることは
しばしにてやみにしかども
その余波(なごり)
しばしは絶(た)えず
よのつね
驚くほどの地震
ニ三十度ふらぬ日はなし
十日
二十日過ぎにしかば
やうやう間遠(まどお)になりて
或(ある)は四五度
ニ三度
もしは一日まぜ
ニ三日に一度など
おほかたその余波
三月ばかりやはべりけむ
四大種(しだいしゅ)のなかに
水(すい)火(か)風(ふう)は
つねに害をなせど
大地にいたりては
異なる変をなさず
昔
斎衡(さいこう)のころとか
大地震(おおない)ふりて
東大寺の仏の御首(みぐし)落ちなど
いみじきことどもはべりけれど
なほこの度(たび)には如(し)かずとぞ
すなはちは
人はみなあぢきなきことをのべて
いささか心の濁(にご)りもうすらぐと
見えしかど
月日かさなり
年経(へ)にしのちは
ことばにかけて
言ひ出(い)づる人だになし
また、これも飢饉(ききん)のときと同じ頃(ころ)のことだった。ひどく大きな地震があって、激(はげ)しく揺(ゆ)れたことがありました。
そのありさまといったら、誠(まこと)にただ事ではない。山は崩(くず)れ落ちて、河を埋(うず)め、海は揺(ゆ)れに揺れて、津波(つなみ)が押し寄せ、陸は海水で一面が浸(ひた)された。
大地は裂(さ)けて、水が噴(ふ)き出し、岩壁(いわかべ)は谷に崩(くず)れ落ちた。
沿岸(えんがん)を漕(こ)ぎ進んでいた船は転覆(てんぷく)して波間(なみま)に漂(ただよ)い、道行く馬は
踏(ふ)み所(どころ)定まらず、足をあがいた。
都の郊外(こうがい)では、あちらこちらのお堂(どう)や塔廟(とうびょう)が倒壊(とうかい)し、一つとして
無事なものはなかった。あるものは崩(くず)れ、あるものは倒(たお)れしていた。
ちりや埃(ほこり)が空に立ち昇(のぼ)り、燃え盛(さか)る煙(けむり)のようだった。大地の揺れ動く音、家屋(かおく)の倒壊(とうかい)する音のすさまじさは、まるで轟(とどろ)く雷鳴(らいめい)のようであった。
家の中にいれば、たちまちにして押(お)しつぶされそうになり、外へ走り出れば、地割(じわ)れするありさまだ。
鳥ではないので羽はなく、空へと逃(に)げ飛ぶわけにもゆかず、龍(りゅう)であったならば、雲に乗ることもできただろうが。
恐ろしいもののうちで、この地震というものほど恐ろしいものが他にあろうかと、つくづく思ったことでした。
このような、ひどく揺れる地震は、暫時(ざんじ)で止(や)んだが、余震(よしん)はしばらく絶えず、普段でさえ驚くような地震が、ニ三十度と揺れない日はなかった。
十日、二十日と過ぎてしまうと、次第に地震も間遠(まどお)になり、あるときは日に四、五度、あるときはニ、三度、もしくは、一日おき、ニ、三日に一度などと、およそその余震は三月(みつき)ばかり続いたでしょうか。
四大種(しだいしゅ)のうち、水(すい)火(か)風(ふう)は常に害を及(およ)ぼすが、大地に至(いた)っては、格別(かくべつ)の異変(いへん)をもたらさない。
昔、斎衡(さいこう)二年のころ、やはり大地震があったと聞く。東大寺の大仏のお首が落ちるなど、たいそうひどいこともあったそうだが、この度(たび)の地震には及(およ)ばなかったという。
災(わざわ)いの当座(とうざ)、人はみな、この世の無常(むじょう)を嘆(なげ)いて、いささかでも日常の煩悩(ぼんのう)が薄(うす)らいだかと思いきや、月日が重なり、年月を経(へ)るにしたがって、地震の恐ろしさを口にして、話の種にする者さえなくなった。
・煩悩の浮世(ぼんのうのうきよ)
すべて世の中のありにくく
我が身と栖(すみか)との
はかなく
あだなるさま
かくのごとし
いはむや
所により
身の程(ほど)にしたがひつつ
心を悩(なや)ますことは
あげて数ふべからず
もし
おのれが身
数ならずして
権門(けんもん)のかたはらに
をるものは
深くよろこぶことあれども
大きにたのしむにあたはず
なげき切(せつ)なるときも
声をあげて泣くことなし
進退(しんだい)やすからず
起居(たちい)につけて
恐れおののくさま
たとへば
雀(すずめ)の鷹(たか)の巣に近づけるがごとし
もし
貧しくして
富める家のとなりにをるものは
朝夕すぼき姿を恥(は)ぢて
へつらひつつ出(い)で入る
妻子(さいし)
僮僕(どうぼく)の
羨(うらや)めるさまを見るにも
福家(ふくか)の人の
ないがしろなるけしきを聞くにも
心念々(ねんねん)に動きて
時として安からず
もし
せばき地にをれば
近く炎上ある時
その災(さい)をのがるることなし
もし
辺地(へんち)にあれば
往反(おうへん)わづらひ多く
盗賊(とうぞく)の難(なん)はなはだし
また
いきほひあるものは
貪欲(どんよく)ふかく
ひとり身なるものは人にかろめらる
財(たから)あればおそれ多く
貧しければうらみ切なり
人を頼めば
身
他の有(ゆう)なり
人をはぐくめば
心
恩愛(おんあい)につかはる
世にしたがへば
身くるし
したがはなば
狂(きょう)せるに似(に)たり
いづれの所を占(し)めて
いかなるわざをしてか
しばしもこの身を宿し
たまゆらも心を休むべき
総(そう)じて、世の中が暮らしにくく、わが身と住まいとのはかなく頼(たの)みにならぬありさまは、ここに述(の)べてきたとおりである。
ましてや、境遇(きょうぐう)によって、それぞれが心労(しんろう)すること、いちいち枚挙(まいきょ)にいとまがないほどである。
もし、わが身がとるに足らぬ身分で、権勢(けんせい)ある者の傍(かたわ)らで暮らしを立てていれば、深く喜ぶことがあっても、気がねがあって、思う存分楽しむことはできない。
悲しみ極(きわ)まるときでさえ、声を上げて泣くこともできない。
一挙一動(いっきょいちどう)、不安を抱(いだ)くまま、起居(たちい)振舞(ふるま)いも落ち着かず、何ごとにつけても、びくつくさまは、雀(すずめ)が鷹(たか)の巣のそばに近づいたときのありさまと同じである。
もし、貧しくて、なお富裕(ふゆう)な家の隣(となり)に住んでいれば、朝も晩(ばん)もみすぼらしい身なりを恥(は)じ、相手にへつらいつつ、家を出入りするようになる。
妻子や奉公(ほうこう)の者が、富裕な家を羨望(せんぼう)するさまを見るにつけても、また、富豪(ふごう)の家の者が、貧しい自分たちを蔑(さげす)む気配(けはい)を知るにつけても、心は瞬時(しゅんじ)に揺(ゆ)れ動き、穏(おだ)やかならぬままである。
もしまた、都の狭小(きょうしょう)な土地に住んでいれば、近隣(きんりん)に火災が生じた時、その災難(さいなん)を逃(のが)れることはできない。
もし、辺地(へんち)に住んでいれば、余所(よそ)との往来(おうらい)が煩(わずら)わしく、盗賊(とうぞく)の難儀(なんぎ)も計り知れない。
また、権勢(けんせい)ある者は、どこまでも欲(よく)深く、後ろ盾(だて)ない者は、他人に軽(かろ)んじられる。
財産(ざいさん)が豊富であれば、気をもむことも多くなり、貧乏(びんぼう)であれば、他人を羨(うらや)む思いにとらわれがちとなる。
他人の世話になれば、わが身はまるで、他人のものである。
他人を世話すれば、わが心はまた、恩愛(おんあい)に
とらわれてしまう。世間に従って暮らせば、束縛(そくばく)に苦しむ。世間に従わなければ、狂人(きょうじん)扱(あつか)いされる。
一体、どんな所に住まいを定め、どんな暮らしぶりをすれば、しばしの間でも心おきなくこの身を宿(やど)し、ほんのわずかでも、心を休めることができるというのか。
・出家遁世(しゅっけとんせい)
わが身
父方の祖母(おおば)の家をつたへて
久しくかの所に住む
その後
縁(えん)かけて身衰(おとろ)へ
しのぶかたがたしげかりしかど
つひにあととむることを得ず
三十(みそじ)あまりにして
さらにわが心と
一つの庵(いおり)を結ぶ
これをありしすまひにならぶるに
十分(じゅうぶ)が一なり
居屋(いや)ばかりをかまへて
はかばかしく
屋(や)をつくるに及(およ)ばず
わづかに
築地(ついひじ)をつけりといへども
門を建つるたづきなし
竹を柱として車をやどせり
雪降り
風吹くごとに
あやふからずしもあらず
所
河原近ければ
水の難も深く
白波(しらなみ)のおそれもさわがし
すべて
あられぬ世を念じすぐしつつ
心をなやませること
三十余年(よねん)なり
その間(あいだ)
をりをりのたがひめ
おのづからみじかき運をさとりぬ
すなはち
五十(いそじ)の春を迎(むか)へて
家を出(い)で
世を背(そむ)けり
もとより妻子(さいし)なければ
捨てがたきよすがもなし
身に官禄(かんろく)あらず
何につけてか執(しゅう)をとどめん
むなしく
大原山(おおはらやま)の雲にふして
また
五(いつ)かへりの
春秋(はるあき)をなん
経(へ)にける
私の身の上、父方(ちちかた)の祖母の家を受け伝えて、久しくそこに住んでいた。
その後、縁(えん)も切れ、私の身の上も衰微(すいび)し、忘れ得ぬ思い出も多々あったが、ついにそこでの暮らしが立ちゆかなくなり、三十余りの歳(とし)になって後
新たにわが心のままに、一軒(いっけん)の小さな家を構(かま)えた。
この家を元の住まいに比(くら)べると、わずかに十分の一の広さである。ただ寝起きするだけの粗末(そまつ)な家であって、整った屋敷(やしき)構えとするまではいかなかった。
なんとか土塀(どべい)は築(きず)いたけれど、門まで建てる余裕(よゆう)はなかった。竹を柱として粗末(そまつ)な車寄せをこしらえたが、雪が降ったり、風が吹いたりするたびに、危(あや)うく心もとない。
住まいは賀茂(かも)の河原の近くなので、水難(すいなん)の不安、盗難(とうなん)の恐れもある。
総(そう)じてままならぬこの世を、耐(た)えて過ごして心労(しんろう)すること、三十余年(よねん)である。その間、おりおり蹉跌(さてつ)に遭(あ)ったが、自然と己(おのれ)の人生の不運を悟(さと)った。
そうしてすぐ、五十歳の春を迎(むか)えて、出家(しゅっけ)し、遁世(とんせい)してしまったのだ。
もとより妻子(さいし)はいないので、世を捨て難(がた)い絆(きずな)もない。
官位(かんい)も俸禄(ほうろく)もないので、格別(かくべつ)思い残すことは、何もない。
こうして私は、何らなすところなく、大原(おおはら)山の雲の下に暮(く)らし、またも五度(たび)の春秋(はるあき)を過ごしたのである。
・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その一
ここに六十(むそじ)の露
消えがたに及びて
さらに末葉(すえは)の宿りを結べることあり
いはば旅人の一夜の宿をつくり
老いたる蚕(かいこ)の繭(まゆ)を営むがごとし
これを中ごろの栖(すみか)にならぶれば
また百分(ひゃくぶ)が一に及ばず
とかくいふほどに
齢(よわい)は歳々(さいさい)にたかく
栖(すみか)はをりをりにせばし
その家のありさま
よのつねにも似ず
広さはわづかに方丈
高さは七尺がうちなり
所を思ひ定めざるがゆゑ(え)に
地を占(し)めてつくらず
土居(つちい)を組み
うちおほひを葺(ふ)きて
継ぎ目ごとにかけがねを掛けたり
もし心にかなはぬことあらば
やすく外(ほか)へ移さむがためなり
そのあらため作ること
いくばくのわづらひかある
積むところわづかにニ両
車の力を報(むく)ふほかには
他の用途(ようと)いらず
ここに六十歳という、命のはかなく消え入ろうという際(きわ)に至(いた)り、新たに余生(よせい)を送るための住まいを構(かま)えることになった。例えるならば、旅人が一晩(ひとばん)の宿をもうけるようなものだ。老いた蚕(かいこ)が繭(まゆ)を作るようなものだ。
この庵(いおり)、かつて賀茂(かも)の河原に建てた家と比べれば、百分の一にも及(およ)ばない。あれこれ言っているうちに、齢(よわい)は年ごとに重なり、住まいは次第に狭(せま)くなっていった。
この庵のありさまは、世間一般のものとはまるで違う。広さはわずかに一丈(いちじょう)四方(しほう)、高さは
七尺にも達(たっ)しない。庵を構える場所は、ここと思い定めたわけではなかったので、土地を所有してこれを建てたわけではない。土台を組み、屋根を葺(ふ)き、木材の継(つ)ぎ目には鎹(かすがい)をかけただけである。
もし、自分の思いにかなわないとなれば、簡便(かんべん)に他所(よそ)へ移し運ぶことができる。再び建て直したところで、いくらも手数はかからない。車に積んでも、わずかにニ両分。労賃(ろうちん)を払う以外に、他に費用はかからない。
・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その二
いま
日野山(ひのやま)の奥に
跡(あと)をかくしてのち
東に三尺余(あまり)の庇(ひさし)をさして
柴折りくぶるよすがとす
南
竹の簀子(すのこ)を敷(し)き
その西に閼伽棚(あかだな)をつくり
北によせて障子をへだてて
阿弥陀(あみだ)の絵象(えぞう)を安置し
そばに普賢(ふげん)をかき
まへに法花経(ほけきょう)をおけり
東のきはに蕨(わらび)のほどろを敷(し)きて
夜の床(ゆか)とす
西南(にしみなみ)に
竹の吊棚(つりだな)を構へて
黒き皮籠(かわご)三合をおけり
すなはち
和歌
管弦(かんげん)
往生要集(おうじょうようしゅう)ごときの抄物(しょうもつ)を入れたり
かたはらに琴
琵琶(びわ)
おのおの一張(いっちょう)をたついはゆる
をり琴
つぎ琵琶
これなり
仮りの庵のありやう
かくのごとし
いま、日野山(ひのやま)の奥に身を潜(ひそ)め暮らすようになって、庵(いおり)の外、東側には三尺余りの
庇(ひさし)を差し出し、その下に薪(たきぎ)を燃やす
竈(かまど)を作った。
南側には竹の簀(すのこ)で縁(えん)を張り、その西側には閼伽棚(あかだな)を設(もう)け、庵の中、西側の
北に寄せて衝立(ついたて)を立て、内(うち)に阿弥陀如来(あみだにょらい)の絵像(えぞう)を安置し、そばに普賢菩薩(ふげんぼさつ)の絵像を描(か)いて掛(か)け添(そ)え、その前に法華経(ほけきょう)を置いた。
東の端(はし)には蕨(わらび)の穂(ほ)を敷(し)きつめ、夜の寝床(ねどこ)とした。西南(せいなん)の方(かた)には竹の吊(つ)り棚(だな)を据(す)え付け
黒い皮籠(かわかご)を三箱(みはこ)置いた。中に
和歌、管絃(かんげん)に関する書、往生要集(おうじょうようしゅう)といった写本(しゃほん)などを収めておいたものだ。
そばに琴(こと)、琵琶(びわ)、それぞれ一張(いっちょう)ずつを立て掛(か)けてある。折琴(おりごと)、
継琵琶(つぎびわ)という、場所を取らない組み立て式のものがそれである。
私の仮(かり)の住まいの有り様(よう)は、ざっと
このような具合である。
・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その三
その所のさまを
いはば南に懸樋(かけい)にあり
岩を立てて
水を溜(た)めたり
林の木ちかければ
爪木(つまぎ)をひろふに乏(とぼ)しからず
名を外山(とやま)といふ
まさきのかづら
跡(あと)埋(う)めり
谷しげけれど
西晴れたり
観念(かんねん)のたより
なきにしもあらず
春は藤波(ふじなみ)を見る
紫雲(しうん)のごとくして
西方(にしかた)に匂(にお)う
夏は郭公(ほととぎす)を聞く
語らふごとに
死出(しで)の山路(やまじ)を契(ちぎ)る
秋はひぐらしの声
耳に満てり
うつせみの世をかなしむほど聞こゆ
冬は雪をもてあはれぶ
つもり消ゆるさま
罪障にたとへつべし
もし念仏ものうく
読経(どきょう)まめならぬ時は
みづから休み
身づからおこたる
さまたぐる人もなく
また 恥(は)づべき人もなし
ことさらに無言をせざれども
独(ひと)りをれば
口業(くごう)を修めつべし
必ず禁戒(きんかい)を
守るとしもなくとも
境界(きょうがい)なければ
何につけてか破らん
もし
あとの白波に
この身を寄する朝(あした)には
岡の屋にゆきかふ船をながめて
満沙弥(まんしゃみ)が風情を盗み
もし
桂(かつら)の風
葉を鳴らす夕(ゆうべ)には
潯陽(じんよう)の江(え)を思ひやりて
源都督(げんととく)のおこなひをならふ
もし
余興(よきょう)あれば
しばしば松のひびきに
秋風楽(しゅうふうらく)をたぐへ
水のおとに
流泉(りゅうせん)の曲をあやつる
芸はこれつたなけれども
人の耳をよろこばしめむとにはあらず
ひとりしらべ
ひとり詠(えい)じて
みづから情(こころ)をやしなふばかりなり
庵(いおり)の外の有りようと言えば、南には懸樋(かけひ)があり、岩を配置し、そこに水を溜(た)めてある。林の中の庵なので、薪(たきぎ)に困ることはない。
この山は外山(とやま)と呼び、正木(まさき)の葛(かずら)が小道を覆(おお)いつくしている。谷は緑深く
、木々が茂(しげ)っているが、西に向かって開けているので、陽(ひ)の沈むさまを見つめつつ、西方浄土(さいほうじょうど)に思いを馳(は)せる便宜(べんぎ)がないわけではない。
春には一面の藤(ふじ)の花房(はなぶさ)が見られ、紫雲(しうん)のように西方(さいほう)に咲き匂(にお)う。
夏は郭公(ほととぎす)の声を聞き、死出(しで)の山路(やまじ)の道案内を頼(たの)む。
秋には蜩(ひぐらし)の声が耳に満ち溢(あふ)れ、その声は、儚(はかな)いこの世を嘆(なげ)くかのように耳に響(ひび)き、こだまする。
冬には降り積む雪を眺(なが)めては、しみじみと感慨(かんがい)に耽(ふけ)る。降っては消え、降っては消えする雪の有りようは、人間の罪障(ざいしょう)に喩(たと)えることもできるだろう。
もし、念仏(ねんぶつ)が大儀(たいぎ)で、読経(どきょう)に専心(せんしん)できぬときは、意に従(したが)って休み、怠(おこた)ればよい。それを妨(さまた)げる人もなければ、それを恥(は)じる相手さえもいない。
ことさら無言の行(ぎょう)をせずとも、自(おの)ずから口業(くごう)を負(お)わずに済(す)む。
仏の禁戒(きんかい)を守ろうと、あえて努めずとも、この境界(きょうがい)では、禁戒を破(やぶ)ろうにも、はじめから破りようがない。
もし、漕(こ)ぎ行く船の残す儚(はかな)い白波(しらなみ)にわが身を思い重ねる朝には、宇治川はるか岡(おか)の屋(や)に行き交う船を眺(なが)め、万葉の詩人
満沙弥(まんしゃみ)の情趣(じょうしゅ)にあやかって、歌を詠(よ)む。
もし、桂(かつら)の葉を風が鳴らす夕べには、唐の詩人
白楽天(はくらくてん)の潯陽江(じんようこう)の故事(こじ)に思いやり、源都督(げんととく)のように、その風雅(ふうが)を真似(まね)て、琵琶を奏(かな)でる。
もし、なお興(きょう)に乗ることあれば、折(おり)にふれ、松風(まつかぜ)の音に誘(さそ)われて秋風楽(しゅうふうらく)を奏(かな)でる。水のせせらぎに合わせ、流泉(りゅうせん)をも。
拙(つたな)い私の技芸(ぎげい)であるが、元来(がんらい)聞く人の耳を楽しませようとは思っていない。一人で奏(かな)で、一人で歌を歌い、一人心を慰(なぐさ)み、一人楽しんでいるだけだから。
・方丈の庵(ほうじょうのいおり) その四
また
ふもとに一つの柴の庵(いおり)あり
すなはち
この山守(やまもり)がをる所なり
かしこに小童(こわらわ)あり
ときどき来たりてあひとぶらふ
もし
つれづれなる時には
これを友として遊行(ゆぎょう)す
かれは十歳(ととせ)
これは六十(むそじ)
そのよはひ
ことのほかなれど
心をなぐさむること
これ同じ
或(ある)は茅花(つばな)を抜き
岩梨(いわなし)をとり
零余子(ぬかご)をもり
芹(せり)をつむ
或(ある)は
すそわの田居(たい)にいたりて
落穂(おちぼ)を拾(ひろ)ひて
穂組(ほぐみ)をつくる
もし
うららかなれば
峰(みね)によぢのぼりて
はるかにふるさとの空をのぞみ
木幡山(こはたやま)
伏見(ふしみ)の里
鳥羽(とば)
羽束師(はつかし)を見る
勝地(しょうち)は主なければ
心をなぐさむるにさはりなし
歩みわづらひなく
心遠くいたるときは
これより峰つづき
炭山(すみやま)をこえ
笠取(かさとり)を過ぎて
或(ある)は石間(いわま)にまうで
かつは家づととす
或(ある)は石山ををがむ
もしはまた粟津(あわず)の原を分けつつ
蝉歌(せみうた)の翁(おきな)があとをとぶらひ
田上河(たなかみがわ)をわたりて
猿丸太夫(さるまるもうちぎみ)が墓をたづぬ
かへるさには
をりにつけつつ桜を狩り
紅葉(もみじ)をもとめ
わらびを折り
木(こ)の実をひろひて
かつは仏にたてまつり
もし
夜しづかなれば
窓の月に故人(こじん)をしのび
猿のこゑ(え)に袖(そで)をうるほす
くさむらの蛍(ほたる)は遠く
まきの島のかがり火にまがひ
暁(あかつき)の雨は
おのづから木の葉吹くあらしに似たり
山鳥のほろほろと鳴くを聞きても
父か母かとうたがひ
峰の鹿(かせぎ)の近く馴(な)れたるにつけても
世に遠ざかるほどを知る
或(ある)はまた
埋(うず)み火をかきおこして
老いの寝覚めの友とす
おそろしき山ならねば
梟(ふくろう)の声をあはれむにつけても
山中(やまなか)の景気
折りにつけて尽(つ)くることなしいはむや
深く思ひ
深く知らむ人のためには
これにしも限るべからず
また、この山のふもとに粗末(そまつ)な一軒(いっけん)の庵(いおり)があり、山番(やまばん)が住まう。
そこに一人の男の子がおり、ときどき私を訪(たず)ねてくれる。もし、格別(かくべつ)用事もないときは、その子を相手に遊んで過ごす。彼は十歳、私は六十歳。齢(よわい)の隔(へだ)たりこそ大きいが、心慰(なぐさ)む思いは互いに同じだ。
またあるときは、茅(ちがや)の花を抜(ぬ)き、苔桃(こけもも)を採(と)り、ぬかごを盛(も)り採り、芹(せり)を摘(つ)む。
あるときは、山裾(やますそ)辺(あた)りの田圃(たんぼ)に行って、落穂(おちぼ)を拾(ひろ)っては、穂組(ほぐみ)を真似(まね)て作ってみたり。
もし、のどかに晴れた日には、峰(みね)によじ登り、はるかに故郷(ふるさと)の空を望み、木幡山(こはたやま)、伏見(ふしみ)の里、鳥羽(とば)、羽束師(はつかし)を見晴るかす。勝地(しょうち)は誰(だれ)のものでもないから、気兼(きが)ねなどせずに、存分(ぞんぶん)に楽しめばよい。
足が軽く、遠地(えんち)にまで心馳(は)せるときには、ここから峰を伝い、炭山(すみやま)を越(こ)え、
笠取山(かさとりやま)を通り、あるときは、岩間寺(いわまでら)、またあるときは石山寺(いしやまでら)を
参詣(さんけい)する。
もしくは、粟津(あわづ)の原に分け行って、琵琶(びわ)奏者(そうしゃ)、蝉丸(せみまる)縁(ゆかり)の地を訪(たず)ね、田上川(たがみがわ)を渡(わた)り、歌人(かじん)、猿丸太夫(さるまるだゆう)の
墓(はか)に参る。
帰途(きと)には、季節の折り折り桜を見たり、紅葉(もみじ)を求めたり、蕨(わらび)を折り取り、木(こ)の実を拾(ひろ)い集め、仏様に供(そな)えたり、家への土産(みやげ)とする。
もし、夜が静かならば、窓から望む月を見て、旧友(きゅうゆう)を偲(しの)び、猿(さる)の悲しげな声に心を寄せ、袖(そで)を涙(なみだ)で濡(ぬ)らす。草むらの蛍(ほたる)は、遠く槇島(まきのしま)のかがり火に見まがい、暁(あかつき)に降る雨の音は、木の葉をざわめかす嵐(あらし)の響(ひび)きのようだ。
山鳥のほろほろと鳴く声を聞けば、生まれ変わった私の父や母が会いに来てくれたのかしらと疑(うたが)い、峰に住む鹿(しか)が人に近寄り、恐(おそ)れずにいるのを見るにつけても、今の私の世俗(せぞく)から隔(へだ)てた暮らしぶりが、わかるというものだ。
眠(ねむ)りが途切(とぎ)れがちな老いた私だから、ときには炭火(すみび)をかき起こして、その火とともに夜を過ごすこともある。
恐ろしいほど山深い山というわけではないから、梟(ふくろう)の声をしみじみと聞けるにつけても、山中(さんちゅう)の情趣(じょうしゅ)は、四季折々(おりおり)尽(つ)きることはない。ましてや、私などより深くものを思い、くものを知る人ならば、山中の自然の興趣(きょうしゅ)を、私以上に感じ得たにちがいない。
・閑居の気味(かんきょのきび) その一
おほかた
この所に住みはじめし時は
あからさまと思ひしかども
今すでに五年(いつとせ)を経(へ)たり
仮りの庵(いおり)もややふるさととなりて
軒(のき)に朽(く)ち葉ふかく
土居(つちい)に苔(こけ)むせり
おのづからことの便りに都を聞けば
この山にこもりゐてのち
やむごとなき人のかくれたまへるもあまた聞こゆ
ましてその数ならぬたぐひ
尽くしてこれを知るべからず
たびたびの炎上(えんじょう)にほろびたる家
またいくそばくぞ
ただ仮の庵(いおり)のみ
のどけくしておそれなし
程(ほど)せばしといへども
夜臥(ふ)す床(ゆか)あり
昼ゐ(い)る座(ざ)あり
一身(いっしん)をやどすに不足なし
かむなは小さき貝を好む
これ身知れるによりてなり
みさごは荒磯(あらいそ)にゐる
すなはち
人をおそるるがゆゑなり
われまたかくのごとし
身を知り世を知れれば
願はずわしらず
ただしづかなるを望みとし
憂(うれ)へなきをたのしみとす
すべて
世の人のすみかをつくるならひ
必ずしも身のためにせず
或(ある)は妻子(さいし)
眷属(けんぞく)のためにつくり
或(ある)は親昵(しんじつ)
朋友(ほうゆう)のためにつくる
或(ある)は主君
師匠(ししょう)および財宝
牛馬(ぎゅうば)のためにさへ
これをつくる
われ
今
身のためにむすべり
人のためにつくらず
ゆゑいかんとなれば
今の世のならひ
この身のありさま
ともなふべき人もなく
たのむべき奴(やっこ)もなしたとひ
ひろくつくれりとも
誰(たれ)を宿し
誰をか据(す)ゑん
そもそも、この外山(とやま)に住まいを定めた当初(とうしょ)は、ほんの暫(しばら)く住もうというほどにしか思わなかったが、すでに五年の年月が経(た)った。
この庵(いおり)も、そこそこ住み慣(な)れた古家(ふるや)となって、屋根は厚(あつ)く枯葉(かれは)を積(つ)み、土台には苔(こけ)が生(む)している。
何とはなしに都の様子を耳にすれば、私がこの山にこもって後(のち)お亡(な)くなりになった高貴(こうき)な方が、数多くいらしたということだ。まして、平俗(へいぞく)な者たちの死んだ数となれば、数え切れるものではなかろう。度重(たびかさ)なる火災(かさい)のために焼失(しょうしつ)した家々の数もまた、どれほどあったろう。
ただ、この仮(かり)の庵(いおり)のみは、平穏(へいおん)で、無事であった。住まいは狭(せま)くとも、夜寝るだけの床(ゆか)はあり、昼座(すわ)れる場所もある。我(わ)が身一つを置くうえで、何の不自由もない。
やどかりは、小さな貝を選んで住む。身の程(ほど)を弁(わきま)えているからだ。みさごは、荒磯(あらいそ)に住む。人を恐れるが故(ゆえ)だ。私もまた、それらと同じことだ。身の程(ほど)を知り、また、世間を知る者として、欲(よく)を抱(いだ)かず、齷齪(あくせく)することもない。ただ平安であることを望み、憂(うれ)いごとのない暮らしを楽しみとしている。
総(そう)じて、世間の人々が住家(すみか)を作るのは、必ずしも我が身だけのためではない。ある時は妻子(さいし)一族(いちぞく)のため、ある時は近親者(きんしんしゃ)、友のために作る。あるいは、主人、師匠(ししょう)のため。財産(ざいさん)、牛馬(ぎゅうば)のためにさえ作ることもあろう。
しかし私は、今、我が身ただ一人のためにこそ、この庵を結んだ。誰(だれ)のためでもない。その訳(わけ)は、今ある私のこの境遇(きょうぐう)である。連れ添(そ)う相手もなく、頼(たよ)りとする従者(じゅうしゃ)もない。たとえ住家(すみか)を広く作るにしても、そこに一体(いったい)誰(だれ)を住まわせられようか。
・閑居の気味(かんきょのきび) その二
それ
人の友とあるものは富めるをたふとみ
ねむごろなるを先とす
必ずしも
なさけあるとすなほなるとをば愛せず
ただ糸竹(しちく)
花月(かげつ)を友とせんにはしかじ
人の奴(やっこ)たるものは
賞罰(しょうばつ)はなはだしく
恩顧(おんこ)あつきをさきとす
さらに
はぐくみあはれむと
安くしづかなるとをば願はず
ただ
わが身を奴婢(ぬひ)とするにはしかず
いかが奴婢とするとならば
もし
なすべきことあれば
すなはち
おのが身をつかふ
たゆからずしもあらねど
人をしたがへ
人をかへりみるよりやすし
もし
ありくべきことあれば
みづからあゆむ
苦しといへども
馬 鞍(くら) 牛 車と
心を悩ますにはしかず
今
一身(いっしん)をわかちて
二つの用をなす
手の奴(やっこ)
足の乗りもの
よくわが心にかなへり
心
身の苦しみを知れれば
苦しむ時は休めつ
まめなれば使ふ
使ふとても
たびたび過ぐさず
もの憂(う)しとても
心を動かすことなし
いかにいはむや
つねにありき
つねに働くは
養性(ようじょう)なるべし
なんぞいたづらに
休みをらん
人を悩(なや)ます
罪業(ざいごう)なり
いかが他の力を借るべき
衣食のたぐひ
またおなじ
藤の衣(ころも) 麻のふすま
得るにしたがひて
肌(はだへ)をかくし
野辺(のべ)のおはぎ
峰(みね)の木(こ)の実
わづかに命をつぐばかりなり
人にまじはらざれば
すがたを恥(は)ずる悔(く)いもなし
糧(かて)ともしければ
おろそかなる報(むく)いをあまくす
すべて
かやうの楽しみ
富める人に対していふにはあらず
ただわが身ひとつにとりて
むかし今とをなぞらふるばかりなり
さて、そもそも友としての人の関係には、相手の富裕(ふゆう)が尊(たっと)ばれ、(たが)いに配慮(はいりょ)し合う、懇(ねんご)ろな付き合いに重きが置かれる。必ずしも情の厚(あつ)い者、率直(そっちょく)な者が大事にされるわけではない。そんな友をもつくらいなら、音楽や自然を友とし、愛するほうが、よほどよい。
従者(じゅうしゃ)というものは、賞与(しょうよ)の多く、何かと心づけを忘れない主人を尊(たっと)ぶ。真心(まごころ)をもって、情愛深く、大事に扱(あつか)われること、暮らしの心安らかな静けさなどは、念頭(ねんとう)になどない。
このような者を従(したが)えるくらいなら、我(わ)が身を従者としたほうがよほどましだ。我が身が私の従者であったなら、なすべきことは、ただちに己(おのれ)の身体(からだ)を使ってなせばよい。面倒(めんどう)がないわけではないが、他人を指図(さしず)し、他人を世話(せわ)する気遣(づか)いが不要だ。
もし、外出する用事があれば、自分の足で歩けばよい。苦しくもあろうが、馬、鞍(くら)だ、牛、車だと、心労(しんろう)するのに比べれば、よほどましというものだ今、私は、一つの我が身に、二つの仕事をさせている。私の手は、私の従者であり、私の足は、私の車である。どちらも、私の意のままに働く。
私の心は、私の身体の辛(つら)さを知っているから、辛いときには身体を休め、達者(たっしゃ)であれば、体を使う。使うと言っても、度を越(こ)しはしない。気が乗らず、怠(なま)けたとしても、心懸(こころが)かりなどない。そもそも、常(つね)に歩き、常に動くことは、いちばんの養生(ようじょう)となろう。むやみに休んでばかりもおられようか。
他人を使い、苦労を強(し)いる行為(こうい)も、人間の罪障(ざいしょう)となろう。他人の力を借りず、自分で自分の世話をすることだ。
衣食(いしょく)についても同じことだ。葛(くず)の織物(おりもの)、麻(あさ)布の夜具(やぐ)を手に入るままに身にまとい、身を包(つつ)めばよい。野原のよめな、山の木(こ)の実を食(しょく)せば、わずかでも命をつなぐ糧(かて)となる。
人との交(まじ)わりがないので、粗末(そまつ)なその姿(すがた)を、恥(は)じて悔(く)いることもない。
乏(とぼ)しい糧(かて)は、却(かえ)って粗末な頂(いただ)きものをうまく味わえる。
すべて、このように述べ立てた私の暮らしの楽しみは、富裕(ふゆう)な者への嫌味(いやみ)ではない。ただ、この楽しみを知り得なかったかつての我が身の上と、今の身の上とを比べて、素直(すなお)な私の感慨(かんがい)を述(の)べたに過(す)ぎない。
・閑居の気味(かんきょのきび) その三
それ
三界(さんがい)は
ただ心ひとつなり
もし
やすからずは
象馬(ぞうめ) 七珍(しっちん)もよしなく
宮殿 楼閣(ろうかく)も望みなし
今
さびしきすまひ
一間(ひとま)の庵(いおり)
みづからこれを愛す
おのづから
都に出(い)でて
身の乞がいとなれることを恥(は)づといへども
帰りてここにをる時は
他の俗塵(ぞくじん)に馳(は)することをあはれむ
もし
人このいへることを疑はば
魚(いお)と鳥とのありさまを見よ
魚は水に飽(あ)かず
魚にあらざればその心を知らず
鳥は林をねがふ
鳥にあらざればその心を知らず
閑居(かんきょ)の気味(きび)もまたおなじ
住まずして誰かさとらむ
そもそも、この世の中というものは、自分の心の有りよう次第(しだい)でどのようにも変わるものだ。
心乱れ、落ち着かずに生きているならば、どれだけ貴重(きちょう)な財産(ざいさん)であれ、何の値打(ねう)ちも見出せないだろう。どれだけ立派(りっぱ)な御殿(ごてん)、楼台(ろうだい)に住み暮らそうが、先々(さぎざき)への望みを抱(いだ)くことも出来ない。
しかし、私は今、閑寂(かんじゃく)な日野の、わずか一間(ひとま)の粗末な庵(いおり)に暮らしながら、これに非常な愛着(あいちゃく)を抱いている。
ときに都へ赴(おもむ)けば、乞食(こじき)同然のみすぼらしい己(おのれ)の姿(すがた)を恥(は)じて感ずることもあるが、日野の庵に戻(もど)ってみれば、世の人の、俗欲(ぞくよく)にあくせくして暮らす様を、却(かえ)って気の毒(どく)にと思う。
もし、人が私のこの言葉をお疑(うたが)いならば、魚と
鳥との有りさまをご覧(らん)なさい。魚は水の中に暮らして飽(あ)きないが、魚でなければその心は理解出来まい。鳥は林の中の暮らしを望むが、鳥でなければその心は実感出来まい。
世俗(せぞく)から離(はな)れ、静かに暮らす、しみじみとしたこの味わいも、また同じことだ。味わってもみずに、わかろうはずがない。
・早暁の思策(そうぎょうのしさく)
そもそも
一期(いちご)の月影(つきかげ)かたぶきて
余算(よさん) 山の端(は)に近し
たちまちに
三途(さんず)の闇(やみ)に向かはんとす
何のわざをかかこむとする
仏の教へたまふおもむきは
ことにふれて
執心(しゅうしん)なかれとなり
今
草庵(そうあん)を愛するもとがとす
閑寂(かんせき)に著(じゃく)するも
さはりなるべし
いかが要なき楽しみを述べて
あたら時を過ぐさむ
しづかなる暁(あかつき)
このことわりを思ひつづけて
みづから心に問ひていはく
世をのがれて
山林にまじはるは
心を修めて道を行はむとなり
しかるを
汝(なんじ)すがたは聖人(ひじり)にて
心は濁(にごり)に染めり
栖(すみか)は
すなはち浄名居士(じょうみょうこじ)の跡を
けがせりといへども
保つところは
わづかに周利槃特(しゅうりはんどく)が行ひにだに
及ばず
もしこれ
貧賎(ひんせん)の報(むくい)の
みづからなやますか
はたまた
妄心(もうしん)のいたりて
狂(きょう)せるか
そのとき
心
さらに答ふることなし
ただかたはらに
舌根(ぜっこん)をやとひて
不請(ふしょう)の阿弥陀仏(あみだぶつ)
両三編(りょうさんべん)申して
やみぬ
時に
建暦(けんりゃく)の
二年(ふたとせ)三月(やよい)のつごもりごろ
桑門(そうもん)の連胤(れんいん)
外山(とやま)の庵(いおり)にして
これをしるす
さて、山の端(は)近くに傾(かたむ)いた月のように、私の生涯(しょうがい)もいよいよ余命(よめい)わずかとなった。もう間もなく、私の命も三途(さんず)の闇(やみ)にと向かっていくことだろう。
この期(ご)に及(およ)び、今さら何を私は嘆(なげ)こうとしているのだ。仏の諭(さと)し示されたその趣意(しゅい)は、執心(しゅうしん)なかれということだ。
私の、この庵(いおり)と、静かな暮らしへの愛着(あいじゃく)は、罪業(ざいごう)となり、往生(おうじょう)の妨(さまた)げとなろう。仏道(ぶつどう)を悟(さと)る道において、何の役にも立たない、閑居(かんきょ)の暮らしの私の楽しみについて、これ以上述べ立てて何になろう。
静かな、早暁(そうぎょう)、この道理(どうり)について、私は考え巡(めぐ)らし、自(みずか)らの心にこう問(と)うてみた。
俗世(ぞくせ)を逃(のが)れ、山林に隠(かく)れ暮らした目的は、心を修(おさ)め、仏道を修行(しゅぎょう)せんがためだった。しかるに、お前は、姿(すがた)こそは僧(そう)でありつつ、心は濁(にご)りに染(そ)まっている。栖家(すみか)もまた、維摩羅詰(ゆいまらきつ)の方丈(ほうじょう)の庵(いおり)にあやかり、真似(まね)たが、生きる有りようは、惰(たいだ)な仏弟子(ぶつでし)、周利槃特(しゅりはんどく)にさえ及(およ)ばない。
もしや、これは前世(ぜんせ)の罪業(ざいごう)、貧賎(ひんせん)の報(むく)いにあって、私は、迷(まよ)い、心労(しんろう)するのか。はたまた、みだらな俗念(ぞくねん)が、私の心の奥深くに入り込み、狂(くる)わせてしまっているのか。
この問いかけに、私の心は、何も答えてくれようとはしない。
ただ、その時、私の心は、罪を為(な)せる私自身の舌(した)を使わせて、本意(ほんい)からでもない念仏(ねんぶつ)を、南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と、そっとニ三度、私に唱(とな)えさせただけだった。
時に、建暦(けんりゃく)二年三月末(すえ)のころ、出家僧(しゅっけそう)、連胤(れんいん)、外山(とやま)の庵にて、これを記(しる)す。
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。