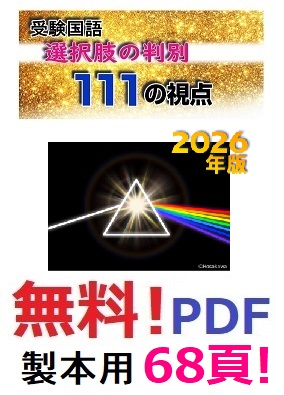中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
- ■短歌(通釈):あ~さ行(105首)
- ■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
- 論理パズル
- 各種論理
- ■所収歌 作者の略歴(五十音順)
- ■所収歌 関連用語
- ■あ行
- あをによし 奈良の都は 咲く花の にほふがごとく 今さかりなり(小野老)
- 赤とんぼ 早く現はれ 捕りて食へ 昼を来てさす このやぶ蚊ども(窪田空穂)
- 秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる(藤原敏行)
- あけて待つ 子の口のなか やはらかし 粥運ぶ 我が匙に触れつつ(五島美代子)
- 朝あけて 船より鳴れる 太笛の こだまは長し 並みよろふ山(斎藤茂吉)
- あさぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪(坂上是則)
- あしひきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む(よみ人知らず)
- あたらしく 冬きたりけり 鞭のごと 幹ひびき合ひ 竹群はあり(宮柊ニ)
- あますなく 小草は枯れて 風に鳴る かなたに小さき 山の中学(木俣修)
- 天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ(僧正遍照=良岑宗貞)
- 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも(阿倍仲麻呂)
- 天地に われ一人ゐて 立つごとき この寂しさを 君はほほゑむ(会津八一)
- 雨に濡れし 夜汽車の窓に 映りたる 山間の町の ともしびの色(石川啄木)
- 淡路島 かよう千鳥の 鳴く声に いくよねざめぬ 須磨の関守(源兼昌)
- 家にあれば 笥もる飯を 草まくら 旅にしあれば 椎の葉にもる(有馬皇子)
- いかるがの さとのをとめは よもすがら きぬはたおれり あきちかみかも(会津八一)
- 幾山河 こえさりゆかば さみしさの はてなん国ぞ きょうも旅ゆく(若山牧水)
- 石がけに 子ども七人 こしかけて 河豚を釣りをり 夕焼け小焼け(北原白秋)
- 石をもて 追わるるごとく ふるさとを 出でしかなしみ 消ゆる時なし(石川啄木)
- いづくにか しるしの糸は つけぬらむ 年々来鳴く つばくらめかな(樋口一葉)
- いちはつの 花咲きいでて 我が目には 今年ばかりの 春行かんとす(正岡子規)
- いついつと 待ちしさくらの 咲き出でて いまはさかりか 風吹けど散らず(若山牧水)
- いつしかに 春の名残と なりにけり 昆布干場の たんぽぽの花(北原白秋)
- 一疋が さきだちぬれば 一列に つづきて遊ぶ 鮒の子の群(若山牧水)
- いつもより 一分早く 駅に着く 一分 君のこと考える(俵万智)
- 稲刈りて さびしく晴るる 秋の野に 黄菊はあまた 目を開きたり(長塚節)
- いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指の間より落つ(石川啄木)
- 妹の 小さき歩み いそがせて 千代紙買いに 行く月夜かな(木下利玄)
- 石ばしる 垂水の上の さわらびの もえいずる春に なりにけるかも(志貴皇子)
- うすべにに 葉はいちはやく 萌えいでて 咲かんとすなり 山桜花(若山牧水)
- 馬追虫の ひげのそよろに 来る秋は まなこを閉ぢて 想ひ見るべし(長塚節)
- 海恋し 潮の遠鳴り 数えては 少女となりし 父母の家(与謝野晶子)
- うらうらに 照れる春日に 雲雀あがり 情悲しも 独りし思へば(大伴家持)
- 瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば ましてしぬばゆ いずくより 来たりしものぞ 眼交に もとなかかりて 安寝しなさぬ(山上憶良)
- 遠足の 小学生徒 うちょうてんに 大手ふりふり 往来とほる(木下利玄)
- 近江の海 夕浪千鳥 汝が鳴けば 情もしのに 古思ほゆ(柿本人麻呂)
- 大海の 磯もとどろに 寄する波 割れてくだけて さけて散るかも(源実朝)
- 大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立(小式部内侍)
- 奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき(よみ人知らず)
- 憶良らは 今はまからむ 子なくらむ それその母も 吾を待つらむぞ(山上憶良)
- 幼きは 幼きどちの ものがたり 葡萄のかげに 月かたぶきぬ(佐々木信綱)
- おとうさまと書き添へて 肖像画の貼られあり 何という吾が鼻のひらたさ(宮柊二)
- 思い出の一つのようで そのままにしておく 麦わら帽子のへこみ(俵万智)
- 親は子を 育ててきたと 言うけれど 勝手に赤い 畑のトマト(俵万智)
- おりたちて 今朝の寒さを おどろきぬ 露しとしとと 柿の落ち葉深く(伊藤左千夫)
- ■か行
- 帰り来ぬものを轢かれし子の靴をそろえ破れし服をつくろう(作者不詳)
- かがやける少年の目よ自転車を買い与へんと言ひしばかりに(作者不詳)
- かすみたつ長き春日をこどもらとてまりつきつつきょうもくらしつ(良寛)
- かにかくに渋民村は恋しかりおもいでの山おもいでの川(石川啄木)
- 瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり(正岡子規)
- 唐衣裾に取りつき泣く子らを置きてぞ来ぬや母なしにして(他田舎人大島)
- ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブリキの屋根に月うつる見ゆ(正岡子規)
- ガラス戸の外のつきよをながむれどランプのかげのうつりて見えず(正岡子規)
- 川ひとすぢ菜たね十里の宵月夜母が生まれし国美くしむ(与謝野晶子)
- 汽車の窓はるかに北にふるさとの山見え来れば襟を正すも(石川啄木)
- 君がため春の野にいでて若菜つむわが衣手に雪はふりつつ(光孝天皇)
- 今日までに私がついた嘘なんてどうでもいいよというような海(俵万智)
- 清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みな美しき(与謝野晶子)
- 清らなる山の水かも蟹とると石をおこせば水の流らふ(島木赤彦)
- 草の実のはぜ落つる音この谷のところどころに聞こえつつおり(斎藤茂吉)
- くさふめばくさにかくるるいしずゑのくつのはくしゃにひびくさびしさ(会津八一)
- 草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり(北原白秋)
- 葛の花踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり(釈迢空)
- 薬のむことを忘れて、ひさしぶりに、母にしかられしをうれしと思へる。(石川啄木)
- くれなゐのニ尺のびたる薔薇の芽の針やはらかに春雨の降る(正岡子規)
- 心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ(西行)
- こころよく我にはたらく仕事あれそれを仕遂げて死なむとぞ思ふ(石川啄木)
- 不来方のお城の草に寝ころろびて空に吸はれし十五の心(石川啄木)
- 子どもらと手まりつきつつこの里に遊ぶ春日は暮れずともよし(良寛)
- 子どもらは列をはみ出しわき見をしさざめきやめずひきいられ行く(木下利玄)
- この朝け霧おぼろなる木の影に日のけはいして鳥鳴きにけり(島木赤彦)
- この三朝あさなあさなをよそほひし睡蓮の花今朝は開かず(土屋文明)
- 駒とめて袖うち払うかげもなし佐野のわたりの雪の夕ぐれ(藤原定家)
- これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬもあふ坂の関(蝉丸)
- 金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に(与謝野晶子)
- ■さ行
- さくらさくらさくら咲き初め咲き終りなにもなかったような公園(俵万智)
- 桜ばないのち一ぱい咲くからに生命をかけてわが眺めたり(岡本かの子)
- さざなみや志賀の都はあれにしを昔ながらの山ざくらかな(平忠度)
- 寂しさはその色としもなかりけり真木立つ山の秋の夕ぐれ(寂連)
- 「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ(俵万智)
- 沢がにをもてあそぶ子に銭くれて赤きたなそこを我は見たり(釈迢空)
- 志賀の浦や遠ざかりゆく波間より氷りて出づる有明の月(藤原家隆)
- しきしまのやまと心を人とわば朝日ににほふ山ざくら花(本居宣長)
- しずかなる峠をのぼり来し時に月の光は八谷を照らす(斎藤茂吉)
- 自転車のカゴからわんとはみ出してなにか嬉しいセロリの葉っぱ(俵万智)
- 死というは日用品の中にありコンビニで買う香典袋(俵万智)
- 信濃路はいつ春にならん夕づく日入りてしまらく黄なる空の色(島木赤彦)
- 死に近き母に添寝しんしんと遠田のかわず天に聞こゆる(斎藤茂吉)
- しばらくを三間うちぬきて夜ごと夜ごと子らが遊ぶに家わきかへる(伊藤左千夫)
- 四万十に光の粒をまきながら川面をなでる風の手のひら(俵万智)
- 霜やけの小さき手してみかんむく我が子しのばゆ風の寒きに(落合直文)
- 白雲に羽うちかわしとぶ雁の数さえ見ゆる秋の夜の月(よみ人知らず)
- 白雲のうつるところに小波の動き初めたる朝のみづうみ(与謝野晶子)
- 白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ(若山牧水)
- 白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝はつめたき水くみにけり(長塚節)
- 銀も金も玉も何せんにまされる宝子にしかめやも(山上憶良)
- 水平線を見つめて立てる灯台の光りては消えてゆくもの思い(俵万智)
- 鈴鹿山うき世をよそに振りすてていかになり行くわが身なるらむ(西行)
- 鈴鳴らす橇にか乗らむいないな先づこの白雪を踏みてか行かむ(若山牧水)
- 戦争の話やめよと隣室の母するどければみな息ひそむ(作者不詳)
- 千メートル泳ぎ切りたる賞状を病気の父は笑みてうなずく(作者不詳)
- 袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ(紀貫之)
- そのかみの神童の名のかなしさよふるさとに来て泣くはそのこと(石川啄木)
- その子二十櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな(与謝野晶子)
- それとなく郷里のことなど語り出でて秋の夜に焼く餅のにほひかな(石川啄木)
- ■剽窃について
■短歌(通釈):あ~さ行(105首)
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。
■俳句・短歌(玄関):俳句・短歌の知識 ・季語一覧表 ・枕詞一覧表・旧暦 ・月の古称 ・いろは歌
【目次】
■所収歌 作者の略歴
■所収歌 関連用語
■短歌(通釈):あ~さ行(105首)※このページです!
■短歌(通釈):た~わ行(126首)
【無料PDF】■季語 一覧表(PDF) (B4・2枚)
■季語 写真集(PDF) (B4・3枚)
■枕詞 一覧表(PDF) (B4・1枚)
論理パズル
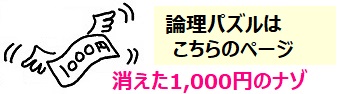
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
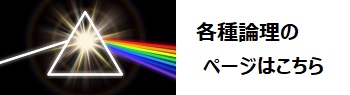
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
■所収歌 作者の略歴(五十音順)
■会津八一(あいづやいち)…大正、昭和の歌人、美術史家、書家。 明治14年(1881年)8月1日に生まれたことから八一(やいち)と名付けられた。
■阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)…716年、19歳で遣唐留学生に選ばれ、翌年、遣唐使に従って入唐したが、日本への帰国を果たせずに唐で没した。
■有馬皇子(ありまのみこ)…飛鳥時代の貴族。斉明天皇のとき、皇位継承をめぐる争いに巻き込まれ、謀反(むほん)を企てたとして処刑された。護送されるときの哀歌二首が「万葉集」に収められている。
■在原業平(ありわらのなりひら)…平安初期の貴族、歌人。六歌仙、三十六歌仙の一人。奔放(ほんぽう)多感な性格で、情熱的で詠嘆の強い和歌を残した。伊勢物語の主人公とされる。
■在原行平(ありわらのゆきひら)… 平安初期の歌人。在原業平(ありわらのなりひら)の兄。
■石川啄木(いしかわたくぼく)…本名は一(はじめ)。岩手県生まれ。率直で平明な口語的表現は歌壇に大きな影響を与えた。明治45年(1912年)、27歳で没。
■石川不二子(いしかわふじこ)… 昭和八年、神奈川県生まれ。東京農工大学農学部卒業後、高校教師に。のち、仲間とともに開拓地の農場に入植。農婦として自然と生活をのびやかに詠(うた)った作品を発表し続けた。
■伊藤左千夫(いとうさちお)…明治、大正時代の歌人、小説家。正岡子規の没後、『馬酔木(あしび)』、『アララギ』を主宰し、写生主義を主張した。著名な小説に『野菊の墓』がある。大正二年(1913年)、48歳で没。
■大江千里(おおえのちさと)…平安時代前期の貴族、歌人。中古三十六歌仙の一人。
■凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)…平安時代の歌人。紀貫之らとともに『古今和歌集』の撰者となった。三十六歌仙の一人。
■太田道灌(おおたどうかん)…室町時代後期の武将。江戸城を築城。
■大伴家持(おおとものやかもち)…奈良時代の歌人。大伴旅人(おおとものたびと)の子。『万葉集』の編纂に携わり、自身、これに最多の作品を残している。三十六歌仙の一人。
■岡本かの子(おかもとかのこ)…歌人、小説家、仏教研究家。子は芸術家の岡本太郎。昭和14年(1939年)、48歳で没。
■他田舎人大島(おさだのとねりおおしま)…奈良時代の防人(さきもり)。
■落合直文(おちあいなおぶみ)… 明治時代の歌人、国文学者。宮城県生まれ。
■尾上柴舟(おのえさいしゅう)…明治から昭和にかけての歌人、国文学者、書家。
■小野老(おののおゆ)… 奈良時代の貴族、歌人。
■小野小町(おののこまち)…平安時代の女流歌人。六歌仙の一人。
■柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)…飛鳥時代の歌人。三十六歌仙の一人。
■金子薫園(かねこくんえん)… 明治から昭和にかけての歌人。東京生まれ。
■北原白秋(きたはらはくしゅう)…大正から昭和にかけての歌人、詩人、童謡作家。
■木下利玄(きのしたりげん)…歌人。大正14年(1925年)、40歳で没。
■紀貫之(きのつらゆき)…平安前・中期の歌人。『古今和歌集』の編者の一人。三十六歌仙の一人。
■紀友則(きのとものり)…平安前・中期の歌人。『古今和歌集』の撰者の一人。三十六歌仙の一人。
■木俣修(きまたおさむ)…昭和期の歌人。
■清原深養父(きよはらのふかやぶ)… 清少納言の曾祖父(そうそふ)にあたる人。
■窪田空穂(くぼたうつぼ)…明治から昭和にかけての歌人、国文学者。
■光孝天皇(こうこうてんのう)…第58代天皇。歌人。
■小式部内侍(こしきぶのないし)…平安時代の女流歌人。女房三十六歌仙の一人。母は和泉式部(いずみしきぶ)。
■五島美代子(ごとうみよこ)…昭和期の歌人。
■後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)…第82代天皇。歌人。承久(じょうきゅう)の乱によって隠岐(おき)の島にて崩御(ほうぎょ)。
■西行(さいぎょう)… 平安末期、鎌倉初期の歌人で、僧。もと、北面(ほくめん:院警護)の武士。二十三歳で出家後、自然を友とする諸国の旅を続け、自己の内面を平明、自在に詠(うた)い、後世に大きな影響を与えた。『新古今和歌集』には94首と最も多く収められている。西行の逸話(いつわ)に次のようなものがある。源頼朝が鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)に参詣(さんけい)した折(おり)、道端(みちばた)にかしこまっている老法師(ろろうほうし)の人品(じんぴん)を見て、ただものならずと見抜き、館に伴(ともな)い帰って終夜語り合った。この老僧に畏敬(いけい)の念(ねん)を抱いた頼朝は、別れに際し猫の形をした銀の香呂(こうろ)を贈ったが、彼は門前にいた子どもに惜(お)しげもなくそれを与えて、どこへともなく立ち去って行ったという。
■斎藤茂吉(さいとうもきち)…大正、昭和期の歌人、精神科医。『アララギ』の中心人物。北杜夫、斎藤茂太は子。昭和28年(1953年)没。
■坂上是則(さかのうえのこれのり)…平安前・中期の貴族、歌人。三十六歌仙の一人。
■佐々木信綱(ささきのぶつな)…歌人、国文学者。佐々木幸綱は孫。
■佐佐木幸綱(ささきゆきつな)… 歌人、評論家。早稲田大学政経学部教授。昭和13年(1938年)、東京生まれ。弘綱、信綱、治綱という歌人の家に生まれる。歌人俵万智(たわらまち)は佐佐木幸綱の影響で早稲田大学在学中に短歌を始めている。
■式子内親王(しきしないしんのう・しょくしないしんのう)… 後白河天皇の第三皇女。
■志貴皇子(しきのみこ)…天智天皇の皇子。奈良時代初期の歌人。
■持統天皇(じとうてんのう)…第41代天皇。天智(てんじ)天皇の娘。天武天皇の皇后。
■島木赤彦(しまきあかひこ)…明治、大正時代の歌人。長野県生まれ。大正15年(1926年)、49歳で没。
■釈迢空(しゃくちょうくう)… 大正から昭和にかけての歌人、詩人、国文学者、民俗(みんぞく)学者。本名折口信夫(おりくちしのぶ)。古語、古句を駆使(くし)し、人情の機微(きび)にふれた近代的な感受性を加味した作風で知られる。
■寂連(じゃくれん)法師(ほうし)… 俗名(ぞくみょう)は藤原定長(ふじわらのさだなが)。
■舒明天皇(じょめいてんのう)…第34代天皇。天智天皇、天武天皇の父。
■蝉丸(せみまる)…平安時代前期の歌人。古くは「せみまろ」とも読む。盲目だったという説もある。
■僧正遍照(そうじょうへんじょう)=良岑宗貞(よしみねのみねさだ)
■平忠度(たいらのただのり)…平安末期の武将、歌人。平清盛の異母弟。
■橘曙覧(たちばなあけみ)…江戸末期の歌人。明治元年(1868年)、57歳で没。
■俵万智(たわらまち)… 昭和37年(1962年)、大阪生まれ。中学2年(14歳)の時、福井県に移転。早稲田大学在学時、歌人佐佐木幸綱(ささきゆきつな)氏の影響を受け、短歌を始める。卒業後、国語教員として神奈川県立橋本高校での4年間の勤務を経て、本格的に創作活動に入る。
■土屋文明(つちやぶんめい)… 大正・昭和時代の歌人。
■寺山修司(てらやましゅうじ)…昭和時代の詩人、歌人、劇作家、映画監督。昭和58年(1983年)、47歳で没。
■土岐善麿(ときぜんまろ)…大正、昭和期の歌人、国語学者。
■長塚節(ながつかたかし)… 明治・大正の歌人、小説家。茨城県生まれ。
■能因法師(のういんほうし)…平安中期の僧侶、歌人。中古三十六歌仙の一人。
■橋田東声(はしだとうせい)…大正時代の歌人、経済学者。昭和5年(1930年)、45歳で没。
■丈部稲麻呂(はせつかべのいなまろ)…駿河(するが:静岡県)の国の防人(さきもり)。
■樋口一葉(ひぐちいちよう)…明治時代の小説家、歌人。明治29年(1896年)、肺結核により24歳で没。
■藤原家隆(ふじわらのいえたか)…鎌倉時代の歌人。『新古今和歌集』の撰者の一人。
■藤原定家(ふじわらのさだいえ・ふじわらのていか)… 平安末期、鎌倉初期の歌人、歌学者。
■藤原俊成(ふじわらのとしなり・ふじわらのしゅんぜい)…平安後期、鎌倉初期の公家、歌人。藤原定家の父。
■藤原敏行(ふじわらのとしゆき)…平安前期の貴族、歌人、書家。三十六歌仙の一人。
■藤原雅経(ふじわらのまさつね)=飛鳥井雅経(あすかいまさつね)…鎌倉初期の歌人。『新古今和歌集』の撰者の一人。
■藤原良経(ふじわらのよしつね)…鎌倉初期の貴族、歌人。
■文屋康秀(ふんやのやすひで)…平安前期の歌人。六歌仙、および中古三十六歌仙の一人。小野小町と親しい関係にあったとされる。
■前田夕暮(まえだゆうぐれ)… 大正から昭和にかけての歌人。本名は洋造。神奈川県の大根村(現秦野市)生まれ。筆名である「夕暮」 は、西行(さいぎょう)の 「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮」 からとったもの。
■正岡子規(まさおかしき)…明治時代の俳人、歌人。明治35年(1902年)、36歳で没。
■源兼昌(みなもとのかねまさ)…平安後期の貴族、歌人。
■源実朝(みなもとのさねとも)… 鎌倉幕府の三代将軍、歌人。頼朝の二男。藤原定家に歌を学び、万葉調の雄大な歌を残した。
■源経信(みなもとのつねのぶ)…平安後期の貴族、歌人。
■源宗于(みなもとのむねゆき)…平安前・中期の貴族、歌人。光孝天皇の孫。
■源義家(みなもとのよしいえ)…平安中・後期の武将。
■壬生忠岑(みぶのただみね)…平安前期の三十六歌仙の一人。『古今和歌集』の撰者の一人。
■宮柊ニ(みやしゅうじ)…昭和時代の歌人。
■紫式部(むらさきしきぶ)…平安中期の女流作家、歌人。著書に『源氏物語』、『紫式部日記』、『紫式部集』など。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。
■本居宣長(もとおりのりなが)…江戸中期の国学者、歌人。
■山上憶良(やまのうえのおくら)…奈良初期の歌人。『貧窮問答歌』を作歌。
■山部赤人(やまべのあかひと)…奈良時代の代表的歌人。三十六歌仙の一人。
■与謝野晶子(よさのあきこ)… 大阪府堺市出身。明治から昭和にかけての歌人。自由奔放(じゆうほんぽう)、官能的(かんのうてき)、情熱的な歌風で知られる。
■良寛(りょうかん)… 江戸後期の曹洞宗の僧、歌人。
■若山牧水(わかやまぼくすい)…大正、昭和初期の歌人。昭和3年(1928年)、43歳で没。
■所収歌 関連用語
■小倉百人一首…藤原定家(ふじわらのさだいえ/ていか)が小倉山(京都)の山荘の襖障子(ふすましょうじ)に貼るために選んだといわれる百首の秀歌撰。天智天皇(てんじてんのう)から順徳天皇に至る百人の歌人から一首ずつを選んだ和歌集。近世以後、歌がるたとして普及した。百人一首。
■あ行
あをによし 奈良の都は 咲く花の にほふがごとく 今さかりなり(小野老)
・あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなり
・奈良の都、平城京は、咲く花が色美しく照り映(は)えるように、今やまことに繁栄(はんえい)の極(きわ)みであることだ。
・花を賞美する自然感情と都への讃美とを重ね合わせ、作者の明るく満ち足りた喜びを伝えている。(句切れなし)
※あを(お)によし… 「奈良」にかかる枕詞。「青丹(あおに)」は青土の意で、奈良時代、奈良山付近から青土が産出して顔料にしたことによるという。
※奈良の都… 平城京。今の奈良市付近。
※にほ(お)う… 美しく咲きにおうように。「にほふ」は色が美しく照り映えるの意。
赤とんぼ 早く現はれ 捕りて食へ 昼を来てさす このやぶ蚊ども(窪田空穂)
・あかとんぼ はやくあらわれ とりてくえ ひるをきてさす このやぶかども
・昼だというのに、しつこく襲(おそ)ってきて刺(さ)すこのやぶ蚊(か)どもには、もう何ともたまらず困っている。赤とんぼよ、頼むから早く私の前に現われて、こいつらを捕まえて食べてしまってくれよ。 (三句切れ)
秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる(藤原敏行)
・あききぬと めにはさやかにみえねども かぜのおとにぞ おどろかれぬる
・秋がやってきたと目にはまだはっきりとは見えないけれども、ふと耳にした涼(すず)やかな風の音に、秋の到来(とうらい)を、ふいに気づかされたことだ。
・視覚と聴覚とのずれをうまく利用して、ふいに気づかされた秋の訪れへの詠嘆(えいたん)が詠(うた)われている。(句切れなし)
※来ぬと… 秋が来てしまったと。
※さやかに… はっきりと。
※見えねども… 見えないけれども。
※おどろかれぬる… 感じてしまわずにはいられない。
あけて待つ 子の口のなか やはらかし 粥運ぶ 我が匙に触れつつ(五島美代子)
・あけてまつ このくちのなか やわらかし かゆはこぶ わがさじにふれつつ
・口を開けて待っている幼い我が子に、お匙(さじ)にお粥(かゆ)をすくって運んでやると、そのたびに匙が子どもの口に触れる。触れるたびに、いたいけな我が子の幼い命の感触が、やわらかに匙から伝わってくる。(三句切れ)
※ 「亡(な)き子来て袖(そで)ひるがへ(え)しこぐとおもふ(う)月白き夜(よ)の庭のブランコ」の項を参照のこと。
朝あけて 船より鳴れる 太笛の こだまは長し 並みよろふ山(斎藤茂吉)
・あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに よしののさとに ふれるしらゆき
・ほのぼのと夜が明けるころに、明け方の月の光がしらじらと照り渡っているのかと思えるほどに明るい、吉野の里に降り積もった白雪の美しさよ。(句切れなし)
※あさぼらけ… 朝、ほのぼのと明るくなったころ。
※有明(ありあけ)の月… 陰暦二十日すぎごろの月で、夜遅く出て、夜明けになってもまだ空に出ている月。残月。
※見るまでに… 見間違えるほどに。
※吉野の里… 現奈良県の吉野町あたり。
★ 小倉百人一首所収。
あさぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪(坂上是則)
・あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに よしののさとに ふれるしらゆき
・ほのぼのと夜が明けるころに、明け方の月の光がしらじらと照り渡っているのかと思えるほどに明るい、吉野の里に降り積もった白雪の美しさよ。(句切れなし)
※あさぼらけ… 朝、ほのぼのと明るくなったころ。
※有明(ありあけ)の月… 陰暦二十日すぎごろの月で、夜遅く出て、夜明けになってもまだ空に出ている月。残月。
※見るまでに… 見間違えるほどに。
※吉野の里… 現奈良県の吉野町あたり。
★ 小倉百人一首所収。
あしひきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む(よみ人知らず)
・あしひきの やまどりのおの しだりおの ながながしよを ひとりかもねん
・(一人寝するという)山鳥の、長くしだれて(たれ下がって)いる尾のように、長い長い秋のこの夜を、恋しい人と離れ、今夜はたった一人で寝なければならないのだろうかなあ。
・秋の夜長を、人を恋いつつ独り寝する慰(なぐさ)めがたいわびしさを詠(うた)っている。(句切れなし)
※足引きの(あしひきの)… 「山」にかかる枕詞。上代(主に奈良時代)以後は「あしびきの」と読まれた。
※山鳥… キジ科に属する野鳥。キジに似るがやや大きく、雄の尾は長さ約1mになる。
※しだり尾の… 長くたれた尾のように。
※ながながし… 長い長い。
※ひとりかも寝む… 一人で寝なければならないのだろうかなあ。
※「ながながし」… 「夜」を修飾する掛詞(かけことば)。「(尾が)長い」という意味と、「長い(夜)」の二つの意味を持たせている。
※掛詞(かけことば)… 一つの言葉に二つ以上の意味をもたせる手法。口語訳する時は、二つの意味が明らかになるように訳すようにする。
※あしひきの山鳥の尾のしだり尾の… 「ながながし」を引き出すために前置きとして使われている序詞(じょことば)。
※序詞(じょことば)… ある語句を引き出すための前置きの言葉。枕詞と同じような働きをするが、音数に制限は無く、二句以上にわたることが多い。枕詞のように慣用化されておらず、ほとんどが作者の創作によるものである。
※小倉百人一首所収。
※小倉百人一首では柿本人麻呂作とされているが、万葉集では作者未詳(みしょう)としている。
あたらしく 冬きたりけり 鞭のごと 幹ひびき合ひ 竹群はあり(宮柊ニ)
・あたらしく ふゆきたりけり むちのごと みきひびきあい たかむらはあり
・身の引き締(し)まるような、新しい冬の到来(とうらい)である。吹きすさぶ寒風に鞭(むち)のような鋭(するど)い音を立てて、群がり生えた竹が、しなり揺(ゆ)れている。(二句切れ)
あますなく 小草は枯れて 風に鳴る かなたに小さき 山の中学(木俣修)
・あますなく おぐさはかれて かぜになる かなたにちいさき やまのちゅうがく
・広い空の下、野山は遠くへと続き、見渡す限り草は冬枯(ふゆが)れて、寒風に乾いた音を立てている。冬の寂(さび)しい風景の中、彼方(かなた)に小さく見えるのは、山間(やまあい)の中学校の校舎の姿である。
・広い野山から、遠く小さい中学校の校舎の姿へと、視野がしぼられている。(三句切れ)
天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ(僧正遍照=良岑宗貞)
・あまつかぜ くものかよいじ ふきとじよ おとめのすがた しばしとどめん
・大空を吹く風よ、天女の帰り上ってゆく雲間(くもま)の通り道を、吹いて閉ざしてくれよ。天女の美しい舞い姿を、今しばらくこの下界にとどめおいて見ていたいのだ。(三句切れ)
※天(あま)つ風… 大空を吹く風。ここでは呼びかけ。
※雲の通ひ(い)路(じ)… 天へと通ずる雲間の道。
※陰暦(いんれき)十一月の中旬に行われた宮中の華麗(かれい)な儀式(ぎしき)、豊明節会(とよのあかりのせちえ)で舞を舞う少女を天女に見立て、美しいその舞姫(まいひめ)の姿をなおも賞美していたいという気持ちが詠(うた)われている。天武天皇の御代(みよ)、天女が吉野に下(くだ)って舞ったという伝説になぞらえ、舞姫を天女に見立てている。
※小倉百人一首所収。
天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも(阿倍仲麻呂)
・あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも
・大空をはるかに見渡すと、今ちょうど東の空に美しい月が出ている。この月は、かつて私が日本に住んでいた頃、故郷奈良の三笠の山の上に出るのを見て楽しんだあのなつかしい月と同じなのだと思うと、胸がしめつけられるように切なくなるのだ。
・仲麻呂が三十五年間の中国での留学生活を終えて、明州(現在の寧波)の海辺で別れの宴(うたげ)の際に詠(よ)んだものと伝えられる(※この帰国航海は海難により失敗)。三十数年の昔に見た故郷の月という「時間」と、今中天にかかる中国大陸の月という「空間」とが一時に結びついて、望郷の念をかきたてられている心情が読み取れる。月を通して、作者の脳裏(のうり)に、今、故郷が現実のものとして蘇(よみがえ)っているのである。(句切れなし)
※天の原… 広い大空。
※ふりさけ見れば… ふり仰いで遠くを眺(なが)めやると。
※春日(かすが)なる… 春日にある。春日は奈良市内にある春日神社のある一帯。
※三笠(みかさ)の山… 春日山の一峰(いっぽう)、御蓋山(みかさやま)のこと。
※出(い)でし月かも… 出たあの月だなあ(、今出ているこの月は。)主語にあたる語句が省略されている。
※阿部仲麻呂(安部仲麻)… あべのなかまろ。奈良時代の文学者。716年、十六歳で留学生に選ばれ、翌年、遣唐留学生として入唐(にっとう:唐の国へ行くこと)、そのまま唐の朝廷に仕える。海難(航海中の事故)のために帰国を果たせず、在唐五十余年、770年、同地にて七十歳で亡くなる。
※小倉百人一首所収。
天地に われ一人ゐて 立つごとき この寂しさを 君はほほゑむ(会津八一)
・あめつちに われひとりいて たつごとき このさびしさを きみはほほえむ
・壮大(そうだい)で広大無辺(こうだいむへん)のこの天地に、私たった一人が立つような孤独感、寂(さび)しさを抱(かか)える思いの中、今私の前に立ち現われた、あなた救世観音(ぐぜかんのん)像の慈悲(じひ)に溢(あふ)れたその永遠の微笑みと、その慈眼(じげん:慈悲に満ちた目)が、私をじっと見守り包んでくれていることだ。(句切れなし)
※作者会津八一(あいづやいち)が、奈良法隆寺夢殿(ゆめどの)の本尊(ほんぞん)である救世観音(ぐぜかんのん)像を拝(はい)した際の作。
※会津八一(あいづやいち)… 正岡子規(まさおかしき)に傾倒(けいとう)したが、歌壇(かだん)とは交渉を直接もたなかった。明治41年、奈良を旅して仏教美術への関心を深め、歌材の多くを奈良の仏教美術からとり、仮名書きによる万葉調で古代への憧憬(しょうけい)の思いを多く詠(よ)んだ。
雨に濡れし 夜汽車の窓に 映りたる 山間の町の ともしびの色(石川啄木)
・あめにぬれし よぎしゃのまどに うつりたる やまあいのまちの ともしびのいろ
・夜の雨の中を、ごとごとと走る汽車に乗りながらぼんやりと窓の外を眺(なが)めていると、山間(やまあい)の町の寂(さび)しい灯(ともしび)が見えてきた。灯の色はしっとりと雨に濡(ぬ)れ、窓に滲(にじ)み浮かんで見えている。しみじみと旅情を感じつつ、山間の町の人々の暮(く)らしを思い、ゆっくり流れてゆく灯を静かな心で見つめていると、ほのかな温かみを感じたことだ。(句切れなし)
淡路島 かよう千鳥の 鳴く声に いくよねざめぬ 須磨の関守(源兼昌)
・あわじしま かようちどりの なくこえに いくよねざめぬ すまのせきもり
・この須磨(すま)の海岸から淡路島(あわじしま)へと、冬の海の上を飛び通う千鳥(ちどり)たちのもの悲しく鳴く声に、須磨の関所の番人は、いったい幾夜(いくよ)を、眠りから覚めては寂(さび)しい思いをしたことだろう。(四句切れ)
・冬のわずか一夜、二夜の旅寝(たびね)でさえ千鳥の鳴き声に寝覚(ねざ)める寂(さび)しさであるものを、もともと人気の少なくうら寂しい須磨の浦で務め暮らさねばならない関守(せきもり)は、その寂しさを幾晩(いくばん)重ねたことだろうかと思いやっている。
※淡路島(あわじしま)… 明石海峡(あかしかいきょう)にある島。兵庫県。
※千鳥(ちどり)… 冬に海辺などに群れをなしている小鳥。海辺を数千羽が群がって飛ぶところからこの名がある。
※須磨(すま)… 兵庫県神戸市須磨区。
※関守(せきもり)… 関所の番人。
※小倉百人一首所収。
家にあれば 笥もる飯を 草まくら 旅にしあれば 椎の葉にもる(有馬皇子)
・いえにあれば けにもるいいを くさまくら たびにしあれば しいのはにもる
・我が家にいればいつも食器に盛って食べる飯(めし)を、今は旅のことであるから、このように椎(しい)の葉に盛ってわびしく食べることだ。(句切れなし)
※笥(け)… 食器。
※飯(いい)… ごはん。米をこしきに入れて蒸したもの。
※有間皇子(ありまのみこ)が、謀反(むほん)の疑いで召されてゆく時の旅の歌。
※「草枕」は「旅」にかかる枕詞。旅先で草を結んで枕とし、夜露に濡(ぬ)れて仮寝(かりね)をしたことから。
いかるがの さとのをとめは よもすがら きぬはたおれり あきちかみかも(会津八一)
・いかるがの sとのおとめは よもすがら きぬはたおれり あきちかみかも
・静かな、夜の斑鳩(いかるが)の里を散策していると、あちらこちらで機織(はたおり)の音が響いている。この里の娘たちは、秋祭りや新年に備えて、こうして夜が更(ふ)けるまで営々(えいえい)と機を織っているのだ。秋が近づいているのだと、しみじみ感じられたことだ。(四句切れ)
※明治41年、作者会津八一(あいづやいち)が奈良法隆寺を訪れ、夜、法隆寺近隣(きんりん)の宿から法隆寺界隈(かいわい)を散策した際に聞こえてきた機織(はたおり)の音に心を打たれて詠(よ)んだ歌。(いかるがの里の乙女は夜もすがら衣機織れり秋近みかも)
※会津八一(あいづやいち)… 正岡子規(まさおかしき)に傾倒(けいとう)したが、歌壇(かだん)とは交渉を直接もたなかった。明治41年、奈良を旅して仏教美術への関心を深め、歌材の多くを奈良の仏教美術からとり、仮名書きによる万葉調で古代への憧憬(しょうけい)の思いを多く詠(よ)んだ。
幾山河 こえさりゆかば さみしさの はてなん国ぞ きょうも旅ゆく(若山牧水)
・いくやまかわ こえさりゆかば さみしさの はてなんくにぞ きょうもたびゆく
・いったい私は、いくつの山川を越えて行けば、寂(さび)しさの終わり果てる国にたどりつくことができるというのだろう。生きている限り私は、今日もまた寂しい思いを胸に旅を続けていかなければならないのだ。(四句切れ)
石がけに 子ども七人 こしかけて 河豚を釣りをり 夕焼け小焼け(北原白秋)
・いしがけに こどもしちにん こしかけて ふぐをつりおり ゆうやけこやけ
・夕方、岸壁(がんぺき)で子どもが七人仲良く並んでこしかけ、河豚(ふぐ)釣(つ)りをして遊んでいる。広い空も子どもたちも、美しい夕焼けの赤い色にとけ込んでしまっている。(四句切れ)
石をもて 追わるるごとく ふるさとを 出でしかなしみ 消ゆる時なし(石川啄木)
・いしをもて おわるるごとく ふるさとを いでしかなしみ きゆるときなし
・まるで石を投げられながら追われるようにしてふるさとを去ったあの時の悲しみは、今でも決して消えることがないことだ。(句切れなし)
※明治38年(1905年)、故郷渋民村の宝徳寺住職であった啄木の父の宗費滞納が原因で一家が寺を追われる事件があった。宗費滞納の理由が啄木自身の借金返済のためだったとする説がある。
いづくにか しるしの糸は つけぬらむ 年々来鳴く つばくらめかな(樋口一葉)
・いずくにか しるしのいとは つけぬらん としどしきなく つばくらめかな
・どこかにきっと、目印になる糸をつけてあるのでしょう。燕(つばめ)は毎年毎年、春が来ると決まって自分の巣に帰って来ては鳴いている。(二句切れ)
※つばくらめ… 燕(つばめ)。日本には春に飛来、人家などに巣を作り、秋に南方へ渡る夏鳥。「つばくらめ」は古名(こめい)。つばくら、つばくろ。
※樋口一葉(ひぐちいちよう)が十三歳の時に詠(よ)んだ歌。
いちはつの 花咲きいでて 我が目には 今年ばかりの 春行かんとす(正岡子規)
・いちはつの はなさきいでて わがめには ことしばかりの はるゆかんとす
・今年もいちはつの花が咲き始めた。重い病にある私の目には、今年限りの最後の春が、今過ぎていこうとしていることだ。(句切れなし)
いついつと 待ちしさくらの 咲き出でて いまはさかりか 風吹けど散らず(若山牧水)
・いついつと まちしさくらの さきいでて いまはさかりか かぜふけどちらず
・いつかいつかと待ち望んでいた桜が、ようやく咲きほころんだ。やがて、夢のように儚(はかな)く散り果ててしまうであろう桜の花だが、花盛(はなざか)りの今は、そんな様子はいささかも感じさせず、風が吹いても、花の一片(ひとひら)さえ散ることはない。(句切れなし)
いつしかに 春の名残と なりにけり 昆布干場の たんぽぽの花(北原白秋)
・いつしかに はるのなごりと なりにけり こんぶほしばの たんぽぽのはな
・いつの間にか春は去ってしまったのだなあ。たんぽぽの花が昆布干場の隅(すみ)に、ひっそりと咲いている。(三句切れ)
一疋が さきだちぬれば 一列に つづきて遊ぶ 鮒の子の群(若山牧水)
・いっぴきが さきだちぬれば いちれつに つづきてあそぶ ふなのこのむれ
・一匹(いっぴき)が先を泳ぐと、それに続いて何匹もの鮒(ふな)の子たちが一列になって続いて泳ぐ。そのうち、別の一匹が群れから飛び出すと、それに続いて鮒の子たちがまた一列になって泳ぐ。鮒の子たちの無心に遊んでいる様子が、何ともほほえましい。(句切れなし)
いつもより 一分早く 駅に着く 一分 君のこと考える(俵万智)
・いつもより いっぷんはやく えきにつく いっぷん きみのことかんがえる
・いつもより一分早く駅に着いてしまった私。電車を待つ時間はいつもより一分多くなるだけだけれど、そんな時でさえ、私が考えているのはあなたのこと。私の心の中にはいつも、大切なあなたがいるから。
稲刈りて さびしく晴るる 秋の野に 黄菊はあまた 目を開きたり(長塚節)
・いねかりて さびしくはるる あきののに きぎくはあまた めをひらきたり
・稲を刈り取ったあとの秋の野山はさびしく感じるが、秋晴れの野原には、明るくさわやかに黄菊がたくさん咲いていたことだ。(句切れなし)
いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指の間より落つ(石川啄木)
・いのちなき すなのかなしさよ さらさらと にぎればゆびの あいだよりおつ
・砂は、こうして力いっぱい手に握(にぎ)っても、さらさらと指の間からこぼれ落ちてしまう。乾(かわ)いた、そして命をもたない砂のはかなさよ。(二句切れ)
・前途の見通しのつかないままに無為の日々を北海道で送っていた作者が、海岸の空しい砂に託(たく)して、人生の儚(はかな)さと自己の虚無(きょむ)的な心境を歌ったもの。
妹の 小さき歩み いそがせて 千代紙買いに 行く月夜かな(木下利玄)
・いもうとの ちいさきあゆみ いそがせて ちよがみかいに ゆくつきよかな
・日はとっぷりと暮れている。千代紙を欲しがった幼い妹を、兄が連れて、夜道を二人で歩いている。ついつい兄は、妹がなかなか速く歩けないので、歩みを急(せ)かせてしまう。二人の兄妹を、ほのぼのと宵の月が照らしている。(句切れなし)
石ばしる 垂水の上の さわらびの もえいずる春に なりにけるかも(志貴皇子)
・いわばしる たるみのうえの さわらびの もえいずるはるに なりにけるかも
・雪解けのためにかさを増し、激しい勢いで石の上を流れる水。滝のほとりのわらびが芽を出した。待ち焦(こ)がれていた春が、いよいよやって来たのだなあ。(句切れなし)
※石(いわ)ばしる… 岩の上を激しい勢いで流れる。枕詞としての使い方をしているという説がある。
※垂水(たるみ)の上… 滝のほとり。地名とする説もある。
※早蕨(さわらび)… 芽を出したばかりのわらび。
※なりにけるかも… なったのだなあ。「かも」は詠嘆(えいたん)を表し、平安時代に「かな」となる。
※志貴皇子(しきのみこ)… 天智天皇の皇子。
うすべにに 葉はいちはやく 萌えいでて 咲かんとすなり 山桜花(若山牧水)
・うすべにに ははいちはやく もえいでて さかんとすなり やまざくらばな
・うす紅(べに)色に染まった若葉が早くも芽を出して、今や咲こうとしている山桜(やまざくら)の花であることだ。(四句切れ)
馬追虫の ひげのそよろに 来る秋は まなこを閉ぢて 想ひ見るべし(長塚節)
・うまおいの ひげのそよろに くるあきは まなこをとじて おもいみるべし
・細く長いウマオイの髭(ひげ)がそっと揺(ゆ)れるように密(ひそ)やかに訪れてくる秋の気配は、眼を閉じて心静かに想い見るのがふさわしい。密やかに訪れる秋の気配を、ささやかなものにしみじみと感じている。(句切れなし)
※馬追虫(うまおい)… ウマオイムシ。スイッチョ。キリギリス科の昆虫。触角が長く、体色は緑色で体長は約3cm。「スイッチョ」と鳴く。
海恋し 潮の遠鳴り 数えては 少女となりし 父母の家(与謝野晶子)
・うみこいし しおのとおなり かぞえては おとめとなりし ちちははのいえ
・ああ、ふるさとの海が恋しい。遠くから聞こえてくる波の音を数え数えしては、夢多い少女に育っていった、あの懐(なつ)かしいふるさとの、父母の家よ。(初句切れ)
うらうらに 照れる春日に 雲雀あがり 情悲しも 独りし思へば(大伴家持)
・うらうらに てれるはるひに ひばりあがり こころかなしも ひとりしおもえば
・うららかに照る春の日、高らかにさえずりながら雲雀(ひばり)は空に舞い上がり、私の心は痛み、切なさに溢(あふ)れる。一人でもの思いに沈んでいると。
・「うらうらに照れる春日にひばりあがり」と「情悲しも」を組み合わせ、明るい叙景から暗い叙情へと移行する暗転の技法を用い、しみじみとした憂愁(ゆうしゅう)の情を深めている。(四句切れ)
※うらうらに… うららかに。のどかに。
※照れる… 照っている。
※情(こころ)悲しも… 心が痛まれるなあ。
※大伴家持(おおとものやかもち)… 奈良時代の歌人。万葉集には四百七十余首と集中最も多数が収められている。また、万葉集編纂(へんさん)者の一人とされている。
瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば ましてしぬばゆ いずくより 来たりしものぞ 眼交に もとなかかりて 安寝しなさぬ(山上憶良)
・うりはめば こどもおもおゆ くりはめば ましてしぬばゆ
いずくより きたりしものぞ まなかいに もとなかかりて やすいしなさぬ(長歌)
・まくわ瓜(うり)を食べていると、わが子が喜んでこれを食べている姿が目に浮かぶ。栗(くり)を食べていればなおいっそうわが子がいとおしく思われてならない。どのような過去の因縁(いんねん)があってこの子は自分の子として生まれてきたものなのだろうか。こうして離れていても、子の面影(おもかげ)が目の前にしきりにちらついて、安らかに眠ることができない。
・作者が遣唐使の随員(ずいいん)として中国に滞在した折に、故国日本を恋い慕(した)って詠(よ)んだもの。我が子に対する親の深い愛情が率直に詠(うた)われている。
※瓜(うり)食(は)めば… 瓜を食べるといつも。「瓜」は今のマクワウリという。
※ましてしぬばゆ… いっそう偲(しの)ばれる。
※いずくより… どこから。
※来たりしものぞ… 来たものなのか。「子供というものは、どのような過去の因縁(いんねん)で、自分の子として生まれてきたものであるのか」の意。
※眼交(まなかい)に… 目先に。
※もとな… むやみに。
※懸(かか)りて… (子供の姿が)ちらついて。
※山上憶良(やまのうえのおくら)… 奈良時代の官人、歌人。
遠足の 小学生徒 うちょうてんに 大手ふりふり 往来とほる(木下利玄)
・えんそくの しょうがくせいと うちょうてんに おおでふりふり おおらいとおる
・遠足の小学生たちが、どの子もうれしさいっぱいの様子で、元気に大きく手をふりふり往来を歩いている様子が、何とも無邪気(むじゃき)でほほえましい。(句切れなし)
近江の海 夕浪千鳥 汝が鳴けば 情もしのに 古思ほゆ(柿本人麻呂)
・おうみのみ ゆうなみちどり ながなけば こころもしのに いにしえおもおゆ
・ほろび果てた大津の都の跡(あと)に立ち、天智天皇の代(よ)を偲(しの)んで悲しみにたえないのに、夕暮れの琵琶湖(びわこ)の波に群がり飛ぶ千鳥(ちどり)よ、お前たちの鳴き騒ぐ声を聞くと、心も打ちしおれていっそう昔のことがしみじみ思われてならない。
・人間的情感と時間的推移とを絵画的な美しさの中に盛り込んだ名作である。「近江の海」「古思ほゆ」は字余り。(句切れなし)
※近江(おうみ)の海(み)… 琵琶湖。
※夕浪千鳥… 夕浪の立つ上を騒ぎ飛ぶ千鳥よ。「夕浪」と「千鳥」を重ねた人麻呂による造語。
※汝(な)が鳴けば… お前が鳴くと。
※情(こころ)もしのに… 心もしおしおとしおれなびくほどに。
※古(いにしえ)思ほゆ… 昔のことが思われる。「古(いにしえ)」は、今は廃墟(はいきょ)と化したこの地に、かつて壮麗(そうれい)な大津の都があった天智天皇の時代を指している。
※柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)… 飛鳥時代の歌人。
大海の 磯もとどろに 寄する波 割れてくだけて さけて散るかも(源実朝)
・おおうみの いそもとどろに よするなみ われてくだけて さけてちるかも
・大海(たいかい)の磯(いそ)にすさまじく打ち寄せる波が、激しく岩にぶつかり割れてとどろき、砕(くだ)け散っていることだ。
・「寄する」「割れて」「くだけて」「さけて」「散る」と動詞が多用され、大海の荒々しさが臨場感を伴った映像として伝わってくる力強い作品である。(句切れなし)
※とどろ… 磯に打ち寄せる波のとどろくさま。
※散る… 砕け散っていることだなあ。「かも」は詠嘆(えいたん)を表し、平安時代に「かな」となる。
※源実朝(みなもとのさねとも)… 鎌倉幕府の三代将軍、歌人。頼朝の二男。藤原定家に歌を学び、万葉調の雄大な歌を残した。
大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立(小式部内侍)
・おおえやま いくののみちの とおければ まだふみもみず あまのはしだて
・大江山(おおえやま)を越え、生野(いくの)の道を通って行く丹後(たんご:京都北部)への道ははるかに遠いので、私はまだ天(あま)の橋立(はしだて)を踏(ふ)み歩いてはいませんし、丹後にいる母(和泉式部:いずみしきぶ)からの手紙も見てはおりません。(四句切れ)
※天の橋立(あまのはしだて)… 京都府宮津湾(みやずわん)にある景勝地(けいしょうち)で、日本三景(他は広島県の宮島、宮城県の松島)の一つに数えられる。
※ 大江山(おおえやま)、生野(幾野:いくの)は、いずれも京都から丹後の国への道筋にある。
※掛詞(かけことば)… 「いく野(地名)」と「行く野」、「踏みも見ず」と「文も見ず」、それぞれ二つの異なる意味をもたせてある。
※作者小式部内侍(こしきぶのないし)は年少でありながらが歌才(かさい)に優れ、宮中(きゅうちゅう)の歌会(うたかい)の歌人に選ばれた時、藤原定頼(ふじわらのさだより)が作者の母親である歌人として有名な和泉式部(いずみしきぶ)に代作してもらえないのでさぞ困っているだろうとからかったところ、小式部内侍がそれに対して即興(そっきょう)で歌って返答したもの。
母である和泉式部はそのころ夫の任地である丹後の国に下(くだ)っていたが、作者は、丹後へ行って母に会ってもいないし、母から手紙さえ受け取っていないと、よくも知らずに人を侮(あなど)るものではないとその疑惑を否定したのである。
母に代作してもらわねば人並みの歌は詠(よ)めまいと思われていた小式部内侍が、即座に技巧の優れた見事な歌を詠み返したので、意表をつかれた定頼は驚嘆(きょうたん)するばかりで逃げ帰ったという。
※小式部内侍十五才の時の作。二十五歳のころに亡(な)くなっている。
※小倉百人一首所収。
奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき(よみ人知らず)
・おくやまに もみじふみわけ なくしかの こえきくときぞ あきはかなしき
・人里遠く離れた山で、散り敷(し)いたもみじ葉(ば)を踏(ふ)み分けて鳴く鹿のもの悲しげな声を耳にすると、秋はひとしお心にしみて悲しく感じられることだ。
・奥山でもみじを踏み分けてもの悲しげに鳴いている鹿の声を聞きながら、その姿を作者が頭の中で思い描き、いっそう秋のうら悲しさを深めているのである。(句切れなし)
※奥山… 人里遠く離れた山。
※もみぢ(じ)踏み分け… (鹿が)散り敷いたもみじ葉を踏み分けて。
※鹿は妻を恋い慕(した)って鳴くとされた。
※作者不明ながら相当な歌人の作と考えられている。小倉百人一首では猿丸太夫作としている。
※小倉百人一首所収。
憶良らは 今はまからむ 子なくらむ それその母も 吾を待つらむぞ(山上憶良)
・おくららは いまはまからむ こなくらむ それそのははも わをまつらむぞ
・私めはそろそろ宴(うたげ)の席よりおいとまさせて頂き、帰ることと致しましょう。きっと家では子どもが泣いているでしょうし、恐らくその子の母なる私の妻も、私の帰宅を待っておりましょう。
・作者が、家で待つ妻や子どもを思う優しさやあたたかい心が感じられる。
※山上憶良(やまのうえのおくら)が宴席(えんせき)を途中で退出する際に詠(よ)んだもの。
幼きは 幼きどちの ものがたり 葡萄のかげに 月かたぶきぬ(佐々木信綱)
・おさなきは おさなきどちの ものがたり ぶどうのかげに つきかたぶきぬ
・幼い子どもたちどうしが、何やら楽しげに話したり、遊んだりしている。葡萄(ぶどう)の木のかげに月がしずもうとしている中、静かな夏の夜はふけていく。(三句切れ)
おとうさまと書き添へて 肖像画の貼られあり 何という吾が鼻のひらたさ(宮柊二)
・おとうさまとかきそえて しょうぞうがのはられあり なんというわがはなのひらたさ
・幼い我が子の描いてくれた私の肖像画(しょうぞうが)に、「おとうさま」と書き添(そ)えて壁に貼(は)られてある。子どもなりに、私の顔を思い浮かべながら一生懸命に描いてくれたのだと思うと、つい微笑ましくなって見入ってしまう。それにしても、紙面いっぱいに勢いよく描かれた私の顔だが、いやはや、何とも平たい鼻であることだ。我が子の健やかな成長を祈るばかりである。(破調)
思い出の一つのようで そのままにしておく 麦わら帽子のへこみ(俵万智)
・おもいでのひとつのようで そのままにしておく むぎわらぼうしのへこみ
・私の思い出と、私とあなたの思い出を残して、夏は過ぎゆこうとしている。部屋の片隅(かたすみ)で見つけた、私の麦わら帽子と、その小さなへこみ。そのへこみさえ、私の大切な思い出のかけらのようで、それを私はそっと、そのままにして、麦わら帽子にとどめておく。時間を永遠にとじこめるように。
親は子を 育ててきたと 言うけれど 勝手に赤い 畑のトマト(俵万智)
・おやはこを そだててきたと いうけれど かってにあかい はたけのとまと
・親としては愛情を精一杯注ぎ、期待をかけ、子育ての苦悶(くもん)も乗り越えて育て上げてきた愛(いと)しい我が子であるが、そんな親の思いを越えて、子どもは子どもとしての思いを抱き、個性をもち、独立した人格をもつかけがえのない自分として成長し、生きている。
おりたちて 今朝の寒さを おどろきぬ 露しとしとと 柿の落ち葉深く(伊藤左千夫)
・おりたちて けさのさむさを おどろきぬ つゆしとしとと かきのおちばふかく
・家の庭に下り立ってみると、あらためて今朝の寒さを肌身(はだみ)に感じたことだ。朝露(あさつゆ)にしっとりと濡(ぬ)れた柿の落ち葉が、深く積もっている晩秋である。(三句切れ)
■か行
帰り来ぬものを轢かれし子の靴をそろえ破れし服をつくろう(作者不詳)
・かえりこぬものを ひかれしこの くつをそろえ やぶれしふくをつくろう
・自動車に轢(ひ)かれて亡(な)くなった我が子がその時履(は)いていた靴(くつ)をそろえてやり、服も破れを繕(つくろ)ってやる母。二度と自分の元へは帰って来ないというのに。戻せるものなら時間を戻したい、不幸な結末など無かったことにしたい。そんなことは絶対に出来るはずがない。それでも、愛する我が子を失った現実が、命の消滅という事実が、一体どうして受け入れられるというのだろう。
・母親の痛ましい心情、運命の非情。これ以上にない悲しさが切実に伝わり、涙を誘う。(句切れなし)
※轢(ひ)かれし… 車にひかれた。
かがやける少年の目よ自転車を買い与へんと言ひしばかりに(作者不詳)
・かがやける しょうねんのめよ じてんしゃを かいあたえんと いいしばかりに
・欲しがっていた自転車を買ってやろうと我が子に約束したところ、たちまち頬(ほお)を火照(ほて)らせ、満面に笑みを浮かべながら心を覗(のぞ)き込むように私の目を見つめる。少年のその瞳は、夢に満ちてきらきらと輝く、純真そのものの瞳であったことだ。(二句切れ)
かすみたつ長き春日をこどもらとてまりつきつつきょうもくらしつ(良寛)
・かすみたつ ながきはるひを こどもらと てまりつきつつ きょうもくらしつ
・うららかに晴れ霞(かすみ)のたなびくのどかな春の日長(ひなが)を、子どもたちと一緒に楽しく手まりをつきながら、今日も私は一日中過ごしてしまったことだなあ。(句切れなし)
かにかくに渋民村は恋しかりおもいでの山おもいでの川(石川啄木)
・かにかくに しぶたみむらは こいしかり おもいでのやま おもいでのかわ
・思い通りにならず、堪(た)えなければならない辛(つら)いことや苦しいことばかりに見舞われて生きていると、ふと、懐(なつ)かしい故郷岩手の渋民村(しぶたみむら)が思い出されてくる。思い出の中の山も川も昔のままに、ただそこにそうしてあるだけだが、ぼろぼろに傷ついた私を癒(いや)し、優しく受け入れてくれるのは、故郷のその美しい自然であるに違いない。もう、いてもたってもいられないほどに、あの故郷が恋しくてたまらないのだ。(三句切れ)
※かにかくに… 古語で、「あれこれと、いろいろと、ともかくも」の意。
瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり(正岡子規)
・かめにさす ふじのはなぶさ みじかければ たたみのうえに とどかざりけり
・病で臥(ふ)す私の床(とこ)のそばの、瓶(かめ)にいけた藤の花房(はなぶさ)が美しく垂(た)れている。花房は、わずかに短くて畳(たたみ)に届いていない。その微妙に保たれた均衡(きんこう)が、ふと私の心を満たしたことだ。今年の春もはや暮れていこうとしている。寝床にあって、花房と畳とのわずかな空間の微妙を捉(とら)えた作者の繊細な視点が異色である。(句切れなし)
唐衣裾に取りつき泣く子らを置きてぞ来ぬや母なしにして(他田舎人大島)
・からころむ すそにとりつき なくこらを おきてぞきぬや おもなしにして
・防人(さきもり)として任地に赴(おもむ)く私の着物の袖にすがりついて、別れを惜(お)しんで泣き悲しむ子どもたちを、家に残したまま来てしまったことだ。子供の世話をする母親もいないのに。(四句切れ)
※防人(さきもり)… 外国の侵略(しんりゃく)に備えて、諸国の軍団の兵士の中から派遣され、今の北九州地方の防備にあたった。定員約千名、勤務年限三年で、多く東国人(とうごくじん)を採用した。
※防人の歌は、防人や防人の家族たちの歌であり、親子や夫婦の別離の悲しみを東国方言に託(たく)して歌いあげた真情あふれた作が多い。他田舎人大島(おさだのとねりおおしま)は信濃(しなの:現長野県)の防人。
※母をもたない子どもを無理に残して任地に赴かなければならなかった父親の悲痛な心情と、防人という公務が個人的な事情をまったく考慮(こうりょ)されない強制力の強いものであったことがうかがわれる。
※唐衣(からころむ)… 防人としての官給(かんきゅう)の服。「からころむ」は「からころも」の東国方言。
※「唐衣(からころも)」を「裾(すそ)」にかかる枕詞(まくらことば)とする説がある。
ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブリキの屋根に月うつる見ゆ(正岡子規)
・がらすどの そとにすえたる とりかごの ぶりきのやねに つきうつるみゆ
・月の清(さや)かに照る静かな夜、ガラス戸越しに見えている、濡(ぬ)れ縁(えん)に置いた鳥かごのブリキの屋根に照り返している月の明かりを眺(なが)めては、私の寝床(ねどこ)からは見えない月の姿を思い見ることだ。(句切れなし)
※脊椎(せきつい)カリエス(脊椎が結核菌に侵される病気。脊椎変形を起こす)で寝たきりの生活を送っていた子規のため、高浜虚子(たかはまきょし)の手配で自宅の病室にガラス戸が入れられ、それによって庭や庭に咲く草花、星や月を歌材とする作品が数多く作られた。
※関連歌、「ガラス戸の外のつきよをながむれどランプのかげのうつりて見えず」を参照のこと。
ガラス戸の外のつきよをながむれどランプのかげのうつりて見えず(正岡子規)
・がらすどの そとのつきよを ながむれど らんぷのかげの うつりてみえず
・美しい月夜の景色を眺(なが)めようと、寝床(ねどこ)からガラス戸越しに外を見やったが、生憎(あいにく)部屋のランプの光がガラスに映って外の景色が何も見えず、がっかりしてしまったことだ。(句切れなし)
※「ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブリキの屋根に月うつる見ゆ」の項を参照のこと。
川ひとすぢ菜たね十里の宵月夜母が生まれし国美くしむ(与謝野晶子)
・かわひとすじ なためじゅうりの よいづきよ ははがうまれし くにうつくしむ
・春の宵(よい)、静かに流れている一筋の川に沿って、どこまでも菜種の花が咲いている。夕月の青い光が、川面や菜の花をおぼろに照らし、まるで夢のような月夜の美しさである。こんな美しい国が、母の生まれたふるさとなのだと思うと、母を慕いつつ、たまらなく愛しくなることだ。
※国… ここでは大阪の河内の平野。
※美(うつ)くしむ… 古語に「慈(うつく)しむ、愛(うつく)しむ」で、「いとおしむ」の意の語がある。
汽車の窓はるかに北にふるさとの山見え来れば襟を正すも(石川啄木)
・きしゃのまど はるかにきたに ふるさとの やまみえくれば えりをただすも
・汽車に乗り、窓の外を眺(なが)めていたら、北のはるか向こうにふるさとの山(岩手山)が見えてきたので、思わず、身のひきしまる思いになったことだ。(句切れなし)
君がため春の野にいでて若菜つむわが衣手に雪はふりつつ(光孝天皇)
・きみがため はるののにいでて わかなつむ わがころもでに ゆきはふりつつ
・あなたに差し上げるために、春の野に出て若菜を摘(つ)んでいると、私の袖には春だというのに雪がしきりに降りかかってくるのでした。これは、そのようにして摘んだ若菜なのです。
・作者の優しい真情が率直に詠(うた)われ、すがすがしい気分を伝えている。(句切れなし)
※若菜… 春の初めに生える食用になる若菜の総称。春の七草(なずな、せり、はこべ、すずな、すずしろ、ごぎょう、ほとけのざ)など。「若菜摘(つ)み」は、正月子(ね)の日にに七種の若菜を摘んで食べると災(わざわ)い・万病(まんびょう)を除(のぞ)くという行事。
※光孝(こうこう)天皇がまだ親王(しんのう)であった時代に、人に若菜(わかな)を贈るのに際して添(そ)えた歌。当時、人にものを贈る際に歌を添える風習があった。
★小倉百人一首所収。
今日までに私がついた嘘なんてどうでもいいよというような海(俵万智)
・きょうまでに わたしがついた うそなんて どうでもいいよと いうようなうみ
・生まれてから今日までに私がついてきた、さまざまな嘘(うそ)。大らかに、深く澄(す)んで、ただそこに遥(はる)かに広がるばかりの海原は、そんな私と私の罪を、黙って許してくれている。大らかさゆえの無関心のようで、それでいて、私の思いも受け入れてくれているかのような、優しく、安堵(あんど)をもたらしてくれる海である。
清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みな美しき(与謝野晶子)
・きよみずへ ぎおんをよぎる さくらづきよ こよいあうひと みなうつくしき
・春、宵闇(よいやみ)の迫(せま)るころ、清水(きよみず)の方へと華(はな)やいだ祇園(ぎおん)の町を歩いていると、夜空に浮かび上がり美しく匂(にお)う桜の花に、月は霞(かす)んで見えている。そぞろ歩きをする誰もが、妖(あや)しくも美しい夜の桜に酔(よ)いしれ、心を浮き立たせている。行き交うそんな人々は、男も女も皆、私にはいっそう美しく感じられたことだ。
・夜の桜の妖(あや)しい美しさに心奪(うば)われる人々と華(はな)やいだ京都の幻想的(げんそうてき)な情緒(じょうしょ)、そして、与謝野鉄幹(よさのてっかん)との出会いによる晶子(あきこ)の至福(しふく)の情感と高揚(こうよう)した気分とが伝わってくる。(三句切れ)
※桜月夜(さくらづきよ)は「朧(おぼろ)月夜」「桜」を組み合わせた与謝野晶子の新造語。
※本作所収、歌集「みだれ髪」には、与謝野鉄幹との激(はげ)しい恋愛の過程で生み出された歌を多く収め、積極的に人間性を肯定し、恋愛感情や青春の官能を歌いあげている。
清らなる山の水かも蟹とると石をおこせば水の流らふ(島木赤彦)
・きよらなる やまのみずかも かにとると いしをおこせば みずのながろう
・何と清らかに澄(す)んだ沢の水であろう。蟹(かに)をとろうと水底(みなそこ、みなぞこ)の石をおこすと、澄みきった水の中で、さっと砂の流れてゆくのが見える。(二句切れ)
草の実のはぜ落つる音この谷のところどころに聞こえつつおり(斎藤茂吉)
・くさのみの はざおつるおと このたにの ところどころに きこえつつおり
・秋の静かな谷間(たにあい)の路(みち)を辿(たど)り、ふと歩みを止めると、辺りで時折(ときおり)、ピシッ…、ピチッ…という微(かす)かな音が聞こえてくる。一体何の音だろうと耳を澄(す)まして聞くと、それは、熟した草の実がはじけ落ちる音だった。山間(やまあい)の静かな、そして、ひっそりとした秋の風情である。(句切れなし)
くさふめばくさにかくるるいしずゑのくつのはくしゃにひびくさびしさ(会津八一)
・くさふめば くさにかくるる いしずえの くつのはくしゃに ひびくさびしさ
・今となっては歴史の時間の中に埋没(まいぼつ)し、姿をとどめない山田寺の跡地(あとち)を訪れ、生い茂る草を踏(ふ)み分けて歩いていると、ふと、私の乗馬靴(じょうばぐつ)の拍車(はくしゃ)が、何かに触れてこすれた音を立てた。それは、草に隠れて見えず、私の足元にあった山田寺の礎石(そせき)に当たって出た音だった。その乾いた音の、何と空(むな)しく、さびしい響きであったことだろう。(草ふめば草に隠るる礎の靴の拍車にひびく悲しさ)
・カ行音の繰り返しにより、響いてきた音のさびしさ、空しさがいっそうよく伝わってくる。(句切れなし)
※いしずゑ(え)… 奈良県桜井市山田の、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)が建立(こんりゅう)した山田寺跡地(あとち)に残る礎石(そせき)。
※拍車(はくしゃ)… 乗馬用の靴(くつ)のかかとにつける金具。かかとの側(かわ)に小さな歯車をつけ、それで馬の横腹を蹴(け)って馬を御(ぎょ)する。
※山田寺(やまだでら)…蘇我氏(そがし)一族であった蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)は宗家(そうけ)の蘇我入鹿(そがのいるか)と対立し、娘婿(むすめむこ)の中大兄皇子(なかのおおえのおうじ:後の天智天皇)について蘇我氏打倒に参画(さんかく)、改新政府の右大臣を務めたが、異母弟(いぼてい)蘇我日向(そがのひむか)により謀叛(むほん)の疑いをかけられ、649年、建造中の山田寺の仏殿において妻子一族と共に、失意のうちに自害して果てた。後に疑いが晴れ、山田寺は着工から45年を経てようやく完成したが、1187年に興福寺(こうふくじ)の僧兵(そうへい)によって焼き払われた。
※1982年、東面回廊跡(かいろうあと)の発掘(はっくつ)調査で西向きに倒壊(とうかい)した状態で屋根瓦(やねがわら)、縁石(ふちいし)、そしてほぼ原形のままの木製の連子窓(れんじまど)が発掘され、世界最古の木造建築である法隆寺よりもさらに半世紀も遡(さかのぼ)る木造建築物の遺物となった。
草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり(北原白秋)
・くさわかば いろえんぴつの あかきこの ちるがいとしく ねてけずるなり
・明るく広がる緑の若草の上で、赤い色鉛筆をナイフで削(けず)ると、芯(しん)の赤い粉が若草の葉にこぼれ落ちる。その鮮やかな赤い色のこぼれ落ちるさまを見ていると、何だか妙(みょう)にいとしく感傷的な気持ちになって、寝転がってそれを見続けながら色鉛筆を削ったことだ。若草のみずみずしい緑の色彩にうち重なってゆく鮮やかな赤が対照的である。(初句切れ)
※赤と緑とは反対色で、刺激を高める対照的な色どうしである。
葛の花踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり(釈迢空)
・くずのはな ふみしだかれて いろあたらし このやまみちを ゆきしひとあり
・葛(くず)の花が踏(ふ)みにじられて、そのなまなましい色を道ににじませてりる。めったに人が通らないようなこの草深い山道を、つい今しがた、私より先に通っていった人があるのだなあ。(三句切れ)
薬のむことを忘れて、ひさしぶりに、母にしかられしをうれしと思へる。(石川啄木)
・くすりのむことをわすれて ひさしぶりに ははにしかられしを うれしとおもえる
・病のための薬をつい飲み忘れていると、薬を飲まねばと母親が私を叱(しか)ってくれた。大人になって、こうして母親にしかられるのは久しぶりのことだが、親子の絆(きずな)、母親の深い情愛を感じ、母に叱られたことがうれしいとさえ思われたことだ。(句切れなし)
※啄木(たくぼく)の母は体の弱い啄木が丈夫に育つよう願い、生涯(しょうがい)卵と鶏肉(けいにく)を断ち、また晩年には自分の好きな茶を断って息子の平復(へいふく)を祈ったという。啄木が26歳で肺結核のため死去する一ヶ月前の明治45年(1912年)3月に亡(な)くなっている。
くれなゐのニ尺のびたる薔薇の芽の針やはらかに春雨の降る(正岡子規)
・くれないの にしゃくのびたる ばらのめの はりやわらかに はるさめのふる
・ニ尺ほど伸びたばらの赤い新芽に出たやわらかそうなとげを包むように、春雨が静かに、やさしく降り注いでいる。
・季節の推移(すいい)や生命感が伝わるとともに、いかにもやわらかでみずみずしい印象を与える歌である。(句切れなし)
※くれなゐ(い)… 紅色。
※二尺… 一尺は約30cm。
※針… とげ。
※「やはらかに」には、①薔薇の芽の「針のやわらかさ」と、②「春雨のやわらかに降るさま」の二つの意味をもたせてある。
※「の」の音の反復が、やわらかな印象とリズムを与えている。
心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ(西行)
・こころなき みにもあわれはしられけり しぎたつさわの あきのゆうぐれ
・俗人(ぞくじん)の感情を絶ち切った、出家僧(しゅっけそう)である私の身にも、鴫(しぎ)が飛び立つ水辺の秋の夕暮れのものさびいい風情には、しみじみとした情趣が感じられることだ。(三句切れ)
※心なき身… 俗人(ぞくじん)のような愛憎(あいぞう)悲喜(ひき)の感情をもたない僧侶(そうりょ)の身。出家によって一切の世間の煩悩(ぼんのう)を離れることから。
※あはれ… もののあはれ。しみじみとした情趣。
※沢(さわ)… 湿地帯。谷より浅く、広い。
※鴫(しぎ)… 夏から秋にかけて田や沢などにいる中型の渡り鳥で、くちばしと足が長い。羽音(はおと)が高い。
※立つ… 飛び立つ。
こころよく我にはたらく仕事あれそれを仕遂げて死なむとぞ思ふ(石川啄木)
・こころよく われにはたらく しごとあれ それをしとげて しなんとぞおもう
・貧しさや苦悩(くのう)、病など、我が身にふりかかるさまざまな困難のために、人は、時には己(おのれ)の理念に背いて生きざるをえないこともある。もし、今私に、自分の生涯(しょうがい)をかけて尽(つ)くすことの出来る仕事が天より与えられたなら、自己の信念に従って私は生き、そして、その仕事を全(まっと)うするために命を捧(ささ)げてもよい。それはまた、人間としての本望であろう。(三句切れ)
不来方のお城の草に寝ころろびて空に吸はれし十五の心(石川啄木)
・こずかたの おしろのくさに ねころびて そらにすわれし じゅうごのこころ
・盛岡城(もりおかじょう)の城跡(じょうせき)の草の中に寝転び、青く広い空を眺(なが)めながら、ふくらむ夢や希望をそこに託(たく)していた、十五才の私だったことだ。(句切れなし)
子どもらと手まりつきつつこの里に遊ぶ春日は暮れずともよし(良寛)
・こどもらと てまりつきつつ このさとに あそぶはるひは くれずともよし
・子どもたちと一緒に手まりをつきながら、この村里(むらざと)で楽しく遊ぶ春の一日だから、このままずっと暮れないでいてほしいものだ。(句切れなし)
子どもらは列をはみ出しわき見をしさざめきやめずひきいられ行く(木下利玄)
・こどもらは れつをはみだし わきみをし さざめきやめず ひきいられゆく
・先生に率いられた子どもたちが、お喋(しゃべ)りをしたりはしゃいだりしながら、列になって道を歩いている。列をはみ出している子もいれば、わき見をしている子もいて、随分(ずいぶん)と賑(にぎ)やかで楽しそうだ。作者は、無邪気(むじゃき)な子どもたちの様子をほほえましく見つめている。(句切れなし)
※さざめき… にぎやかな声や音。
この朝け霧おぼろなる木の影に日のけはいして鳥鳴きにけり(島木赤彦)
・このあさけ きりおぼろなる きのかげに ひのけはいして とりなきにけり
・今日の明け方は、見ると一面に霧(きり)が立ちこめている。霧の中に沈んでぼうっと霞(かす)んで見えていた木立(こだち)が、やがてぼんやりとその姿を浮き上がらせてきたのは、昇(のぼ)り始めた朝日の光を受けているからだろう。どこからともなく、鳥たちのさえずりも聞こえ始めてきた。(句切れなし)
※朝明(あさけ)… 古語で、夜明け方。
※おぼろ… ぼうっと霞むさま。
※影(かげ)… ものの姿、形。
※日の気配(けはい)… 何となく感じられる朝日の様子。
この三朝あさなあさなをよそほひし睡蓮の花今朝は開かず(土屋文明)
・このみあさ あさなあさなを よそおいし すいれんのはな けさはひらかず
・この三日間、朝には必ず美しく咲いていた睡蓮(すいれん)の花なのに、今朝はもう咲かない。美しくもはかない花の命がわびしいことだ。(句切れなし)
駒とめて袖うち払うかげもなし佐野のわたりの雪の夕ぐれ(藤原定家)
・こまとめて そでうちはらう かげもなし さののわたりの ゆきのゆうぐれ
・乗る馬を暫(しばら)くとめて、袖に降りかかった雪を払おうにも、その物陰(ものかげ)さえもないことだ。ここ佐野(さの)の辺りの、雪の降りしきる夕暮れ時よ。苦しさ、わびしさよりも優美で絵画的な印象を与える幽玄(ゆうげん)の趣(おもむき)の作である。(三句切れ)
※駒(こま)… 馬。
※陰(かげ)もなし… 家はもちろんのこと、物陰さえない。
※佐野(さの)… 和歌山県南部の地名。
※わたり… 辺(あた)り。また、「渡し」の意だとする説もある。
これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬもあふ坂の関(蝉丸)
・これやこの ゆくもかえるも わかれては しるもしらぬも おうさかのせき
・これがまあ、東国へ行く人も都へ帰って来る人も、ここで別れたり出逢(であ)ったり、また、互いに知る人、知らぬ人がここで逢(あ)うという、名に聞くあの逢坂(おうさか)の関(せき)なのだなあ。逢坂の関での人々の別れと出逢い、人生の断面を詠(うた)っている。(句切れなし)
※逢坂(おうさか)の関… 京都府と滋賀県の境の関所で、鈴鹿(すずか)の関(三重県)、不破(ふわ)の関(岐阜県)とともに昔の三関(さんかん)の一つ。
※蝉丸(せみまる)… 平安中期の歌人。伝記不明。盲目(もうもく)で琵琶(びわ)の名手であったという。
※掛詞(かけことば)… 「あふ」には、①動作「逢(あ)う」の意味と、②地名「逢坂(あふさか=おうさか)」の「逢(あふ=おう)」との二つの意味をもたせてある。
★小倉百人一首所収。
金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に(与謝野晶子)
・こんじきの ちいさきとりの かたちして いちょうちるなり ゆうひのおかに
・秋の淡(あわ)い夕陽に照らされて、まるで金色をした小さな鳥が舞うように、岡の銀杏(いちょう)の葉がはらりはらりと散ってゆく。(四句切れ)
■さ行
さくらさくらさくら咲き初め咲き終りなにもなかったような公園(俵万智)
・さくらさくら さくらさきそめ さきおわり なにもなかったようなこうえん
・桜の花の季節を迎えると、ようやく本格的な春である。誰もが桜の話題でもちきりで、今か今かと待ち望んでいた桜がようやくほころび、やがて散り果ててしまうと、桜を愛(め)でる人々であれほど賑(にぎ)やかだった公園が、何もなかったようにもの寂(さび)しい風情であることだ。
桜ばないのち一ぱい咲くからに生命をかけてわが眺めたり(岡本かの子)
・さくらばな いのちいっぱい さくからに いのちをかけて わがながめたり
・儚(はかな)くも可憐(かれん)な桜の花よ。生命(いのち)に燃え、生命の色を咲かせる桜の花よ。その美しさは、生命そのものの美しさ。私は生命を見つめる。私自身の生命をかけて、桜の花の生命を見つめる。(句切れなし)
さざなみや志賀の都はあれにしを昔ながらの山ざくらかな(平忠度)
・さざなみや しがのみやこは あれにしを むかしながらの やまざくらかな
・志賀(しが)の都は荒れ果てて見る影もないが、長良山(ながらやま)の桜は、昔のままに美しく咲き匂(にお)っていることだ。(句切れなし)
※志賀の都… 天智(てんじ)天皇の御代(みよ)、大津(滋賀県の琵琶湖のほとり)に作られた都。壬申(じんしん)の乱で滅ぼされた。
※掛詞(かけことば)… 「昔ながら」には、「昔のまま」と「長等山(ながらやま)」と、二つの異なる意味をもたせてある。
※この歌を収めた千載(せんざい)和歌集を撰進(せんしん)した時、平氏は朝敵(ちょうてき)となっていたので平忠度(たいらのただのり)の名を伏(ふ)せて「よみ人知らず」として収録(しゅうろく)した。
※「さざなみや」は「志賀(しが)」にかかる枕詞(まくらことば)。
寂しさはその色としもなかりけり真木立つ山の秋の夕ぐれ(寂連)
・さびしさは そのいろともし なかりけり まきたつやまの あきのゆうぐれ
・このもの寂(さび)しさというのは、特に景色のどの色合いのせいというわけでもないのだなあ。一年中真木(まき:杉・ヒノキなどの常緑樹)の緑に覆(おお)われて、秋らしさを感じさせるわけでもないこの山の、何とも言えない夕暮れ時のもの寂しさよ。(三句切れ)
※その色としも… 特にどの色のせいというわけでも。
※真木(まき)… 槇(まき)とも。杉やヒノキなどの常緑樹。
「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ(俵万智)
・さむいねと はなしかければ さむいねと こたえるひとの いるあたたかさ
・「寒いね」と、何気(なにげ)ないひとときに、何気なくあなたと交わした、何気ない言葉。真冬の寒さを共感し合える人が、こうして私のそばにいてくれることに、私は幸せと喜びを感じずにはいられない。
沢がにをもてあそぶ子に銭くれて赤きたなそこを我は見たり(釈迢空)
・さわがにを もてあそぶこに ぜにくれて あかきたなそこを われはみたり
・夏、谷川で沢蟹(さわがに)をつかまえて、手に持って遊んでいる子どもがいたので、お金を与えてその小さな蟹(かに)を譲(ゆず)ってもらった。そして、左右で大きさの違った赤いはさみやその動きを興味深くまじまじと見て、その面白さを味わった。民俗(みんぞく)学者として各地の風俗(ふうぞく)や伝統、文化などを調査する旅の途上でのひとこまであろう。(句切れなし)
※沢蟹(さわがに)… 北海道を除く各地の谷川など清流にすむ。大きさは2~3cm。はさみは普通、右側のものが大きい。イシガニ。
※もてあそぶ… 手に持って遊ぶ。いじくる。
※掌(たなそこ)…古語で、手のひら。ここでは蟹(かに)のはさみ。
志賀の浦や遠ざかりゆく波間より氷りて出づる有明の月(藤原家隆)
・しがのうらや とおざかりゆく なみまより こおりていずる ありあけのつき
・琵琶湖(びわこ)の志賀(しが)の浦(うら)の、岸から凍(こお)りはじめてだんだん沖の方へと遠ざかってゆく波間から、凍ったように冴(さ)えきった光を放って出た夜明けの月の幽寂(ゆうじゃく)な光であることよ。(句切れなし)
※志賀(しが)の浦(うら)や… 志賀の浦の。志賀の浦は琵琶湖西岸、大津市の北の辺り。
※幽寂(ゆうじゃく)… 奥深く、もの静かなこと。
しきしまのやまと心を人とわば朝日ににほふ山ざくら花(本居宣長)
・しきしまの やまとごころを ひととわば あさひににおう やまざくらばな
・大和心(やまとごころ=日本人の気性(きしょう))とはどういうものかと人に尋(たず)ねられたならば、それは、朝日に美しく照り映えた山桜の花のようなものであると答えよう。(句切れなし)
※大和心(やまとごころ)… 日本人の気性(きしょう)。
※にほふ(におう)… 色が照り映える。
※「しきしまの」は「大和(やまと)」にかかる枕詞(まくらことば)。
しずかなる峠をのぼり来し時に月の光は八谷を照らす(斎藤茂吉)
・しずかなる とうげをのぼり こしときに つきのひかりは やたにをてらす
・静かな箱根の峠を登りきったその時に、ふと見ると、白く煌煌(こうこう)とした月の光が、眼下の谷という谷を明るく照らしだしていたことだ。(句切れなし)
※八谷(やたに)… 「多くの谷」の意。
自転車のカゴからわんとはみ出してなにか嬉しいセロリの葉っぱ(俵万智)
・じてんしゃの かごからわんと はみだして なにかうれしい せろりのはっぱ
・私が乗っている自転車のカゴに入れた新鮮なセロリが、「わん」と勢(いきお)いよくはみ出して揺(ゆ)れている。期待や喜びに胸を躍(おど)らせているように、何か楽しげに思えたことだ。
死というは日用品の中にありコンビニで買う香典袋(俵万智)
・しというは にちようひんの なかにあり こんびにでかう こうでんぶくろ
・人の死は人生における厳粛(げんしゅく)な出来事ではあるが、存命(ぞんめい)する者たちにとって、死との関わりは、死を迎えた者に対する儀礼(ぎれい)をもってしか経験出来ないことがある。儀礼に必要なその香典袋(こうでんぶくろ)も、日用品を広く扱うコンビニへ行けば、私たちは簡単に手に入れることが出来る。
・私たちにとって死とは、日用品の中にあり、日常の、商品を選択する行為の一つに表れているだけのものに過ぎなくなっているのかもしれない。
※香典袋(こうでんぶくろ)… 死者の霊前(れいぜん)に香(こう:よいにおいを出すたきもの)のかわりとして供える金品を包むための袋。
信濃路はいつ春にならん夕づく日入りてしまらく黄なる空の色(島木赤彦)
・しなのじは いつはるにならん ゆうづくひ いりてしまらく きなるそらのいろ
・信濃路(しなのじ)の春はおそい。草木の芽吹きも花の季節も、まだ先のことである。西の空は、夕日が沈んでしばらくの間、黄色に染まっている。ただ、やわらかな黄色に染まったその夕映(ゆうば)えだけが、春の始まりを告げている。信濃の国には、いつ春がやってくるのだろう。重い病に臥(ふ)した私は、祈りににた思いで、彼方の夕映えを見つめる。(二句切れ)
※この作歌後の翌月、作者は四十九歳にて死去(しきょ)。
死に近き母に添寝しんしんと遠田のかわず天に聞こゆる(斎藤茂吉)
・しにちかき ははにそいねの しんしんと とおだのかわず てんにきこゆる
・夜、危篤(きとく)に陥(おちい)った私の母の傍(そば)に寄り添(そ)って寝ていると、自分を生み、育て、ずっと見守り続けていてくれた母親の深い愛情と、そしてささやかな母の生涯(しょうがい)が思われ、深い悲しみが胸の底からつきあげてくる。夜がしんしんと深まるにつれ、悲しみも胸いっぱいになり、あたりの静けさを破って遠くの田で鳴く蛙(かえる)の声は、天にしみいるように響いている。(句切れなし)
※「のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ屋梁(はり)にいてたらちねの母は死にたまふなり」の項を参照のこと。
しばらくを三間うちぬきて夜ごと夜ごと子らが遊ぶに家わきかへる(伊藤左千夫)
・しばらくを みまうちぬきて よごとよごと こらがあそぶに いえわきかえる
・ひとときの間、三つの部屋を打ちとおして開け放していると、子どもたちが毎夜毎夜遊び回るので、家の中はいつになく賑(にぎ)やかにわきかえっていることだ。(句切れなし)
※三間(みま)… 三つの部屋。
四万十に光の粒をまきながら川面をなでる風の手のひら(俵万智)
・しまんとに ひかりのつぶを まきながら かわもをなでる かぜのてのひら
・四万十川(しまんとがわ)、そのゆったりとした川の流れに日差しが明るく降り注ぎ、反射した陽光がきらきらと美しく輝いている。そよ風が、おだやかな川面(かわも)をやさしくなでるように吹くと、川面には無数の光の粒が撒(ま)かれ、生き生きと煌(きらめ)いている。
※四万十(しまんと)… 四万十川(しまんとがわ)。高知県南西部を流れ、土佐湾に注ぐ川。豊富な自然に育まれ、たくさんの水生生物が見られ、それに関わる珍しい漁法なども現存している。 本流に大規模なダムが建設されていないことから、「日本最後の清流」と呼ばれる。
霜やけの小さき手してみかんむく我が子しのばゆ風の寒きに(落合直文)
・しもやけの ちいさきてして みかんむく わがこしのばゆ かぜのさむきに・霜焼けの小さな手をして蜜柑(みかん)をむいている我が子が、しみじみと思い出されることだ。真冬のこの風の寒さに、いったいどうしていることだろう。(四句切れ)
白雲に羽うちかわしとぶ雁の数さえ見ゆる秋の夜の月(よみ人知らず)
・しらくもに はねうちかわし とぶかりの かずさえみゆる あきのよのつき
・夜の空高く、白雲(しらくも)のある辺りを、互いに羽をすれすれに交えて飛んでいる雁(かり)の、その姿だけでなく数さえもが一つ一つ見えるほどに明るい、秋の夜の月の美しさよ。(句切れなし)
白雲のうつるところに小波の動き初めたる朝のみづうみ(与謝野晶子)
・しらくもの うつるところに さざなみの うごきそめたる あさのみずうみ
・だんだんと明るさを増してゆく朝方、湖面を見つめていると、風が起こったのだろうか、白雲(しらくも)の姿がおぼろげに映っている辺りに、小波(さざなみ)が立ち始めている。湖の目覚めのような情景が、朝の始まりを印象づけている。(句切れなし)
白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ(若山牧水)
・しらとりは かなしからずや そらのあお うみのあおにも そまずただよう
・白鳥(しらとり)は悲しくはないのだろうか。空の青さにも海の青さにもとけ合うことなく、その白い姿のまま漂っている。ただ一面の青い世界にありながら、それに染められることなく孤高(ここう)を貫いているかのような白鳥の姿に、作者の、自身を哀(かな)しみ愛(いと)しむ思いを託(たく)して詠(うた)っている。また、自己の芸術追究への覚悟も伝わってくる。(二句切れ)
※白鳥(しらとり)… ここでは、かもめのこと。
※悲しからずや… 「悲しくはないのだろうか、いや、きっと悲しいことだろう」の意。
※反語… 疑問文の形をとりながら、実は強い否定の意を表す。ここでは、否定文が肯定の意を強めている。
白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝はつめたき水くみにけり(長塚節)
・しらはにの かめこそよけれ きりながら あさはつめたき みずくみにけり
・清らかな白埴(しらはに)の瓶(かめ)はよいものだ。早朝、つるべ井戸の傍(そば)で、冷たい井戸の水を、深くたちこめた朝霧(あさぎり)といっしょにこの瓶に汲(く)んだことだ。「白、霧、朝、冷、水」といった共通性のある言葉の使用によって、ひんやりとして静かに冴(さ)え澄(す)んだものを感じることができる。(二句切れ)
※白埴(しらはに)の瓶(かめ)… 白い釉をかけた焼き物の瓶。
銀も金も玉も何せんにまされる宝子にしかめやも(山上憶良)
・しろがねも くがねもたまも なにせんに まされるたから こにしかめやも
・銀も金も宝石も何になろうか。子どもに勝(まさ)る宝などありはしない。(三句切れ)
水平線を見つめて立てる灯台の光りては消えてゆくもの思い(俵万智)
・すいへいせんを みつめてたてる とうだいの ひかりては きえてゆくものおもい
・浜辺の闇(やみ)に、ぽつんと佇(たたず)むように立つ丘(おか)の上の灯台。何があるでもない、誰が待つでもない、遥(はる)か水平線の闇を見つめ、静かに明滅(めいめつ)を繰り返す。浮かんでは消える、虚(うつ)ろにも似た幻影(げんえい)と、私のもの思い。
鈴鹿山うき世をよそに振りすてていかになり行くわが身なるらむ(西行)
・すずかやま うきよをよそに ふりすてて いかになりゆく わがみなるらん
・このように世の中を振(ふ)り捨てて出家し、この鈴鹿山(すずかやま)を越えて旅してゆく自分の身は、今後どのようになっていくのであろうか。(句切れなし)
※鈴鹿山(すずかやま)… 三重県鈴鹿市付近の鈴鹿山脈の総称。東西交通の要所に当たる。
鈴鳴らす橇にか乗らむいないな先づこの白雪を踏みてか行かむ(若山牧水)
・すずならす そりにかのらん いないなまず このしらゆきを ふみてかゆかん
・さあ、馬につけられた鈴を鳴らしながら走る橇(そり)に乗って、いよいよ出発しよう。いや、その前に、どこまでも続くこの真っ白い雪を、自分の足で踏んで確かめながら歩いてみたい。
・南国宮崎県生まれの牧水(ぼくすい)には、北国の雪への思いはひとしおのものがあったのだろう。
※大正5年、東北旅行での歌。
戦争の話やめよと隣室の母するどければみな息ひそむ(作者不詳)
・せんそうの はなしやめよと りんしつの ははするどければ みないきひそむ
・何気なく戦時を話題に兄弟たちが語り合っていたところ、突然、母の、「戦争の話はするな」という、重く厳しい声が隣室(りんしつ)から響いた。忌(いま)わしい戦争の記憶が甦(よみがえ)るのに堪(た)えられなかった母の私たちを諌(いさ)める鋭(するど)い声に、皆、息をひそめて黙るしかなかったことだ。(句切れなし)
千メートル泳ぎ切りたる賞状を病気の父は笑みてうなずく(作者不詳)
・せんめーとる およぎきりたる しょうじょうを びょうきのちちは えみてうなずく
①千メートルの遠泳を泳ぎ切って、誇(ほこ)らしい気持ちで、もらった賞状を病床(びょうしょう)のお父さんに見せた。お父さんは、ただ笑(え)みを浮かべて黙ってうなづいて、ぼくの健闘をたたえてくれた。(句切れなし)
②我が子が千メートルの遠泳を泳ぎ切って、病床(びょうしょう)にある私に、もらった賞状を誇(ほこ)らしげに見せてくれた。私は、ただ笑(え)みを浮かべて黙ってうなづいて、我が子の健闘をたたえてやったことだ。(句切れなし)
袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ(紀貫之)
・そでひじて むすびしみずの こぼれるを はるたつきょうの かぜやとくらむ
・かつて夏の暑い日に、袖が濡(ぬ)れながらもすくって遊んだ水が、冬の寒さに凍(こお)っているのを、立春となった今日の春の風が解かしているだろうか。(句切れなし)
※袖(そで)ひじてむすびし水… 袖が濡(ぬ)れるという状態ですくった水。
※春立つ…立春の。
そのかみの神童の名のかなしさよふるさとに来て泣くはそのこと(石川啄木)
・そのかみの しんどうのなの かなしさよ ふるさとにきて なくはそのこと
・昔、私がまだ子どもだった頃、人からは神童などと呼ばれ将来を期待されたものだったが、貧しさのため辛い日々を送っている今のこの我が身を思うと、神童などという呼び名の、何と切なく空しく響くことだろう。ふるさとに帰ってきて涙するのは、ただそれを思ってのことだ。(三句切れ)
※そのかみ… 昔。その当時。
その子二十櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな(与謝野晶子)
・そのこはたち くしにながるる くろかみの おごりのはるの うつくしきかな
・鏡に映った、今二十歳の私。髪(かみ)を櫛(くし)で梳(と)かせば、流れ、ゆらぐ、その艶(つや)やかな黒髪の、誇(ほこ)りに満ちた私の青春の、何と美しいことよ。(初句切れ)
※青春のただなか、人生の春を生きる若き作者が、女性としての生身(なまみ)の美しさを堂々と歌い上げている。明治という時代にあって、女性を強く縛(しば)っていた当時の封建(ほうけん)道徳に対する反骨(はんこつ)が自由な新しい感情表現によって描かれている。
※晶子(あきこ)は後に、初句を「わが二十」と改めている。
それとなく郷里のことなど語り出でて秋の夜に焼く餅のにほひかな(石川啄木)
・それとなく ふるさとのことなど かたりいでて あきのよにやく もちのにおいかな
・静かな秋の夜、人と語り合っているうちに、それとなく私は、岩手の懐(なつ)かしい自分の故郷のことなどを、しみじみと語り出してしまう。餅(もち)を焼くにおいも、望郷の念をいっそう募(つの)らせることだ。静かに、寂(さび)しく、秋の夜は更(ふ)けてゆく。(句切れなし)
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。