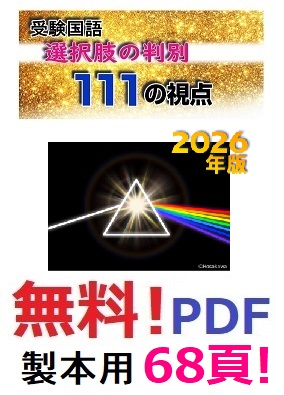中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川
■難関中学 受験対策
■国語読解・記述指導
■東京23区・千葉県北西部
■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。
■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。
■お問い合わせ
■047-451-9336
■午前10時~午後2時
■まずはお電話でお問い合わせください。
■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。
★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!
■俳句・短歌の基本
■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』
■最新版がダウンロードされたかご確認ください。
■記事
・B5正味68ページ(B4両面18枚/表紙1枚含む)
・本編約110,000字
■PDFデータ量
・7.79MB
■プリンター設定
・B4用紙
・印刷の向き(横)
・両面印刷
・短辺とじ
※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。
■製本
・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。
・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。
■補足
・本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。
・本資料は国語の読解問題における選択肢を思考力や論理力、分析力や検討力等によって正しく判別するための育成教材であるため、コツ、裏技といった安直な解決法は記載していません。(※ただし、一部ネタも含みます)
・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。
■頒布自由
・本資料(PDFデータ、または冊子)を必要とする各人、各所への頒布は自由です。
【目次】
■俳句とは
■短歌とは
■旧暦
■月の古名(和風月名)
■いろは歌
【教材・資料:無料PDF】
■季語 一覧表 (B4・2枚)
■季語 写真 (B4・3枚)
■枕詞 一覧表(B4・1枚)
■俳句の通釈①:「あ行」~「さ行」(123句)
■俳句の通釈②:「た行」~「わ行」(119句)
■短歌の通釈①:「あ行」~「さ行」(105首)
■短歌の通釈②:「た行」~「わ行」(126首)
論理パズル
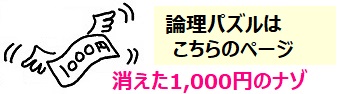
■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。
各種論理
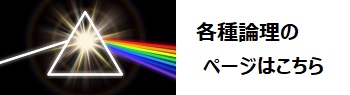
■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。
俳句とは
■俳句とは
・俳句は「五・七・五」の十七音で詠(よ)まれる世界で最も短い定型詩です。季語(季節を表す語)を一つ必ず読み込む決まりとなっており、江戸時代に松尾芭蕉によって大成されました。
〈例〉
・古池や 蛙飛びこむ 水の音(松尾芭蕉) ※季語は蛙、季節は春
※句の意味は、「静かな、ひっそりとした古池に佇(たたず)み、しみじみとした情趣に浸(ひた)っていた。と、その時、一匹の蛙(かえる)が池に飛び込む小さな音が聞こえた。辺りの静けさを破ったその一瞬の水音がした後には、以前にもまして深い静寂の世界が広がったことだ。」です。
※蛙(かわず)について…「蛙」は春先に冬眠から覚め、最初の繁殖期を迎えて盛んに鳴くことから春の季語とされている。また、春先にその年初めて目にする蛙を「初蛙(はつかわず)」といい、これが蛙の季語を春とする由来となっているとする説もある。ただし、「青蛙(あおがえる)」や「雨蛙(あまがえる)」は夏の季語なので注意。
※定型詩…五音や七音など、一定の音数で組み立てられた詩。
※併せて『詩の種類と表現技法』をご参照ください。
①構成要素
・「五・七・五」の各句を「初句」「二句」「結句」と呼び分けます。また、それぞれを「上五、または初五」、「中七」、「下五、または座五」などといった呼び方をする場合もあります。
②音数の数え方
・「音数」は文字を平仮名に改めて数えます。
〈例〉
・立身出世(りっしんしゅっせ)…七音(り・っ・し・ん・しゅ・っ・せ)
・ジャッキー・チェン… 六音(じゃ・っ・き・い・ちぇ・ん)
(1)拗音(ようおん):「きゃ・しゅ・ちょ」などは一音で数える。
(2)特殊音(とくしゅおん):外来語に由来する「ファ・トゥ・シェ」などは一音で数える。
(3)促音(そくおん):小さな「っ」は一音で数える。
(4)撥音(はつおん):「ん」は一音で数える。
(5)長音(ちょうおん):「ー」は一音で数える。また、「おかあさん」の「あ」や「おねえさん」の「え」なども長音としてやはり一音で数える。(オカーサン・オネーサンに同じ)
※(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の五種全ての音が含まれている「ジャッキー・チェン」の語で音数の数え方をしっかりと確認しておこう。「ファッションショー」の語でもいいですね。
③破調
音数が十七音を越える場合は「字余り」、不足する場合を「字足らず」といいます。「字余り」や「字足らず」のように音数に多少が出ることを「破調(はちょう)」といいます。
(1)字余りの例
・目には青葉 山ほととぎす 初がつを(山口素堂)
※「六・七・五」の十八音で詠まれている「字余り」の句です。
※句の意味は、「目には染(し)み入るような青葉の色がすがすがしく、耳には爽(さわ)やかなホトトギスの声を耳にしながら、口には初物(はつもの)の生き生きとした鰹(かつお)を賞味できる、すばらしいこの初夏を迎えたことだ。」です。
(2)字足らずの例
・兎(うさぎ)も片耳(かたみみ)垂(た)るる大暑(たいしょ)かな(芥川龍之介)
※「四・七・五」の十六音で詠まれている「字足らず」の句です。
※句の意味は、「鬱陶(うっとう)しい梅雨が終わったかと思えば、今は日照り激しい酷暑の時節を迎え、兎の片耳さえ力が入らず垂れ下がるほどの、うだるようなその暑さであることだ。」です。
■「五・七・五」の定型をわざと「五・五・七」や「七・五・五」、「六・六・五」のように変えて詠む「破調」もあります。「五・七・五」の各句の「切れ目」と「文節の終わり」とが合致しないため、これは「句またがり」となります。
〈『五・五・七』の破調例〉
・海暮(くれ)て 鴨(かも)の声 ほのかに白し(松尾芭蕉)
※「うみくれて・かものこえ・ほのかにしろし」とすることで、冬の海の澄んで寒々とした空気や、鴨の声を心に描きつつ耳を傾ける芭蕉の落ち着いた心持ちといったものがしみじみと醸(かも)し出されます。「海暮れて・ほのかに白し・鴨の声(五・七・五)」とした場合と比べて印象の違いを比べてみましょう。
※句の意味は、「日が暮れて暗くなった冬の海辺にいると、沖合いからほのかに鴨(かも)の鳴く声が聞こえてくる。夕闇のため姿は見えないが、じっとその声に聞き入っていると、この寒々とした海辺に響く鴨の鳴き声までがほの白く感じられることだ。」です。
④句切れ
・文としての意味が途切れる所を「句切れ」といいます。最初の五音で意味的な切れ目となる場合を「初句切れ」、七音までで意味が切れる場合を「二句切れ」、そして、句全体で一文として構成されている場合を「句切れなし」といいます。一般には「マル(句点)が打てる所が句切れ」といった基準が提示されますが、そもそもどこにマルが打てるかの判断が小学生には困難な場合が少なくないようです。やはり句の意味を考え、感じ、味わうという本来の学習を疎(おろそ)かにしてはいけません。
〈例〉
(1)初句切れ:閑(しず)かさや。/岩にしみいる 蝉(せみ)の声(松尾芭蕉)
(2)二句切れ:柿食へば 鐘(かね)が鳴るなり。/法隆寺(正岡子規)
(3)句切れなし:遠山(とおやま)に 日の当たりたる 枯野(かれの)かな。/(高浜虚子)
※中には初句の途中や二句の途中、あるいは結句の途中で切れている「中間切れ」の句もあります。
〈例〉
(1)上五(初句)の中間切れ:寒(さむ)や。/吾(わ)がかなしき妻を 子にかへす(石田波郷)(2)中七(二句)の中間切れ:やせ蛙負けるな。/一茶これにあり(小林一茶)
(3)下五(結句)の中間切れ:算術の少年しのび泣けり。/夏(西東三鬼)
⑤切れ字
「かな、けり、や」などの語のことで、次の大切な二つの働きがあります。
(1)感動の集中を表す。
(2)そこで「句切れ」となる。
〈例〉
・古池や 蛙飛びこむ 水の音
※この句では、「古池や」の部分(初句)に、「古くて静かな池であることだよ…」といった、しみじみとした「感動」が込められています。また、意味上も初句で切れるので、「初句切れ」となります。
※「切れ字」には「かな・けり・や」以外にも多くの種類があります。基本として「かな・けり・や」の三種を覚えたら、他の主要な切れ字を含め、「かな・けり・や・ぞ・たり・なり・よ・か・も・し」のように順に並べ、リズムよく声に出して読んで覚えてみてください。
⑥季語
・俳句は季節感の文学ともいわれ、俳句を味わうには何よりも季節をとらえることが大事です。春、夏、秋、冬の季節を表す言葉が季語で、それぞれの季語がどの季節に属するかは約束によって定められています。 また、短歌には季語を詠み込むという決まりはありませんが、俳句には季語を必ず一つ詠(よ)み込むのが作法となっています。
〈例〉
・旅に病んで夢は枯野(かれの)をかけめぐる(松尾芭蕉:元禄七年(1694年10月8日))
※季語は枯野、季節は冬。
※句の意味は、「九州への旅の途中、大坂(大阪)で病床に臥(ふ)してしまった私だが、夢に見るのは、今なお旅人として寂(さび)しい枯野(かれの)の中を颯爽(さっそう)と旅し流離(さすら)う、私自身の姿であったことだ。」です。松尾芭蕉が亡くなる四日前に詠んだ、彼にとって生涯最後の句となりました。
※季語は「季題」ともいいます。
※新年の季語… 春の季語の中で「元旦」「初日の出」「若菜」「賀状」「鏡もち」などの景物を特に「新年の季語」と分類する場合があります。
※歳時記(さいじき)… 俳句で用いられる季語を季節ごとに分類し、解説と例句を添えた書物のことです。「俳句歳時記」「季寄せ(きよせ)」などとも呼びます。
■季重なり(きかさなり・きがさなり)
・ 「季重ね(きかさね・きがさね)」ともいいます。一句に季語を一つだけ詠み込むのが俳句の作法ですが、二つ以上の季語を詠み込んだ場合、これを季重なり(季重ね)といいます。季節特有の風物を表す季語を複数用いると季節感がぼやけてしまうので、これを嫌います。季重なりとなっている場合は、特にその句の主題(感動の中心)となっているほうを季語としてとります。
〈例〉
・啄木鳥(きつつき:秋)や落葉(おちば:冬)をいそぐ牧の木々
※句の意味は、「すがすがしい晩秋の高原の牧場に、啄木鳥(きつつき)がせわしなく幹をつつく音が響いている。牧場の木々は、まるで冬支度を急いでいるかのように、あわただしく葉を散らしてゆく。」です。
※落ち葉散りゆくさびしい晩秋の高原に、まるで冬への移り変わりを急かすかのようにせわしなく響きわたる啄木鳥の幹を叩く音。そこに過ぎゆく秋を惜しむ作者のしみじみとした気持ちが込められていますから、主題となる季語は「啄木鳥」となります。「啄木鳥」に切れ字の「や」が用いられていることも手がかりとなります。
※「落葉・落ち葉(冬)」や「つばめ(春)」、「虫(秋)」など、季節の境目に当たる風物は特に小学生にとっては判断に迷う場合が多い。日がな一日机に向ってばかりいるのではなく、普段から季節の移り変わりやその風物にも関心を持ち、人と人との関わりを大切にし、視野を広げ、世の中の動きにも目を向け、感じ、考える姿勢が大切です。それこそが本当の意味での勉強だと言えます。
⑦無季自由律
・正岡子規の没後、自然主義の影響を受け、季語を無視し、従来の五七五の定型に制約を受けず自由な音律で制作しようとする新形式を河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)が試みました。この新傾向運動は碧梧桐の門下である荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)らによっても進められ、明治末年の口語自由律俳句の運動へと繋がります。口語自由律俳句の運動は、瞬間の印象や情緒を直接口語で表現しようとしたものでしたが、形式上の変革が急であったため、尾崎放哉(おざきほうさい)、種田山頭火(たねださんとうか)らが活躍した大正から昭和初期以降は大衆化しないうちに衰退していきました。
〈例〉
(1)犬よちぎれるほど尾をふってくれる(尾崎放哉)
※句の意味は、「犬よ、孤独な私を迎えるように、精一杯尾を振ってくれている。ちぎれるほどに、喜んでこの私のために尾を振ってくれている。」です。定型を無視し、季語も用いられていません。
(2)咳(せき)をしても一人(尾崎放哉)
※句の意味は、「部屋で「ごほん、ごほん」と咳(せき)をした。しかしその咳の音は、部屋の中の静寂(せいじゃく)にたちまち飲み込まれてしまった。誰がこの私を心配してくれるでもない、たった一人私だけがいるこの部屋の、恐ろしいほどの静寂の中に。」です。「咳」は冬の季語ですが、作者はこれを季語として作品に用いているわけではありません。
⑧俳句の数え方
・俳句の作品は一句、二句と数えます。短歌の場合は一首、二首と数えるので、間違えないようにしよう。
⑨短歌と俳句の違い
・和歌に「長歌」という詩形があり、それに対する詩形が「短歌」です。短歌は「五・七・五・七・七」の三十一音で詠まれる日本古来の定型詩で、俳句や川柳、狂歌などの原型となりました。奈良時代に編纂(へんさん)された『万葉集』には多くの優れた作品が収められています。俳句には季語を一つ必ず詠み込むという決まりがありますが、短歌にはそのような決まりはありません。
〈例〉
・あをによし 奈良の都は咲く花の にほふがごとく 今盛りなり(小野老:おののおゆ)
※歌の意味は、「奈良の都、平城京は、咲く花が色美しく照り映(は)えるように、今やまことに繁栄(はんえい)の極(きわ)みであることだ。」です。
※長歌とは、「五・七・五・七…」を何度か繰り返し、最後に「七で結ぶ」詩形のことです。
【関連ページ】
■俳句:季語一覧表
■短歌:枕詞 一覧表
【教材・資料:無料PDF】
■季語 一覧表 (B4・2枚)
■季語 写真 (B4・3枚)
短歌とは
■短歌とは
・和歌に「長歌」という詩形があり、それに対する詩形が「短歌」です。短歌は「五・七・五・七・七」の三十一音で詠(よ)まれる日本古来の定型詩で、俳句や川柳、狂歌などの原型となりました。奈良時代に編纂(へんさん)された『万葉集』には多くの優れた作品が収められています。短歌には、「たらちねの」や「くさまくら」などのような、特定の語を修飾し、歌の調子を整えるための「枕詞(まくらことば)」が用いられることがあります。俳句には季語を必ず詠み込まなければならないという決まりがありますが、短歌には季語や枕詞を必ず詠み込まなければならないという決まりは特にありません。
〈例〉
・あをによし 奈良の都は咲く花の にほふがごとく 今盛りなり(万葉集)
※読み方は「あおによし・ならのみやこは・さくはなの・におうがごとく・いまさかりなり」で、「五・七・五・七・七」の定型どおりに詠まれています。
※歌の意味は、「奈良の都、平城京は、咲く花が色美しく照り映(は)えるように、今やまことに繁栄(はんえい)の極(きわ)みであることだ。」 です。
※和歌とは、中国の漢詩に対し、日本固有の形式による大和歌(やまとうた)を意味する詩の総称です。奈良時代には「短歌」以外に「長歌」や「旋頭歌(せどうか)」、「仏足石歌(ぶっそくせきか)」などの和歌がありましたが、後には短歌しか詠まれなくなり、和歌といえば短歌のことを指すようになりました。
※長歌とは、「五・七・五・七…」を何度か繰り返し、最後に「七で結ぶ」詩形のことです。また、旋頭歌は「五・七・七・五・七・七」、仏足石歌は「五・七・五・七・七・七」の形式で詠まれました。
※定型詩…五音や七音など、一定の音数で組み立てられた詩。
※併せて『詩の種類と表現技法』もご参照ください。
①構成要素
・「五・七・五・七・七」の五つの句を上から順に「初句・二句・三句・四句・結句」と呼び分けます。また、全体を前半と後半に分け、「五・七・五」の部分を「上(かみ)の句」、「七・七」の部分を「下(しも)の句」といいます。
②音数の数え方
・「音数」は文字を平仮名に改めて数えます。
〈例〉
・立身出世… 七音(り・っ・し・ん・しゅ・っ・せ)
・ジャッキー・チェン… 六音(じゃ・っ・き・い・ちぇ・ん)
(1)拗音(ようおん):「きゃ・しゅ・ちょ」などは一音で数える。
(2)特殊音(とくしゅおん):外来語に由来する「ファ・トゥ・シェ」などは一音で数える。
(3)促音(そくおん):小さな「っ」は一音で数える。
(4)撥音(はつおん):「ん」は一音で数える。
(5)長音(ちょうおん):「ー」は一音で数える。また、「おかあさん」の「あ」や「おねえさん」の「え」なども長音としてやはり一音で数える。(オカーサン・オネーサンに同じ)
※(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の五種全ての音が含まれている「ジャッキー・チェン」の語で音数の数え方をしっかりと確認しておこう。「ファッションショー」の語でもいいですね。
※ジャッキー・チェン:香港出身の映画俳優・監督・スタントマン。中国武術(クンフー)を駆使したアクション映画等で世界的に知られる。
※短歌では三十一音、つまり平仮名に改めて三十一文字使われることから、短歌のことを「三十一文字(みそひともじ)」とも呼びます。
③破調
・音数が三十一音を越える場合は「字余り」、不足する場合を「字足らず」といいます。「字余り」や「字足らず」のように音数に多少が出ることを「破調(はちょう)」といいます。
(1)字余りの例
・ふるさとの 訛(なま)りなつかし 停車場(ていしゃば)の 人ごみの中に そを聴きにゆく(石川啄木)
※読み方は、「ふるさとの・なまりなつかし・ていしゃばの・ひとごみのなかに・そをききにゆく」で、「五・七・五・八・七」の三十二音で詠まれている「字余り」です。「に」が加わることで、故郷への思いやさびしさがいっそう強く伝わってきます。
※歌の意味は、「ふるさとを離れ、ずっと東京で暮らしていると、故郷岩手のお国なまりがたまらなく懐(なつ)かしくなることがある。ある時私は、故郷とを列車で結ぶ上野駅の人ごみの中に、お国なまりの言葉をわざわざ聴きに行ったことだ。」です。
(2)字足らずの例
・群がれる 蝌蚪(かと)の卵に 春日さす 生(うま)れたければ 生れてみよ(宮柊二)
※読み方は、「むらがれる・かとのたまごに・はるひさす・うまれたければ・うまれてみよ」で、「五・七・五・七・六」の三十音で詠まれている「字足らず」です。「生まれてみよ」と命令調で強く言い切ることで、小さな命に対する愛情や確信が強く伝わってきます。
※歌の意味は、「春先の水辺を歩いていると、清く澄んだ水の中に蛙(かえる)の卵が沈みかたまっているのを見つけた。春の明るい陽の光に守られるようにして、無数にある黒い粒の一つひとつが、穏やかな心持ちで、静かに、安らかに眠っているかのようだ。一つひとつの小さな命よ、やがてその命の光を発散させたいならば、自らの意志をもって、力強く泳ぎ出よ。そして、生きてみせよ。」です。
④句切れ
文としての意味が途切れる所を「句切れ」といいます。「初句」に意味上の切れ目が来る場合を「初句切れ」、二句に切れ目が来る場合を「二句切れ」、順に「三句切れ」、「四句切れ」といい、歌全体で一文として構成されている場合は「句切れなし」といいます。
〈例〉
(1)初句切れ
・海恋し。/潮の遠鳴り 数へては 少女(おとめ)となりし 父母(ちちはは)の家(与謝野晶子)
※「ふるさとの海がたまらなく恋しい。」と初句で強く言い切ることで、作者の望郷の念が強く伝わってきます。
※歌意:ああ、ふるさとの海が恋しい。遠くから聞こえてくる波の音を数え数えしては、夢多い少女に育っていった、あの懐(なつ)かしいふるさとの、父母の家よ。
(2)二句切れ
・信濃路(しなのじ)は いつ春にならん。/夕づく日 入りてしまらく 黄なる空の色(島木赤彦)
※「信濃路はいつになったら本格的な春を迎えるのだろう。」と、重い病に臥(ふ)して苦しみつつも、春の訪れを待ちわびる作者の祈りに似た思いが伝わってきます。作者、島木赤彦はこの歌を詠んだ翌月に四十九歳で亡くなりました。
※歌意:信濃路(しなのじ)の春はおそい。草木の芽吹きも花の季節も、まだ先のことである。西の空は、夕日が沈んでしばらくの間、黄色に染まっている。ただ、やわらかな黄色に染まったその夕映(ゆうば)えだけが、春の始まりを告げている。信濃の国には、いつ春がやってくるのだろう。重い病に臥(ふ)した私は、祈りににた思いで、彼方の夕映えを見つめる。
(3)三句切れ
・いつしかに 春の名残(なごり)と なりにけり。/昆布(こんぶ)干場(ほしば)の たんぽぽの花(北原白秋)
※昆布干し場の隅(すみ)にひっそりと咲いたたんぽぽを見つめながら、「いつの間にか春は過ぎ去って、たんぽぽはただその名残となってしまったのだなあ。」と、過ぎ去った春をしみじみと惜しむ作者の気持ちが伝わってきます。
※歌意:いつの間にか春は去ってしまったのだなあ。たんぽぽの花が昆布干場の隅(すみ)に、ひっそりと咲いている。
(4)四句切れ
・街(まち)をゆき 子どものそばを 通るとき みかんの香(か)せり。/冬がまた来る(木下利玄)
※「街を歩いていて、子どもとすれ違ったとき、ほのかにみかんの香りが漂(ただよ)ってきたことだ。」と、ふいに気づかされた季節の推移にしみじみと感じ入っている作者の思いが伝わってきます
※歌意:街を歩いていて、子どもとすれ違ったとき、ほのかにみかんの香りが漂(ただよ)ってきた。ああ、そうか、もう冬がやって来たのだなあ。
(5)句切れなし
・のど赤き 玄鳥(つばくらめ)ふたつ 屋梁(はり)にいて たらちねの母は 死にたもうなり。/(斎藤茂吉)
※生命の象徴である燕(つばめ)と滅び行く命とを対照させながら、作者の深い悲しみと慟哭(どうこく)とを印象的に伝えています。
※歌意:のどが鮮やかな赤い色をしたつばめが二羽やって来て、家の軒先(のきさき)の古びた屋梁(はり)の上に、まるでこれから起きるできごとを見守るかのようにして止まっているそんな中、私を生み育ててくださった最愛の母は、まさに今、死んでゆかれたことだ。
※一般には「マル(句点)が打てる所が句切れ」といった基準が提示されますが、そもそもどこにマルが打てるかの判断が小学生には困難な場合が少なくないようです。やはり歌の意味を考え、感じ、味わうという本来の学習を疎(おろそ)かにしてはいけません。
■五七調と七五調
(1)五七調とは
・【五音+七音】がひとまとまりになって、意味上密接なつながりを持つ歌の調子をいいます。
〈例〉【春過ぎて(5)・夏来たるらし(7)】+【白妙の(5)・衣干したり(7)】+(天の香具山)
※ボリューム的に『上/はじめ(五音)』が小さく、『下/あと(七音)』が大きいことから「安定感」が感じられ、素朴で力強く、また、荘重(そうちょう)な響きとリズムを与えます。この力強さや重々しさを「男性的」とたとえることもあります。
※【五音+七音】の組み合わせに重点が置かれるため、句切れは「二句切れ」か「四句切れ」となります。例に上げた歌は二句と四句の二か所で切れています。二句と四句のところで少し間を置いて声に出して読んでみてください。(はるすぎて、なつきたるらし。/しろたえの、ころもほしたり。/あめのかぐやま。)
※歌の意味は、「春は知らぬ間に過ぎ、いよいよ夏がやって来たらしい。/真っ白な衣(ころも)が干してあるのが鮮やかに見えている。/あの青葉のみずみずしく茂った天の香具山(かぐやま)のふもとに。/」です。(持統天皇作)
※「五七調」は奈良時代の万葉集に多く見られましたが、平安時代に入り、やがて「七五調」に取って変わられました。
(2)七五調とは
・【七音+五音】がひとまとまりになって、意味上密接なつながりを持つ歌の調子をいいます。
〈例〉(心なき)+【身にもあはれは(7)+知られけり(5)】+(しぎ立つ沢の)+(秋の夕暮れ)
※ボリューム的に『上/はじめ(五音)』が大きく、『下/あと(七音)』が小さいことから「軽快感」が感じられ、流麗(りゅうれい)で優美な響きとリズムを与えます。この流れるような滑らかさを「女性的」とたとえることがあります。
※【七音+五音】の組み合わせに重点が置かれるため、句切れはその前後である「初句切れ」か「三句切れ」となります。例に挙げた歌は「三句切れ」です。三句のところで少し間を置いて声に出して読んでみてください。(こころなき・みにもあわれは・しられけり。/しぎたつさわの・あきのゆうぐれ。)
※例に挙げた歌の意味は、「俗人(ぞくじん)の感情を絶ち切った出家僧(しゅっけそう)である私の身にさえ、しみじみとした情趣が感じられることだ。/鴫(しぎ)が飛び立つ水辺の、秋の夕暮れのこのものさびいい風情には。/」です。(西行作)
※平安時代に入り、「七五調」は奈良時代に全盛だった「五七調」に取って変わりました。「古今和歌集」で盛んに用いられ、以後も『平家物語』や歌舞伎の台詞(せりふ)、また、近代に入ってからも新体詩や唱歌など、和歌に限らず広く用いられるようになりました。
■参考
・次の例で「五七調」と「七五調」それぞれの調子や印象の違いを比較してみよう。
(1)五七調
※厳かで重々しく、力強いリズムとなっています。(男性的)
・『椰子(やし)の実』(島崎藤村)
名も知らぬ 遠き島より(五音+七音)
流れ寄る 椰子の実一つ(五音+七音)
故郷(ふるさと)の 岸を離れて(五音+七音)
汝(なれ)はそも 波に幾月(いくつき)(五音+七音)
※歌意:名も知らない遠い島から、流れ着いた椰子の実が一つ。故郷の岸辺を離れてから、お前は一体どれだけの月日を、波に漂い続けていたのだろう。
・『題知らず』(読み人知らず)※古今和歌集(平安時代)
わが君は 千代に八千代に(五音+七音)
さざれ石の 巌(いわお)となりて(六音+七音)
苔(こけ)のむすまで(七音)
※後の『和漢朗詠集』では「わが君は」が「君が代は」に変わっている。
※歌意:わが君は、千年も八千年も、お元気でいらっしゃいませ。小さな石が、長い年月を経て大きな岩となり、それに苔が生えるまで、末永く。
・弘法も 筆の誤り(五音+七音)※ことわざ
(2)七五調
※優美で、滑らかで、軽やかなリズムとなっています。(女性的)
・『耳』(ジャン・コクトー作、堀口大学訳)
私の耳は(七音)
貝のから(五音)
海のひびきを(七音)
なつかしむ(五音)
・「いろは歌」(平安時代)
色は匂へど 散りぬるを:イロワニオエド・チリヌルヲ(七音+五音)
我が世誰ぞ 常ならむ:ワガヨタレゾ・ツネナラン(七音+五音)
有為の奥山 今日越えて:ウイノオクヤマ・キョウコエテ(七音+五音)
浅き夢見じ 酔ひもせず:アサキユメミジ・エイモセズ(※七音+五音)
※歌意:花は色艶(あで)やかに咲くけれども、間もなく散り果ててしまう。人間の命もこの花と同じであって、永久に生き続けることはできない。それだから、空しい夢を見たり、人情におぼれたりする浮世(うきよ)の煩悩(ぼんのう)の境地から逃(のが)れて、ひたすら仏様にすがって、往生(おうじょう)を祈ろう。
・『にっぽん昔ばなし』(川内康範)※アニメ主題歌
坊やよい子だ ねんねしな(七音+五音)
いまも昔も かわりなく(七音+五音)
母のめぐみの 子守歌(七音+五音)
遠いむかしの 物語り(七音+五音)
・雉(きじ)も鳴かずば 撃(う)たれまい(七音+五音)※ことわざ
・「セブンイレブン いい気分」(七音+五音)※近年詐欺商法で名を馳せるコンビニのキャッチコピー。
⑤表現技法
(1)枕詞(まくらことば):「あおによし」や「たらちねの」などのような、ある言葉を引き出すためにその言葉の前に置かれる、主に五音の修飾語をいいます。歌の調子を整え、情趣を添えます。
(2)比喩(ひゆ):ものごとを他のものごとにたとえることで、印象をより鮮明にします。
(3)体言止め:結句の末尾を体言で止めることで、意味を強め、余情を持たせます。
(4)倒置法:語順を置き換えることで、意味を強め、印象を深めます。
(5)対句(ついく):対照的なものや似たものを並べることで、印象を強めます。
(6)反復法:同じ言葉をくり返すことで、意味を強め、リズムを生みます。
(7)呼びかけ法:対象に呼びかけるような言葉を用い、親しみの気持ちを表します。
(8)押韻(おういん):句の頭か末尾を同じ音でそろえ、リズムを生み、調子を整えます。
※併せて『詩の種類と表現技法』もご参照ください。
〈例〉
(1)金色(こんじき)の ちひさき鳥の かたちして 銀杏(いちょう)ちるなり 夕日の丘に(与謝野晶子)
①比喩:夕日を受けてひらひらと舞い散る鮮やかな黄色をした銀杏の葉を「金色をした小さな鳥」にたとえ、華やかで美しい絵画的な情景を印象づけています。
②倒置法:本来の「夕日の丘に・銀杏ちるなり」の語順を倒置して、意味を強めて余韻を残しています。
※歌意:秋の淡(あわ)い夕陽に照らされて、まるで金色をした小さな鳥が舞うように、岡の銀杏(いちょう)の葉がはらりはらりと散ってゆく。
(2)みちのくの 母のいのちを 一目見ん 一目見んとぞ ただに急げる(斎藤茂吉)
・反復法:「一目見ん(一目でも見よう)」の繰り返しにより、「生きているうちに母に一目でも会いたい」という作者の強い焦りや切実な思いがひしひしと伝わります。
※歌意:故郷山形にいる母、私を生み育ててくださった最愛の母が今、臨終(りんじゅう:今にも死のうとする時)を迎えようとしている。命あるうちに母に一目でも会おうと、ただひたすらに急いだことだ。
(3)これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂(おおさか)の関(蝉丸)
①対句:「行くも・帰るも」、「知るも・知らぬも」がそれぞれ対照関係にある語どうしであり、意味を強め、印象を深めています。
②体言止め:「関」という体言(名詞)で止め、余情を深めています。
※歌意:これがまあ、東国へ行く人も都へ帰って来る人も、ここで別れたり出逢(であ)ったり、また、互いに知る人、知らぬ人がここで逢(あ)うという、名に聞くあの逢坂(おうさか)の関(せき)なのだなあ。逢坂の関での人々の別れと出逢い、人生の断面を詠(うた)っている。
(4)くさふめば くさにかくるる いしずえの くつのはくしゃに ひびくさびしさ(会津八一)
①押韻:初句、二句、四句それぞれの頭に「く」の音を置いて韻を踏むことで、リズムを生み、調子を整えています。
②体言止め:句の末尾を「さびしさ」という名詞(体言)で止め、余情を深めています。
※歌意:今となっては歴史の時間の中に埋没(まいぼつ)し、姿をとどめない山田寺の跡地(あとち)を訪れ、生い茂る草を踏(ふ)み分けて歩いていると、ふと、私の乗馬靴(じょうばぐつ)の拍車(はくしゃ)が、何かに触れてこすれた音を立てた。それは、草に隠れて見えず、私の足元にあった山田寺の礎石(そせき)に当たって出た音だった。その乾いた音の、何と空(むな)しく、さびしい響きであったことだろう。
(5)我が母よ 死にたまひゆく 我が母よ 我(わ)を生まし 乳(ち)足らひし母よ(斎藤茂吉)
①反復法:「母よ」を三度繰り返し、死んでいかれようとしている自分の母親への痛切な思いが強調されています。
②呼びかけ法:「母よ」と心の中で「呼びかけの言葉」を三度も繰り返し、死んでいかれようとしている自分の母親への深い愛情が切実に響いてきます。
※歌意:私の母よ、死んでゆかれようとする私の母よ。私を生み育ててくださった、愛する母よ。
⑥枕詞(まくらことば)
(1)それ自体は直接の意味を持たず、(2)ある特定の言葉を修飾し、(3)短歌の調子を整え、歌に情趣を添えます。(4)音数は五音が普通ですが、三音や四音、六音などのものも少数あります。枕詞は約1200語あり、古くは実質的な意味を持っていたと考えられますが、時代が過ぎるにつれて形式化しました。また、俳句には季語を必ず詠み込まなければならないという決まりがありますが、短歌には枕詞を必ず読み込まなければならないという決まりは特にありません。
〈例〉
・あをによし 奈良の都は 咲く花の にほふがごとく 今盛りなり(小野老)
※「あをによし」が枕詞で、「奈良」を修飾しています。「青丹(あおに)」の語源については、「奈良山付近から塗料の顔料として用いた『青丹(青土)』を産出したことによるのではないか」と考えられていますが、よくわかっていません。「青丹」は、それと関連の深い「奈良」を修飾して歌の調子を整え、情趣を添えるために用いられているだけなので、「青丹の色は美しい」などと訳す必要はありません。
※歌の意味は、「奈良の都、平城京は、咲く花が色美しく照り映(は)えるように、今やまことに繁栄(はんえい)の極(きわ)みであることだ。」です。
※他に「あかねさす→紫」、「足引きの→山」、「石走(いわばし)る→垂水(たるみ)」、「草枕(くさまくら)→旅」、「白妙(しろたえ)の→衣」、「足乳根(たらちねの)の→母」「久方(ひさかた)の→光」などは基本として覚えておこう。
⑦感動を表す語
(1)直接心情語
「かなし・かなしさ」、「さびし・さびしさ」、「うれし・うれしさ」といった心情を直接表す言葉に作者の感動が込められている場合が多い。
〈例〉
・白鳥(しらとり)は 哀(かな)しからずや 空の青 海の青にも 染(そ)まずただよふ(若山牧水)
※ただ一面の青い世界にありながら、それに染められることなく孤高(ここう)を貫いているかのような白鳥の姿に、作者自身の「哀しさ」を思い重ねて歌っています。
※歌の意味は、「白鳥(しらとり)は悲しくはないのだろうか。空の青さにも海の青さにもとけ合うことなく、その白い姿のまま漂っている。」です。
(2)助詞や助動詞
「かな・けり・や・ぞ・たり・なり・よ・かも」などの語に感動が込められている場合が多い。
〈例〉
・大海(おおうみ)の 磯(いそ)もとどろに 寄する波 割れてくだけて さけて散るかも(源実朝)
※歌の意味は、「大海(たいかい)の磯(いそ)にすさまじく打ち寄せる波が、激しく岩にぶつかり割れてとどろき、砕(くだ)け散っていることだ。」です。
⑧短歌の数え方
短歌の作品は一首、二首と数えます。俳句の場合は一句、二句と数えるので、間違えないようにしよう。
⑨俳句と短歌の違い
・俳句は「五・七・五」の十七音で詠まれる世界で最も短い定型詩で、季語(季節を表す語)を一つ必ず詠み込むのが決まりとなっています。それに対し、短歌は「五・七・五・七・七」の三十一音を定型とした日本古来の詩形で、俳句と異なり、季語を必ず詠み込まなければならないという決まりはありません。
〈俳句の例〉
・古池や 蛙飛びこむ 水の音(松尾芭蕉) ※季語は蛙、季節は春
※句の意味は、「静かな、ひっそりとした古池に佇(たたず)み、しみじみとした情趣に浸(ひた)っていた。と、その時、一匹の蛙(かえる)が池に飛び込む小さな音が聞こえた。辺りの静けさを破ったその一瞬の水音がした後には、以前にもまして深い静寂の世界が広がったことだ。」です。
※併せて『詩の種類と表現技法』もご参照ください。
【関連ページ】
■短歌:枕詞 一覧表
【教材・資料:無料PDF】
■枕詞 一覧表(B4・1枚)
季語と旧暦
■季語と旧暦
・季語は昔使われていた旧暦(太陰暦、陰暦)をもとに分類されています。旧暦は月の満ち欠けによって日を決め、満月の日を十五日とした昔の暦です。現在採用されている新暦(太陽暦、陽暦)は地球が太陽の周りを一周する時間、365日を一年とするもので、明治六年(1873年)に採用されました。
・「立春」とは「春の始まる日」という意味で、旧暦で立春は一月の初めにあたりましたから、春の始まりの月は一月です。同様に夏は立夏を迎える四月から、秋は立秋を迎える七月から、冬は立冬を迎える十月からということになります。
※旧暦での立春は約30年に一度だけ旧暦1月1日と重なるが、ほとんどの年は元旦と重ならない。
・ちなみに新暦では立春が二月四日ごろ、立夏は五月六日ごろ、立秋は八月八日ごろ、立冬は十一月八日ごろですから、旧暦と違い春は二月から、夏は立夏を迎える五月から、秋は立秋を迎える八月から、冬は立冬を迎える十一月からとなります。
・ただし、厳密には立春の前日である節分(2月3日頃)までが冬であり、「節分」は冬の季語となります。以下、立夏の前日である5月4日頃までが春、立秋の前日である8月6日頃までが夏、立冬の前日である11月6日頃までが秋です。梅雨が明けて間もなく小学生たちは夏休みに入り、気候的には夏の盛りを迎えるわけですが、夏休みの中頃(8月7日頃)にはもう暦のうえでの秋を迎えることになります。
・俳句の季語は旧暦をもとに分類されており、新暦とは約1か月のズレ(遅れ)がありますから、今の感覚ではとらえにくいものがあり、注意が必要です。たとえば「七夕」は七月の行事ですが、旧暦では七月は秋の始まりの月でしたから、秋の季語となります。
・同じ春の季語でも「元旦」や「初夢」などと「茶つみ」や「八十八夜」などとは三か月近くも時期が離れており、陽気に相当の差があります。「梅」の花も「桜」の花に先立って咲きますから、季節の移ろいをも念頭に季語の学習を進めるとよいでしょう。
※旧暦と新暦… 新暦明治6年1月1日となったのは旧暦明治5年12月2日の翌日でした。よって、旧暦明治5年12月3日から12月30日の28日間は存在しません。月の満ち欠けをもとにした旧暦では一年が354日となり、新暦より11日少なくなります。三年で33日も少なくなりますから、三年に一度、「閏月(うるうづき・じゅんげつ)」を入れて調整しました(閏月の挿入は19年に計7回)。閏月とは、季節と日付を合わせるために、三年に一回付け加えた特別の月のことで、つまり、閏月のある年は一年が13か月あったということです。
【関連ページ】
■俳句:季語一覧表
【教材・資料:無料PDF】
■季語 一覧表 (B4・2枚)
■季語 写真 (B4・3枚)
月の古名(和風月名)
一月:睦月(むつき)
・「正月には人々が親しみ睦(むつ)み合って過ごす」ことから。(有力説)
二月:如月(きさらぎ)
・諸説あり。
・「寒いために更(さら)に衣(きぬ)を着る」という意味の「衣更着(きぬさらぎ)」から。(有力説)
・「陽気が発達する時季が更に来る」、という意味から。
三月:弥生(やよい)
・「草木がいよいよ生い茂(しげ)る月」。(定説)
四月:卯月(うづき)
・「卯花(うのはな)が咲く月」。(有力説)
※卯花…ウツギの別称。ユキノシタ科の落葉低木。枝先に多くの白い花を咲かせる。
五月:皐月(五月)(さつき)
・諸説あり。
・「佐(さ:田植え)をする月」。(有力説)
・「早苗(さなえ)月」から。
※早苗(さなえ)…稲の苗で、苗代(なわしろ)から田に移し植える頃のもの。
六月:水無月(みなづき)
・諸説あり。
・水無月の「無(な)」は「の」にあたり、「水の月」、つまり「田に水を引く月」という意味から。(有力説)
・「どの田も水をたたえている」という意味の「水月(みなづき)」から。
・「梅雨も終わって水も枯(か)れる月」。(俗説とされる)
七月:文月(ふみづき・ふづき)
・諸説あり。
・「七夕に短冊に文(ふみ:歌や字)を書いて書道の上達を祈った」ことから。(有力説)
・「文(ふみ:書物)を虫干しをする日である七夕のある月」であることから。
※虫干し…夏の晴天の日に衣類や書物等を箱から取り出して日光に当てたり陰干しして風を通し、湿り気やカビ、虫の害等を防ぐこと。
八月:葉月(はづき・はつき)
・諸説あり。
・「木の葉が黄色く染(そ)まる月」。
九月:長月(ながつき)
・「夜がようやく長くなる」という意味の「夜長(よなが)月」から。(有力説)
十月:神無月(かんなづき)
・諸説あり。
・「水無月」と同様、「無(な)」は「の」にあたる言葉であるため、「神の月」、つまり「神を祭る月」から。(有力説)
・「諸国(しょこく)の神々が一年のことを話し合うために出雲国(いずものくに)に集まり、出雲以外の国々には神が不在となる」ことから。(ただし、この説は中世以降に後付けされた民間伝承とされる)
※出雲国では「神有月・神在月:かみありづき」と呼ぶ。
※出雲国(いずものくに)…旧国名。現在の島根県東半部。
十一月:霜月(しもつき)
・「霜(しも)がしきりに降る」という意味の「霜降り月」から。(定説)
※霜(しも)…空気中の水蒸気が夜間に冷えた地面や物体に触れて、その表面に氷の結晶として凝結(ぎょうけつ)したもの。
十二月:師走(しわす)
・「歳(し)が果(は)つ(年が終わりに達する)」ことから。(定説)
・十二月には僧(そう)を迎(むか)えて仏事(ぶつじ)が行なわれるので、「僧が東西に忙しく駆(か)け回る月」であることから。(ただし、この説は中世以降に後付けされた民間伝承とされる)
■『月の古名』:無料PDFのダウンロード(A4・1枚)
いろは歌
■いろは歌(伊呂波歌)
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑひもせす
色は匂(にほ)へど(イロワニオエド)
散りぬるを(チリヌルヲ)
我(わ)が世誰(たれ)ぞ(ワガヨタレゾ)
常(つね)ならむ(ツネナラン)
有為(うゐ)の奥山(おくやま)(ウイノオクヤマ)
今日(けふ)越(こ)えて(キョウコエテ)
浅き夢見じ(アサキユメミジ)
酔(ゑ)ひもせず(エイモセズ)
■意味
花は色艶(あで)やかに咲(さ)くけれども
間もなく散(ち)り果(は)ててしまう
人間の命もこの花と同じであって
永久に生き続けることはできない
それだから
空しい夢を見たり
人情(にんじょう)におぼれたりする
浮世(うきよ)の煩悩(ぼんのう)の
境地(きょうち)から逃(のが)れて
ひたすら仏様にすがって
往生(おうじょう)を祈(いの)ろう
※浮世…辛(つら)くはかないこの世
※煩悩…悟(さと)りを妨(さまた)げる人間のさまざまな心の働き
※悟り…真理を会得すること。
※往生…極楽浄土に生まれ変わること
※極楽浄土…苦しみのない安楽の世界
(平安時代中期)
※ 仏教の根本思想である諸行無常(しょぎょうむじょう…万物は絶えず移り変わり生滅(しょうめつ)するもので、不変なものではないということ)の精神を訳したものです。
■ちなみに以下は、明治三十六年、黒岩涙香氏の主宰する新聞「万朝報(よろずちょうほう)」で「国音の歌」として「ン」を入れた四十八字の歌を懸賞募集した際に第一位を獲得した、埼玉の坂本百次郎という人の作による「新いろは歌」です。
■新いろは歌
とりなくこゑす ゆまさませ
みよあけわたる ひんかしを
そらいろはえて おきつへに
ほふねむれゐぬ もやのうち
鳥なく声(こゑ)す(トリナクコエス)
夢さませ(ユメサマセ)
見よ明けわたる(ミヨアケワタル)
東(ひんかし)を(ヒンガシヲ)
空色(そらいろ)映(は)えて(ソライロハエテ)
沖(おき)つ辺(へ)に(オキツベニ)
帆(ほ)ふね群れゐぬ(ホフネムレイヌ)
もやのうち(モヤノウチ)
■意味
鳥のさえずりが聞こえてくる
夢から醒(さ)めようか
見てごらん
明け渡る東の空一面を
薄明(はくめい)鮮やかに
沖の方(かた)には
帆船(ほふね)が幾艘(いくそう)も
群れ漂(ただよ)っている
静かな朝靄(あさもや)の中に
(新伊呂波歌 明治三十六年)
■『いろは歌』:無料PDFのダウンロード(A4・1枚)
■剽窃について
■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。
①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。
・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。
②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。
・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。
③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。
・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。
④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。